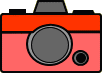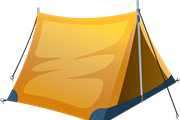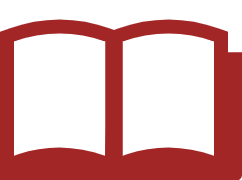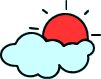むかし、むかし、そのむかし、十万年も前の昔のこと! 大きな山が・・・とつぜん大噴火! 噴煙は空高く上がり風に流されて火山灰が九州から東北地方まで積ったそうだ  雨が降り、山々が崩れ、洪水が土砂を運び・・・平野ができ・・・草木が繁り・・・その後も噴火や洪水が繰り返されて時が過ぎた  やがて、最終氷河期も終り・・・ 縄文時代になり・・・ |

 稲佐の浜から望む三瓶山  三瓶山は 国引き神話で国引きの綱を繋ぎ止めた杭の山 |
むかし、むかし、そのむかし、十万年も前のむかしのこと!. 大きな山が・・・とつぜん大噴火! 噴煙は空高く上がり風に流されて火山灰が九州から東北地方まで積ったそうだ  雨が降り、山々が崩れ、洪水が土砂を運び・・・平野ができ・・・草木が繁り・・・その後も噴火や洪水が繰り返されて時が過ぎた |
やがて最終氷河期も終り・・・
縄文時代に・・・
|
年代 INDEX

| 今 か ら |
時 代 |
三瓶山や郷土のできごと |
| 115~100万年前 | ||
| 100万年前 | 石見銀山の鉱床ができる(島根ジオサイト)。大江高山火山群のマグマ熱水によってできた鉱床。仙ノ山の東西約2Km、南北約1Kmの範囲に分布、600以上間歩、
石見銀山(中国地質調査業協会) |

 11~10万年前 |
 旧 石 器 時 代 |
三瓶山が噴火。噴火で噴出された火山灰は東北地方まで分布する.地質の鍵層(三瓶木次テフラ:SKP)
|
| 9万年前 | ||
| 7万年前 | 三瓶山が噴火。三瓶大田軽石流(宍道湖中海ジオパーク)が海岸まで到達する。三瓶雲南軽石(火山灰)が広く積もる
・カルデラが形成される、志学展望広場
・降下軽石流に埋った出雲市横見埋没林が発見される |
|
| 7~2万年前 | 最終氷河期(wiki)で海面が低く動物や人が陸伝いに往来する
|
|
| 6~5万年前 | 大山が噴火(wiki)。大規模な噴火で大量の火山灰、軽石や火砕流を噴出
火山灰は遠く福島県まで降り積る(大山倉吉軽石:DKP:wiki) |
|
| 5~3万年前 | 三瓶山が噴火。三瓶池田降下軽石:SI.志学展望広場
・三瓶池田テフラ と三瓶浮布テフラの年代決 (JSSCP)
|
|
| 2.9万年前 | 姶良カルデラ:姶良Tn(AT)(wiki)、火山灰は遠く丹沢まで降り積る |
|
| 2万年前 | 三瓶山が噴火、日影山はこの頃の溶岩ドーム
・地質の鍵層(三瓶浮布テフラ:SUk)
・三瓶火山第IV期・浮布降下軽石堆積物の年代三瓶自然館
・三瓶池田テフラ と三瓶浮布テフラの年代決 (JSSCP) |
|
| 1.9万年前~ | 縄 文 時 代 |
最終氷河期が終わり海面の上昇が始まる縄文海進(wiki) |
| 1.3万年前 | 三瓶山が噴火。志津見降下火山灰、切割降下火山灰堆積物
・表裏条痕文土器(約1万年前:板屋3遺跡):飯南町のできごと(飯南町志津見)からおよそ1万年前の土器が見つかる |
|
| 7300年前 |
火山灰は東北地方まで積もる(K-Ah)
|
|
| 6500年前~ | 海面の上昇のピーク、現在より約5m高くなる縄文海進(wiki)
縄文時代の海進について(日本第四紀学会) |
|
| 5600年前~ | 三瓶山が噴火
・角井降下火山灰堆積物、志学火砕流堆積物、志学降下火山灰堆積物
|
|
| 5000年前~ | 古宍道湾:斐伊川からの土砂の供給によって埋め立てが進み東西2つの水域に分かれる、宍道湖・中海のおいたち(島根県)
・下山遺跡(角井)貝谷遺跡:飯南町のできごとから磨消縄文土器(約4000年前)がみつかる
・五明田遺跡(八神):指定文化財解説から赤色顔料が施された縄文土器(約4000年前)がみつかる |
|
| 4000年前 | 三瓶山が噴火
・火砕流や岩屑なだれに山麓の森(縄文の森)が土中に深く埋まる
・平成10年(1998)11月に発見され、翌年1月一般公開と現地説明会が行なわれる。縄文の森・三瓶小豆原埋没林(日本遺産)
|
|
| 2600年前~ | 約2600~2500年前の大田市仁摩町古屋敷遺跡(古代出雲歴史博物館)、彩文土器が出土する
2500年前頃の出雲山間部で東西文化交流の木次町万場Ⅰ遺跡が発見される
スサノオ神話は縄文から弥生への頃でしょうか?八岐大蛇神話 |
|
| 2400年前〜 | 弥 生 時 代 |
西川津遺跡(島根県)から土笛(島根県)が多数出土する、稲作と共に持ち込まれたと思われる |
御堂谷遺跡(大田市長久町・鳥井町、弥生時代前期:紀元前2~3世紀)が発見される。山陰地方では類例の少ない高地性集落とみらる。島根県 |
||
| 2200年前 前後~ |
九州北部から銅矛が伝わる。出雲型銅剣が製作される |
|
田和山遺跡(島根県)(弥生前期後半~中期後半)、環壕が発見される |
||
| 2000年前 前後~ |
||
このころの遺跡、荒神谷博物館
|
||
このころ中国山地山間部で鉄器を製作する集落が営まれる |
||
2~3世紀、塩津山墳墓(荒島地区活性化推進協議会) 四隅突出墓・方墳、出雲地方の東に大勢力か |
||
239年(景初3年)、倭国の卑弥呼が魏に遣使、銅鏡を百枚を賜る(wiki) |
||
| 2世紀後半~3世紀、西谷墳墓群(国:wiki) 四隅突出型墳丘墓、祭祀の跡確認、出雲に王の存在 |
||
| 1800年前 前後~ |
古 墳 時 代 |
3世紀後半、神原神社古墳(wiki)、神原神社古墳発掘で景初3年銘の三角縁神獣鏡(出雲歴史博物館)が出土する |
4世紀後半、スキモ塚古墳(wiki)前方後円墳、築造時期は4世紀後半、全長96m、出土した円筒埴輪などが大元古墳のものと酷似(読売新聞:2022.10.29) |
||
4~6世紀後半、造山古墳(wiki)古代出雲王陵の丘の中にある。副葬品に三角縁神獣鏡 |
||
413~502年、倭の五王(wiki)が中国の宋王朝へ使者を派遣(朝貢)する |
||
5世紀中頃の、古曽志大谷1号墳(松江市)、前方後円墳 |
||
513年、勅命により「石見一宮物部神社」の社殿ができる物部神社さんのHP |
||
| 538年・552年、百済から仏教の伝来(公伝)(wiki)する | ||
6世紀中頃の、山代二子塚古墳(国:wiki)、全国有数の規模、土層の見学ができる施設 |
||
6世紀中頃の、今市大念寺古墳(国:wiki)、前方後円墳、日本最大級の家形石棺 |
||
6世紀後半の、岡田山古墳(国:wiki)、出土大刀に「各田卩臣(額田部臣)の文字 |

詳しい三瓶山火山はこちら
今から 年前~
| 西暦 和暦 |
で き ご と |
| 587年 | |
| 593年 | 聖徳太子(wiki)が推古天皇の摂政となる。仏教興隆の詔(594) |
| 604年 | 推古天皇12年、十七条憲法が制定される(wiki) 和を尊ぶこと、仏教を敬うことなど17条 |
| 645 大化 元年 |
|
| 659 斉明5年 |
出雲国造に命じて杵築大社を造営(修造)させる 明治4年(1874)に出雲大社と改称 |
| 663 天智2年 |
韓国百済滅亡 倭国・百済連合軍白村江の戦い(wiki)で唐と新羅連合軍に敗北を喫す |
| 672 天武元年 |
壬申の乱(wiki)日本古代最大の内乱戦争、大海人皇子が勝利) |
| 684 白鳳 13年 |
10月14日(11/29)、白鳳の南海・東海地震(M8.0)(防災システム研究所)
・当大地震で「佐比賣山ノ西崖崩落」して渓谷が塞き止められ浮布池ができたとの伝聞がある |
| 701 大宝元年 |
| 710 和銅 3年 |
元明天皇(wiki)が平城京(奈良)に都を移す(遷都) |
| 712 和銅5年 |
|
| 713 和銅6年 |
元明天皇の詔により風土記編纂が命ぜられる
・郡郷の地名(好字を用いて)、産物、土地の肥沃の状態、地名の起源、伝えられている旧聞異事など(三瓶山 歴史と伝説 石村禎久著) |
| 715 霊亀元年 |
|
| 718 養老2年 |
佐比賣山に外敵(新羅)に対する烽(とぶひ)が置かれる 志学ホームタウンプロジェクト |
| 720 養老4年 |
日本書紀(wiki)が完成。奈良時代に成立した日本の歴史書、第八段一書第五。五十猛命、つま津姫命、大屋津姫命は、全国の山々に木種を撒く |
| 726 神亀3年 |
佐比賣山(さひめやま)から三瓶山(さんべさん)に改名(石村禎久著:三瓶山)
五十猛村を磯竹村に改称(ふるさと読本 西部ブロック推進協議会)、明治22年の町村制時に五十猛村へ |
| 733 天平5年 |
|
| 743 天平15年 |
墾田永年私財法(wiki) 自分で新しく開墾した耕地は本人が所有できる制度 |
| 770 宝亀元年 |
大乗寺が室の内に創立.志学ホームタウンプロジェクト |

今から 年前~
| 794 延暦13年 |
桓武天皇(wiki)が平安京(京都)に都を移す(遷都)10月22日 |
| 850 嘉祥3年 |
甘露が降り石見国の国守(笠峰雄)が文徳天皇に献上する→以来この地を甘屋村と称する |
| 864 貞観8年 |
富士山が噴火する(wiki)。大規模な溶岩が流れる |
| 880 元慶4年 |
10月14日(880/11/23)、出雲地震 M7.0?)が起きる(三代實録)地震調査研究推進本部 |
| 889 寛平元年 |
このころ波根に宝台寺が建立される |
| 891 寛平3年 |
このころ佐比賣山神社(多根)、大己貴命、小彦名命、須勢理姫命鎮座
このころ三瓶神社(藤木)、大国主命、八島土奴美命、大年神鎮座(旧山口村郷土の歴史) |
| 931 承平元年 |
このころ霊椿山・円城寺(野城)が開山される(930〜946年) 開基は、朝満上人 |
| 1026 万寿3年 |
5月23日(6/16) 益田・高津沖で M7.6 の地震(CiNii)。鴨山が海に没し(wiki) 鳥井町では津波が襲い船が峠まで押し上げられる (船越坂と名付ける:島根県技術士会)、 バス停:船越坂(Mapion) |
| 1108 天仁元年 |
出雲杵築大社本殿が転倒(出雲大社HP)する.1031、1061、1109、1141、1172、1225年等の記録も |
| 1115 永久3年 |
出雲杵築大社が正遷宮「寄木の御造営」(出雲大社HP)(仮殿の遷宮は1108年) |
| 1150 久安6年 |
平安時代末期の日本の総人口は、680万人(厚生労働省) |
| 1160 平治元年 |
12月9日、平治の乱(1/19)(wiki)、平清盛が熊野詣の留守中に起きた異変 |
| 1181 治承5年 |
平清盛(1118年~1181/3/20)(wiki)は熱病で死去する |
| 1185 文治元年 |
3月24日(4/25)、源義経、壇ノ浦で平氏(平家礼賛のホームページ)を滅ぼす |
今から 年前~
| 西暦 和暦 |
で き ご と |
| 1192 建久3年 |
源頼朝征夷大将軍となり、鎌倉幕府(wiki)をひらく |
| 1204 元久元年 |
大田に大願寺が建立される.新纂浄土宗大辞典 |
| 1205 元久2年 |
山口八幡宮の勧請 井屋ヶ迫伝説と遷座(元亀2年1571年) |
| 1206 建永元年 |
このころ 明光上人の指書きの名號 が建立されたと思われる |
| 1221 承久3年 |
承久の乱、後鳥羽上皇は隠岐(隠岐神社HP)に、順徳上皇は佐渡に配流される |
| 1225 嘉禄元年 |
室の内にあった八面神社を洪水のため金比羅坂に移遷(志学ホームタウンプロジェクト)
|
| 1281 弘安4年 |
石見海岸に18の砦が築かれる(浜田市)、元寇(蒙古襲来)wikiの来襲に備える(8月) |
| 1306 徳治元年 |
波根湖の水を排水。有馬氏が開掘し日本海へ疎水(掛戸松島:立久手公民館) |
| 1332 元弘2年 |
4月、後醍醐天皇は隠岐(西郷町)に流される |
| 1333 元弘3年 |
後醍醐天皇は隠岐を脱出(大山町)、鎌倉幕府は新田義貞らの軍に滅ぼされる |

| 1338 暦応元年 |
足利尊氏(wiki) 征夷大将軍となる |
| 1527 大永7年 |
石見銀山 博多の商人「神屋寿禎」が発見し領主大内義興(wiki)の支援で銀を掘り出す(注.1527年説が有力:石見銀山学ことはじめ)
 ・大永時代に佐津目銅山が開山する~昭和30年代まで断続的採鉱が続く(山口町郷土館) |
| 1530 享禄3年 |
石見銀山は、小笠原長隆が銀山を奪うも、大内義隆が奪回する |
| 1533 天文2年 |
石見銀山 灰吹法(はいふきほう)による銀精錬が開始される(それまでは銀鉱石を博多などに積み出していた:精錬は博多や朝鮮半島) |
| 1537 天文6年 |
石見銀山に尼子経久(wiki)侵攻し大内氏の銀山を奪う。石見銀山は尼子氏の支配下になる |
| 1560 永禄3年 |
|
| 1562 永禄5年 |
毛利元就は出雲侵攻を開始する。霊椿山・円城寺(931年~)は、毛利氏の追討の劫火で炎上し多くが灰となる |
| 1566 永禄9年 |
毛利元就は富田城を攻め富田城は落城し尼子義久(安来市観光協会)は降伏(11月) 毛利氏は中国地方8ヶ国を支配する大名になり、石見銀山は毛利氏の独占となる |
| 1573 元亀4年 |
15代将軍足利義昭が織田信長に追放される。室町幕府の滅亡(wiki) |

 1580 1580天正8年 |
石見銀山で、安原伝兵衛が有望鉱脈「釜屋間歩」などを発見する(石見銀山資料館) |
| 1582 天正10年 |
織田信長(wiki)(1534?~1582/6/21)は、明智光秀の本能寺の変で倒れる。清洲会議を経て豊臣秀吉は天下人となる |
| 1584 天正12年 |
毛利輝元は豊臣秀吉に服属。石見銀山は豊臣・毛利の共同管理となる |
| 1597 慶長2年 |
毛利輝元、銀3000枚(129貫)を秀吉に献上する |
| 1598 慶長3年 |
太閤秀吉(wiki)は伏見城で没する(1536?~1598/9/18) |
| 1600 慶長5年 |
9月15日(10/21)、徳川家康の東軍は、関ヶ原で西軍を撃破する(関ヶ原の戦い:wiki)
11月、石見銀山接収に大久保長安を下向させ石見銀山地域を幕府直轄地の天領とする |
| 1601 慶長6年 |
大久保石見守長安(1545~1613年) wiki、石見銀山奉行となる |
| 1602 慶長7年 |
石見銀山 年産4000貫(15トン)の銀を産出する |

今から 年前~
 西暦 和暦 |
で き ご と |
| 1603 慶長8年 |
徳川家康(wiki) 征夷大将軍となる |
| 1603 慶長9年 |
慶長地震(wiki)、1605/2/3 駿河湾から徳島沖を震源、推定M8.0、津波が最大10m |
| 1611 慶長16年 |
松江城が完成する。現存天守12城(国宝5城)(wiki) (松江城のHP) |
| 1638 寛永16年 |
2月、松平直政(wiki)、信州松本(7万石)から松江藩(wiki)に移封(18万6千石)
 ・斐伊川は、寛永12、16年の洪水により東に流路を変えて宍道湖に注ぐ(国土交通省) |
| 1643 寛永20年 |
吉永藩の誕生(wiki)、会津藩から転封(wiki)、
42万石から1万石へ転封、財政難のため年貢高率課税が行なわれる、その後に起きる騒動の遠因なる |
| 1667 寛文7年 |
|
| 1670 寛文10年 |
西の原に放牧、吉永藩が種牛を購入し放牧する(NHK食べ物新世紀) |
| 1675 延宝3年 |
前年の寅の大洪水などにより石見地方大飢饉となる。吉永藩は窮民に米麦の粥などで救済する |
| 1676 延宝4年 |
津和野地震 M6.5 (地震調査研究推進本部)津和野城石垣崩れる、潰家133、死者7人 |
| 1682 天和2年 |
吉永藩(1643年〜の40年間、安濃郡20ヶ村)は、水口藩(wiki)に転封となる。領地は天領(石見銀山領)となる |
| 1690 元禄3年 |
石見銀山の産銀量がピークとなる:1690年:612.840貫、1691年:625.705貫(石見銀山ことはじめⅠ)
ちなみに銀1貫の価格は、現代で約1,250,000円とのこと(古文書ネットさん)→7億6605万円ですね
|
| 1693 元禄6年 |
2018年の江の川の水害で被害を受けた江津市桜江町の旧家の蔵を片付けているときに、元禄6年の古文書が発見される
・石州銀山近里巡礼縁起 桜江古文書を現代に活かす会
・霊椿山・円城寺は14番札所 |
| 1702 元禄15年 |
|
| 1707 宝永4年 |
10月 4日(10/28)、宝永地震(wiki)、太平洋沖を震源として推定M8.6、県下で震度6
 11月23日(12/16)、富士山が噴火する(宝永の大噴火:Wiki)江戸市中に火山灰積もる |
| 1731 享保16年 |
井戸平左衛門正明(wiki)、9月13日に第19代大森代官に着任する |
| 1732 享保17年 |
|
| 1744 延享元年 |
|
| 1773 安永2年 |
松江藩。北の原(徳原)で薬用人参を栽培(島根県)する。5ha余 |
| 1783 天明3年 |
天明の飢饉(wiki)6〜8月長雨・洪水・冷気により飢饉となる。大田で百姓一揆起きる |
| 1792 寛政4年 |
4月1日(5/21)雲仙岳眉山で山体崩壊と津波が発生する(wiki)、死者行方不明 15000人 |
| 寛政年間 | ・三瓶山十二勝、志学出身の医師「今田知郷」が三瓶山周辺の十二勝を依頼・制作された日本画・和歌・漢詩 三巻の巻物(志学ホームタウンプロジェクト)、湯谷温泉の和歌はこちら |
| 1800 寛政12年 |
3月 石見銀山 邇摩郡佐摩村大森で大火にみまわれる。市中残らず消失する |
| 1806 文化3年 |
801年伊能忠敬全国測量に着手。石見〜出雲沿岸測量が行なわれる(6/5日〜8/8日) |
| 1835 天保6年 |
三瓶山付近で地震、M5.5、(地震調査研究推進本部) |
| 1836 天保7年 |
天保の大飢饉(wiki)。銀山領内は大凶作となるも甘藷で食をつなぐ |

 1853 嘉永6年 |
6月3日(7/8)黒船来航(wiki)、アメリカ合衆国海軍東インド艦隊(4隻)の蒸気船が日本に来航する |
| 1854 嘉永7年 安政元年 |
1月16日(2/13)、ペリー再来港、日米和親条約(wiki)。江戸幕府とアメリカ合衆国が締結する
11月5日(12/24)、安政南海大地震(wiki)。M8.4、鳥井村で全壊34戸の記録がある |
| 1858 安政5年 |
12月2日(1/5)、石見(那賀郡、美濃郡)で地震、M6.2 地震調査研究推進本部 |
| 1859 安政6年 |
9月9日(10/4)、石見(那賀郡、美濃郡)で地震、M6~6.5 地震調査研究推進本部 |
| 1864 元冶元年 |
3月13日(4/18)、富山村才坂長沢で野火が燃え下り全戸が焼失する。死者1名 |
| 1865 慶応元年 |
|
| 1866 慶応2年 |
|
| 1867 慶応3年 |
10月14日(11/9)、徳川慶喜は大政奉還(wiki)を上奏し勅許される
 11月15日(12/10)、坂本龍馬(wiki)は京都の近江屋で刺客に襲われ暗殺される |

今から 年前~
 西暦 和暦 |
で き ご と |
| 1868 明治元年 |
慶応4年9月8日(10/23)に改元(wiki)。元日に遡って元号が摘要される
 ・日本の総人口は、3,400万人(厚生労働省) |
| 1869 明治2年 |
享保17年につぐ凶作となる
大森県が置かれ管轄となる(県庁は邇摩郡佐摩村)
 長崎浦上(wiki)のキリスト教徒90名松江藩、150余名津和野藩(wiki)預りとなる |
| 1870 明治3年 |
大森県が改称され浜田県(wiki)管轄となる(県庁は那賀郡浅井村)。松江藩は農兵・町兵を廃止、帰農・帰商を許可する。前年凶作のため飢餓、物価高騰 |
| 1871 明治4年 |
杵築大社と称されていたが、出雲大社(いずもおおやしろ)(wiki)と改称する
・山口は神門郡第33区に入り区会所を窪田に置く(小学校の百ニ十年)
・11月、松江、広瀬、母里の3県が合併して島根県が生まれる(島根県の県名由来) 明治14年に現在の島根県ができる |
| 1872 明治5年 |
2月6日(3/14)16時40分頃浜田地震(wiki)起きる。M7.1、浜田、邑智、大田で震度7(推定)死者551名
 多根では、余震のために水田に小屋掛けして住む(寒さと余震に難儀する)、山口では、徳原池に亀裂生ずる(旧山口村 郷土の歴史)
 五十猛村大浦では、地震発生の15分前に8尺(2.4m)海面が低下した記録がある
    8月2日、学制が太政官より発される(wiki)、小学校を義務化し国民皆学をめざす
 12月3日、太陽暦(グレゴリオ暦)採用(wiki)され、この日が明治6年1月1日となる。準備不足で大混乱となる。24時間制も同時に採用され、「とき」から0~24時になる。注.数え年齢が満年齢になるのは昭和24年
|

ここから太陽暦表示(新暦)

 西暦 和暦 |
で き ご と |
| 1873 明治6年 |
2月多根村に多根学校開校する(ふるさと百年)→明治26年多根尋常小学校に改称
 廃城令が公布(wiki)。
明治8年松江城は払い下げて撤去、天守閣も180円で売却、その後勝部本右衛門、高城権八らにより買い戻され取り壊しは中止される(松江城HP) |
| 1874 明治7年 |
5月、西善寺仮校舎で出雲国山口小学校開校する(旧山口村郷土の歴史)→明治23年新築移転 |
| 1875 明治8年 |
|
| 1876 明治9年 |
石見国は廃藩置県で島根県へ (明治2年大森県→明治3年浜田県→明治9年島根県) |
| 1879 明治12年 |
県下でコレラが流行。死亡2149名(県大年表)
井戸神社建立(第19代代官井戸平左衛門正明を祀り遺徳を偲びさつまいもを奉納)
|
| 1881 明治14年 |
県下で風雪と厳寒、松江で85cm
宍道湖が凍結し人馬の通行が試される。 |
| 1883 明治16年 |
県下で大旱魃、6~8月降雨無し。四国では7/21~9/17降雨無し(四国災害アーカイブス) |
| 1886 明治19年 |
志学温泉は雪崩で全壊(志学ホームタウンP)下流に引湯、浴場や旅館を設ける
 三瓶高原で広島第五師団野砲第五連隊が初めて高原の砲撃演習を実施する。明治32年には浜田第21連隊、明治39年には松江63連隊も使用を始める(終戦まで) |
| 明治 中期 |
多根から大田方面に荷車が通る道が開ける(木橋も架けられる)
荷馬車の登場で人力と牛馬の荷役は終わり、車引きの多くは失業する(ふるさと百年) 農林業資材や機材も搬入され農作業が軽減される |
| 1888 明治21年 |
佐比賣村、志々村、山口村の有志により三瓶牧畜組合が設置される(ふるさと百年) |
| 1889 明治22年 |
4月、町村制が施行される
・山口は、神門郡山口村(wiki)←山口村、佐津目村、吉野村、高津屋村、上橋波村、下橋波村の6ヶ村合併
・多根は、安濃郡佐比賣村(wiki)←野城村、多根村、小屋原村、上山村、志学村、池田村の6ヶ村合併、昭和29年まで村名は続き市制時で三瓶町に |
| 1891 明治24年 |
9月、三瓶山で砲兵演習、第5師団野戦砲兵第5連隊が射撃演習(浜田21,松江63連隊) |
| 1894 明治27年 |
県下で旱魃。5~7月まで降雨なく田面亀裂(県大年表) |
| 1895 明治28年 |
神西から志学への陸軍道路がつくられる(大須~佐津目尾根道:小学校の百ニ十年) |
| 1896 明治29年 |
4月、郡制の施行。出雲郡、神門郡、楯縫郡は合併して簸川郡(wiki)となる、郡役所は今市町
山口村は簸川郡山口村となる(昭和23年に再編成、昭和29年に大田市に編入) |
| 1900 明治33年 |
小学校令により尋常小学校4年の修学が義務ずけられる(小学校の百ニ十年)、6年になるのは明治40年
10月、第1回中国5県連合畜産共進会が志学で開催される |
| 1903 明治36年 |
安濃郡立農学校設立(現大田高校)、邇摩郡立石東農学校創立
 日御碕灯台が完成、高さ43.65m(海抜63.3m)で東洋一 |
| 1904 明治37年 |
9月21日、大田彼岸市は秋にも開催される。以降年2回春秋に開催される |
| 1905 明治38年 |
5月27~28日、日露戦争日本海海戦
那賀郡都濃村にイルテッシュ号が漂着224人上陸、美濃郡鎌手村にウラール号の21人がボートで漂着、五十猛の大鼻崎に監視所を設置
6月2日、芸予地震 M7.2。志学(三瓶)温泉の泉温が43度位にもなる(志学ホームタウンP)
12月8日、石見地方で地震振動回数10、家屋の壁に亀裂(県大年表) |
| 1907 明治40年 |
小学校令が改正され小学校の義務年齢が6年となる(小学校の百ニ十年) |
| 1908 明治41年 |
多年報徳社創立→その後報徳会に改称→昭和35年多根自治会に改称される
・東の原に兵舎15棟が建設される(堺市から移設) |
| 1908 〜 1921 |
・山陰線の鉄道が開通する。松江(1908年)、出雲今市(1910年)、石見大田(1915年)、餘部鉄橋等の完成により京都~出雲今市の間が全線開業する(1912/3/1)
・明治の末期より大正の初期にかけて、稚児滝の滝水を利用した水力タービンの出光製材所が設けられていた 木切り、木出し、製材人夫等で多根野城の多くの人が仕事にありついたものだといわれてい(るふるさと百年) |
| 1910 明治43年 |
三瓶山の浮布池で養鱒を計画し十和田湖より姫鱒卵を養殖する(歴史大年表) |
| 1911 明治44年 |
8月、山口村山口尋常小学校は渡瀬に開校、山口小と佐津目小が統合する |

今から 年前~
 西暦 和暦 |
で き ご と |
| 1912 大正元年 |
7月30日、改元。7月30日から大正となる
 ・日本の総人口は、5,000万人を越える(厚生労働省) |
| 1913 大正2年 |
大田変電所ができる(松江電灯)、大田町内に配電され電灯がともる |
| 1914 大正3年 |
1月12日、桜島大噴火(wiki)、大量の溶岩で大隅半島と地続きになる
 7月、第一次世界大戦が勃発する(1914~1918年) |
| 1915 大正4年 |
7月 7日、「島根県安濃郡誌 島根県安濃郡役所」が発行される
7月11日、石見大田駅開駅。京都~石見大田まで鉄路が繋がる
・農水産物や鉱工品の輸送により産業の活性化が図られる
・多根山口地区は木炭の出荷で現金収入が図られ炭焼きは一大産業となる。昭和初期のトラック搬送までの間は荷馬車も忙しく行き通う(農閑期の現金収入が魅力)
11月、窪田発電所:発電開始する(水のプログラム)。山口村に電灯が付くのは大正15年 |
| 1917 大正6年 |
1月、県下で厳寒と大積雪。三瓶でも積雪により家屋崩壊。気温−13℃の厳寒 |
| 1918 大正7年 |
・スペイン風邪、松江市では人口4万人のうち2.4万(60%)が感染(島根県:山陰新聞)
11月、山陰線、石見大田−浅利間開通 |
| 1919 大正8年 |
5月大暴風、五十猛村漁船が大被害を受ける
 県中部で地震、M5.8、震源は三次市、地震調査研究推進本部 |
| 1920 大正9年 |
1月、ベルサイユ講話条約後に国際連盟発足する。1946年国際連盟は解散する
3月、戦後恐慌で株価暴落 |
| 1921 大正10年 |
出雲山口郵便局が開設される(12月6日開局し、閉局は昭和58年4月3日)
 三瓶山麓のわさびは、わさび腐敗病 の大発生で壊滅的被害を受ける |
| 1922 大正11年 |
ブラーゲー(ドイツ人)が 三瓶山で初めてスキーを試みる
6月~旱魃被害が広がる |
| 1923 大正12年 |
9月1日午前11時58分、関東大震災(wiki) M7.9、死者行方不明 10万5千余
 石見銀山 経営不振で鉱山は休山となる |
| 1924 大正13年 |
県下で大旱魃(県大年表)、四国災害アーカイブス |
| 1925 大正14年 |
富山村で小作争議が起きる。小作料40〜42%減額となる。ラジオ放送開始(wiki) |
| 1926 大正15年 |
郡役所制廃止(wiki)→安濃郡佐比賣村大字多根と大字野城に
山口に電灯がつく |

今から 年前~
 西暦 和暦 |
で き ご と |
| 1926 昭和 元年 |
12月25日改元。12月25日から昭和となる |
| 1927 昭和2年 |
佐比賣村に消防隊が組織される→昭和39年大田市多根分団となる(ふるさと百年) |
| 1928 昭和3年 |
第1回普通選挙実施(2月)、ラジオ体操始まる(11月) |
| 1929 昭和4年 |
不況いよいよ深刻となる。米価3分の1、豊作貧乏、借金不払い続出
 夏より地震が頻発、三瓶の鳴動が続き人心動揺小屋掛けして万一に備えた人もあり1ヶ月余続いた(旧山口村郷土の歴史)
 10月24日、ニューヨーク証券取引所で株価が大暴落。世界恐慌(wiki)の始まり |
| 昭和初期 | 多根・山口にトラックが通うようになり荷馬車は激減する。乗合自動車も通う(ふるさと百年)
山口~小田間定期自動車が佐津目地内で転落40m、死傷2名(小学校の百ニ十年) |
| 1930 昭和5年 |
農山漁村の窮乏が深刻になる。失業者全国で30万人
 12月20日、県中部で地震、M6.1、震源は三次市、地震調査研究推進本部 |
| 1931 昭和6年 |
|
| 1932 昭和7年 |
|
| 1933 昭和8年 |
米穀統制令実施される。この年は豊作
12月、山口村診療所開設(樋野自愛医師) |
| 1934 昭和9年 |
4月、山口小学校付近の田出山山林大火災、数十町歩焼失(小学校の百ニ十年)
電話が開通する(山口局)10戸加入が開局の条件(10戸希望者が集まる) |
| 1935 昭和10年 |
9月、省営バス大田線。石見大田〜赤名間を開業する
 10月、県立三瓶農民道場が開設→満州開拓団員の方が訓練を受ける、その後 経営伝習農場となる→昭和25年に北三瓶中学校、農場の一部を借りて開校する |
| 1936 昭和11年 |
国号を大日本帝国に統一(4月)
波根西の珪化木が天然記念物に指定される
 大山地区は「大山国立公園」として指定される、三瓶山等の地域編入は昭和38年 |
| 1937 昭和12年 |
石東農学校が仁摩町に開校する(4月)
日中戦争(wiki)始まる(7月)
 多根報徳会館倶楽部→田向林道の木材(石田山)を貰受け公会堂建立(ふるさと百年)
 三瓶山が島根県の県立公園に指定される |
| 1933 昭和13年 |
・国家総動員法公布(wiki)(3月)、代替燃料で木炭自動車が登場する。ガソリン切符制 |
| 1939 昭和14年 |
三瓶高原でグライダー滑空訓練行われる
この年は降雨少なく県下で大旱魃(~9月)
 第二次世界大戦(wiki)が欧州で勃発する(9月) |
| 1914 昭和15年 |
紀元2600年記念式が全国的に行われる。松江測候所が開設される |
| 1941 昭和16年 |
米穀配給通帳制(4月)、ぜいたく品禁止令(7月)、パーマ髪型禁止、砂糖一人半斤
 12月、太平洋戦争(wiki)起こる、全校児童胸に氏名札をつける |
| 1942 昭和17年 |
・寺院の梵鐘供出が始まりお寺の鐘の音が消える、家庭から金属供出(鍋、釜、火鉢等)、衣料切符制度(7月) |
| 1943 昭和18年 |
9月10日、鳥取地震(wiki)、M7.2、死者1,083人(半年前の3月4日にもM6.2)
 9月19~20日、台風23号による大災害。死者400余名、家屋流失損壊約6000戸、降水量341ミリ、多根、山口の道路、田畑、家屋は大被害を被る。三瓶農民道場(開拓青年隊)百数十人の応援を得て災害応急復旧が行なわれる(旧山口村郷土の歴史) |
| 1944 昭和19年 |
スイカやメロンなどの不急作物作付け禁止(1月)、旅行証明書発給(4月旅行制限)、砂糖配給停止(8月)、米軍機島根県東部に飛来(8月)、座布団の綿を回収(11月) |
| 1945 昭和20年 |
4月30日、山口村藤木で山林火災が発生し数百町歩を焼く大火事となる(旧山口村郷土の歴史)
 8月6日、広島へ原子爆弾投下(wiki)
8月9日、長崎へ原子爆弾投下(wiki) |

今から 年前~
 西暦 和暦 |
で き ご と |
| 1945 昭和20年 |
8月15日正午、戦争終結の詔書を放送(玉音放送:Wiki)太平洋戦争戦没者は310万人 |
| 1946 昭和21年 |
2月16日、新円切り替え(wiki)、預金封鎖(wiki)が行なわれる。インフレ続く
 3月、三瓶山麓に開拓団の入植が始まる。三瓶開拓酪農農業組合が発足(昭和23年)
 12月21日、昭和南海地震、M8.0、松江浜田で震度4、地震調査研究推進本部 |
| 1947 昭和22年 |
 5月3日、日本国憲法(公布は21年11月3日:ぶん蔵)が施行される
 ・日本の総人口は、7,800万人(厚生労働省) |
| 1948 昭和23年 |
9月1日、簸川郡山口村の一部が窪田村(wiki)に編入される(中佐津目、下佐津目、上橋波、下橋波、吉野、高津屋)→新山口村は戸数211戸、人口1039人(旧山口村郷土の歴史) |
| 1949 昭和24年 |
成人の日が定まる(1月15日)、満年齢を用いる法律公布(5月)
対面交通実施(11月) |
| 1950 昭和25年 |
 8月22日、三瓶山付近で地震、M5.2、(地震調査研究推進本部) |
| 1951 昭和26年 |
上多根の経営伝習農場を廃止、農業経営研修所が開所される(農業試験場内)
  11月、国立大田療養所が発足。現在の大田市立病院
 ・女三瓶山に無線中継所(中国管区警察局)ができる その後次々と中継局ができる |
| 1952 昭和27年 |
7月19日、第15回オリンピック・ヘルシンキで開催(wiki)、日本は戦後初参加(75人) |
| 1953 昭和28年 |
・通貨の円未満は切捨てる(銭の単位は無くなる12月) |
今から 年前~
 1954 昭和29年 |
1月1日、大田市制施行される。大田町、久手町、長久村、鳥井村、波根東村、川合村、久利村、静間村で発足する
4月1日、安濃郡佐比売村、簸川郡山口村が大田市に編入。大田市三瓶町と山口町となる |
| 1955 昭和30年 |
 日本の高度成長の始まりで神武景気(wiki)となる(29年12月~32年6月) |
| 1956 昭和31年 |
大田市森林組合設立(4月)、大田市立図書館ができる(和田哲夫氏の寄付による) |
| 1957 昭和32年 |
郷土の力士「三瓶山」初土俵(S32~43年)、1万円札発行(12月)、なべ底不況始まる |
| 1958 昭和33年 |
4月、多根小学校と山口小学校は統合、大田市立北三瓶小学校が開校する
12月、壱万円紙幣(wiki)が発行される(日本銀行)、昭和33年度の国の一般会計予算:1兆3316憶円 |
| 1959 昭和34年 |
 北三瓶体育協会が発足する(山口町と多根野城の区域)
 多根と山口で有線放送が開始。全家庭で通話ができる(各農協に本部)→41年に統合
 この年は、なべ底不況から一転して岩戸景気(wiki)(33年7月~36年12月)となる |
| 1960 昭和35年 |
10月、三瓶温泉に国民宿舎さんべ荘が開業する
 10月、第1回中国連合畜産共進会記念碑建立(中国和牛協会) |
| 1961 昭和36年 |
3月、稚児橋は稚児滝谷越えの鉄筋コンクリート橋竣工難所解決に稚児行列で祝う
11月、三瓶山東の原と大平山を結ぶリフトが完成 スキー、登山に利用される |
| 1962 昭和37年 |
 NHK大田テレビ中継所(11月)、オリンピック景気始(wiki)まる(37年11月~39年10月)
|
| 1963 昭和38年 |
1月、38年豪雪(約100年ぶりの豪雪) 三瓶山麓で積雪4m。宍道湖が全面凍結する
 4月10日、隠岐島、島根半島、三瓶山、蒜山地域が編入し、大山隠岐国立公園となる |

今から 年前~
 1964 昭和39年 |
6月16日、新潟地震(wiki)、死者26人、家屋全壊1960棟、隠岐諸島などに津波被害
 7月18日、山陰北陸豪雨(気象庁),日降水量200mmを超える。 死者:出雲43名、大田10名
 ・北三瓶青年団の発足(多根青年団と山口青年団が合併する)
 10月10~24日、第18回オリンピック競技大会(1964/東京)開催 日本オリンピック委員会
     10月16日、中国は初の核実験(wiki)行なう。新疆ウイグル自治区ロプノール湖 |
| 1965 昭和40年 |
1月、北九州から三瓶山へスキー列車「白銀号」が運転される
 6月22日、日韓基本条約が締結される(wiki)
 7月22~23日、石見地方で集中豪雨。死者11人被害総額123億円、江川橋梁が流失 |
| 1966 昭和41年 |
日本の総人口が一億人を突破する(厚生労働省)
  5月、新国道9号線は島根県内を全線開通する(開通式:大田高校体育館)
 7月、大田市内の有線放送は全市統合1本化。→平成22年終了→石見銀山テレビへ |
| 1967 昭和42年 |
三瓶山自然林が国の天然記念物に指定される。いざなぎ景気(40年11月~45年7月) |
| 1968 昭和43年 |
1月、三瓶山、全日本スキー連盟指導員研修会に高松宮殿下御臨席(県大年表)
2月、県下で豪雪。奥出雲、三瓶周辺などで被害(県大年表)
6月、姫逃池のカキツバタ群落 と 本宮神社の大杉が、県の天然記念物に指定される |
| 1969 昭和44年 |
7月、三瓶山アイリスライン(三瓶山高原有料道路)開通。第二高原道路開通(45年)⇒無料化は昭和62年
 8月6~7日、第11回国立公園大会が三瓶山で開催され常陸宮同妃殿下御臨席
 8月、「ふるさと百年」発刊される。著者:大迫好市、発行者:多根老人クラブみかど会
 11月、三瓶山自然林 が国の天然記念物として指定される |
| 1970 昭和45年 |
3月14日、大阪万博EXPO70 開催(日本万国博覧会記念機構) 来場者数 6421万人
  8月、指書きの名号石の引越(山口消防団の奉仕活動)松は平成5年に植替え三代目
 12月5日、石見大田駅の新駅舎完工式、大田市駅に改称は46年2月5日 |
| 1971 昭和46年 |
2月3~4日、立春豪雪災害 被害総額9億6,000万円
 4月18日、第22回全国植樹祭(wiki)が三瓶山で開催される(天皇・皇后陛下ご臨席)
 12月、ニクソン・ショック(wiki)を受けて、1ドル:308円となる |
| 1972 昭和47年 |
3月、山陽道新幹線、新大阪−岡山間開業、乗り継ぎ:やくも号(岡山−益田)
 7月9~15日、47年豪雨、80年ぶりの大水害、川本町江川水位14m、浸水家屋1497戸 |
| 1973 昭和48年 |
4月、円は変動相場制(wiki)に移行する
6月〜8月、大干ばつ大正13年以来 降水量は平年の約30%、梅雨期の雨量112mm
 10月6日、第四次中東戦争勃発。第1次オイルショック(wiki)、トイレットペーバー騒動 |
| 1974 昭和49年 |
3月、文化の館(資料館)「美山館」が開館。土蔵の提供で(能美正義氏)展示が始まる |

今から 年前~
 1975 昭和50年 |
7月13~14日、大田地方集中豪雨。死者9名、浸水3102戸、総雨量350ミリ、激甚災害指定 |
| 1976 昭和51年 |
8月、「石見銀山資料館」が代官所跡地に開館する(1日)(石見銀山資料館HP)
 11月、「国立三瓶青年の家」開所、2006年「国立三瓶青少年交流の家」に改称 |
| 1977 昭和52年 |
3月、三瓶山東の原スキー場へのスキー客が初めて10万人を突破する
 5月2日、三瓶山付近で地震、M5.3、建物被害約300戸、気象庁、地震調査研究推進本部 |
| 1978 昭和53年 |
1月2〜3日、低気圧による暴風雪。三瓶、山口、佐田、川合で冠雪被害
 6月4日、三瓶山付近で地震 M6.1、被害5億円、墓石が倒れる地震調査研究推進本部
 8月12日、日中平和友好条約が締結される(wiki) |
| 1979 昭和54年 |
 |
| 1980 昭和55年 |
7〜8月、冷夏 戦後最大の農作物被害となる(8月にコタツを出す程の冷夏)
この冷夏の影響は農業だけでなく、製造業、サービス業など広範囲におよぶ。繊維、食品、レジャー用品に冷夏倒産が集中した(気象庁)  |
| 1981 昭和56年 |
多根神楽は市の指定無形民俗文化財に指定(2月18日)
第1回三瓶山山開き(5/17)
 島根県立農業大学校開校(波根)。大田市民の祭り「天領さん」始まる(8月) |
| 1982 昭和57年 |
岡山~出雲市間が電化される(特急やくも号)
・多根佐比売山神社棟札(室町時代)大田市の有形文化財として指定(54年4月発見) |
| 1983 昭和58年 |
 小豆原で埋没林の一部が土地改良事業中に掘り出される縄文時代の埋没林発見
 7月20~23日、県西部で豪雨災害が発生する、死者 112名、日降水量331.5mm(23日) |
| 1984 昭和59年 |
84~85年、荒神谷遺跡(同博物館)発掘調査、銅剣358本、銅鐸6個、銅矛16本出土
 5月12日、世界初の衛星テレビ放送(NHK)開始。離島・山間部の難視聴地域が解消 |
| 1985 昭和60年 |
「日ノ平たたら跡」が発見される(佐津目3月)。三瓶ダム基本協定調印される(7月)
 8月15日、戦没者遺芳録(附従軍者名簿)山口町大正会編が発刊、36柱・115名従軍 |
| 1986 昭和61年 |
7月21日、三瓶周辺集中豪雨(被害37億円)、海岸に大量の廃油漂着、被害9000万円
 お祝や来客時の郷土料理「箱寿司」、ふるさとおにぎり百選(wiki)に選定される
 12月、バブル景気(wiki)始まる、平成3年2月迄、日経平均株価38,915円(1989年12月) |
| 1987 昭和62年 |
3月、三瓶山アイリスライン(高原道路)は無料開放される
 4月、日本国鉄道は民営化される。山陰線は西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)となる |
| 1988 昭和63年 |
4月4〜5日、三瓶山林野火災(島根県)。西の原と北の原から同時に出火し94haを焼失する。多根消防団は、1日に2回も男三瓶山頂に登り消火活動を行う
7月、俳人稲畑汀子さんの句碑が北の原に建立される |

今から 年前~
 西暦 和暦 |
で き ご と |
| 1989 平成元年 |
1月8日改元。1月8日から平成となる
 |
| 1990 平成2年 |

今から 年前~
 1991 平成3年 |
2月、1986年12月~1991年2月の間(51ヶ月)続いたバブル景気(wiki)が,崩壊(wiki)する
 3月、「仁摩サンドミュージアム」砂博物館が開館する(世界最大の砂時計)
 7月27日、「多根神楽伝承館」が佐比売山神社の隣にできる
 9月27日21時頃、台風19号(りんご台風)が大田市付近の海上を通過 「名号の松」は根こそぎ倒れる
 10月6日、第15回全国育樹祭(wiki)が三瓶山で開催される(皇太子殿下ご臨席)
 10月19日、「県立三瓶自然館サヒメル」が三瓶山北の原に開館する |
| 1992 平成4年 |
・バブル景気が崩壊(wiki)して景気後退期に入り深刻な経済不況となる
5月、第1回東三瓶ポピー祭が志津見で開催。東三瓶フラワーバレー |
| 1993 平成5年 |
3月、指書きの名号 の「名号の松」三代目を植える
 7月、石見空港が開港(益田市)
・長梅雨と冷夏で全国的な米の不作となる。全国の作況指数は「著しい不良の74」。外米騒動 |
| 1994 平成6年 |
5月、北三瓶小学校児童数:32人、中学校生徒数:34人、合計:66人 |

今から 年前~
 1995 平成7年 |
1月17日、阪神淡路大震災(wiki)、M7.3、死者6437人、全壊住宅104,906棟、松江で震度3
 |
| 1996 平成8年 |
2月、北三瓶小学校改築記念 「小学校の120年」発刊。佐津目分校は本校に統合
 4月、三瓶ダム(さひめ湖)が完成する。堤高54.5m、堤頂長140m、総貯水容量712万
 5月、三瓶山西の原で和牛の放牧が24年ぶりに復活(里地ネットワークさんのHP)
 6月1日、東京北三瓶会が発足する(26名:恵比寿ガーデン) |
| 1997 平成9年 |
6月25日、島根・山口県境で地震(M6.1)。益田で震度5、松江で震度4 |
| 1998 平成10年 |
4月「山口町郷土資料館」が開館、月2回一般公開始まる(山口町ことぶき会、自治会)、平成30年の地震で被害・廃館となる
 |
| 1999 平成11年 |
4月、あすてらす 島根県立男女共同参画センター 大田市駅前に開館する |
| 2000 平成12年 |
10月6日、鳥取県西部地震(wiki)、M7.3、死者0人、約480億円、大田で震度5弱
 10月29日、北三瓶中学校開校50周記念式典挙行される(昭和22年開校) |
| 2001 平成13年 |
3月24日、芸予地震(wiki)、M6.7、被害総額約193億円、県内負傷者3人、大田で震度4 |
| 2002 平成14年 |
4月18日、県立三瓶自然館「サヒメル」で、埋没林スギが公開される
 10月、稚児大橋が谷越えで架橋され難所が解決される(埋没林を模した親柱)
 10月23日、三瓶山東麓周辺の地震活動 M4.3、京都大学防災研究所、地震調査研究推進本部 |

今から 年前~
 2003 平成15年 |
2002~2003年冬季、姫逃池の水位回復を目的とした自然再生事業が行なわれる
 4月2日、三瓶山東麓周辺の地震活動 M4.3、京都大学防災研究所、地震調査研究推進本部
  5月29日、佐田町横見で埋没林が発見される(佐田町教育委員会発表) |
| 2004 平成16年 |
2月、三瓶小豆原埋没林は「国指定天然記念物」に指定される
 4月、大田市山村留学センター三瓶こだま学園が竣工(山口町) 受入れが始まる |
| 2005 平成17年 |
3月20日、福岡県北西沖地震(wiki)M7.0、最大震度6弱、大田で震度4
 3月、「小豆原大橋」が架橋され、三瓶小豆原埋没林公園に大型車が通行可能となる
 10月1日、温泉津町と仁摩町が大田市に合併。新大田市発足。人口 40,703人 |
| 2006 平成18年 |
 10月1日、島根県下で地上デジタル放送(wiki)が開始される、島根県
|
| 2007 平成19年 |
6月、姫逃池のカキツバタ保全作業(草刈)りが行なわれる(関係団体、ボランテア)、以降毎年続く
 7月、石見銀山遺跡とその文化的景観は、ユネスコの世界遺産に登録される
 11月、「定めの松」の樹精回復作業実施(市民ボランテア) 日本樹木医会 島根県支部
 11月11日、大阪北三瓶会が発足する(36名、大阪ツイン21) |

今から 年前~
 2008 平成20年 |
4月、三瓶小豆原埋没林公園の入場者が30万人になる
 9月15日、リーマン・ブラザーズが破綻(wiki)し世界的金融危機の引き金となる
・破綻ショックで超円高(1ドル:87円)となり大不況となる
 10月20日、石見銀山世界遺産センターが全面会館する(石見銀山ことはじめⅠ)
 11月22日、大田市立北三瓶小学校 開校50周年記念行事が盛大に挙行される |
| 2009 平成21年 |
1月9~15日、県央(特に三瓶山周辺)の山林で大雪による冠雪被害が発生する
 5月10日、三瓶小豆原埋没林は日本の地質100選に選定される
 7月、「旧山口村郷土の歴史」石橋悦雄著 が発刊される ぎんざんテレビ開局する |
| 2010 平成22年 |
7〜9月、猛暑:30年に一度の異常気象。大田も9月5日まで続く(wiki)、7日の台風で涼しくなる
 10月、国勢調査人口、島根県717,397人、高齢化率29.1%(全国2位)大田市38,069人 |

 2011 平成23年 |
3月11日、東日本大震災(wiki)M9.0、死者・行方不明者18,452人、全壊住宅121,896棟
 3月17日、超円高・戦後最高値(wiki) 1ドル:76円25銭
 5月15日、多根神楽伝承館創立20周年記念神楽大会が挙行される
 6月4日1時57分、三瓶山南東(北緯35.1,東経132.7)で地震(地理院地図) M5.2,深さ11Km,震度4〜3、地震調査研究推進本部 |
| 2012 平成24年 |
3月3日、三瓶山東の原で雪景花火大会開催。5000人以上の観客が集る
 5月12~、三瓶小豆原埋没林で発掘した埋設木の保存状態確認調査と一般公開
 5月、北三瓶よろず会が発足する(野城、多根、山口地域の連携を強くする) |
| 2013 平成25年 |
5月10日~、1ドル100円台となる(2009年4月以来の円安ドル高)
6月15日~、多根公民館で「さんべ学講座(4回)」開講。おおだWebミュージアム
 7月30日、三瓶ダム上流で集中豪雨、総雨量が190㎜(時間100㎜の記録的な雨量)、wiki |
| 2014 平成26年 |
3月14日、伊予灘地震(日本気象協会)M6.2、最大震度5強、大田で震度4
  7月、2日発~3日着
 10月、農薬・化学肥料不使用米「三瓶甘露米」が発売される。百姓天国(facebook)
 11月2日、山口八幡宮例大祭、花車奉納、まちカフェ、青竹花瓶作り、そらショップ |
| 2015 平成27年 |
1月、田舎暮らしの本・宝島社2月号 住みたい田舎ランキングで大田市が全国第一位
 8月28~31日、多根神楽(団長以下14名)がベトナム・ホイアン市(世界遺産の町)wikiの「ホイアンー日本祭」で文化交流(大田市:世界遺産の町)をはたす |
| 2016 平成28年 |
4月14日21時26分~16日1時25分熊本地震(wiki)M7.3・震度7、大田市で震度4
 10月21日14時7分、鳥取県中部地震(wiki)、M6.6、震度6弱、大田で震度4
 11月26日、佐比賣山神社で7年に一度の大元神楽が奉納される |
| 2017 平成29年 |
6月4日、東京北三瓶会第20回記念開催。北三瓶からご来賓12名,こだま学園5名、計41名
 7月、石見銀山世界遺産登録10周年記念行事が開催される。提灯行列でお祝い
 11月、平成30年北三瓶ふるさとカレンダー発刊される(北三瓶よろず会) |
| 2018 平成30年 |
4月9日1時32分、島根県西部の地震 深さ12km,M6.1,大田町で震度5強、詳しくは三瓶山は火山、山口町郷土館は当地震で損壊(敷地も崩れる)のため廃館となる(北三瓶地区の食や民具に掲載)
|
2019 平成31年 |
3月26日、松江地方気象台は松江市でサクラが開花したと発表。暖冬のため平年より5日早い開花となる。今冬は雪も極めて少なかった
4月30日、平成天皇陛下退位される |

今から 年前~
 西暦 和暦 |
で き ご と |
2019 令和元年 |
5月1日、新天皇陛下が即位され「令和」となる 6月4日、北三瓶小学校はオキナグサ保全活動対して地域環境保全功労者表彰を受賞する
 6月、石見神楽は日本遺産に認定される.日本遺産ポータルサイト
 6月26日、中国地方の梅雨入りは26日(1951年以降で最も遅い)
 11月、令和2年北三瓶ふるさとカレンダー発刊
|
| 2020 令和2年 |
1月15日、日本で新型コロナの最初の感染者が確認される
 3月20日、新型コロナで春の彼岸市(大田)は中止
 4月 7日、〃緊急事態宣言(7都道府県)、4月16日全国に拡大
 5月25日、〃解除、感染者16,581人(全国)、24人(島根県)
死者:830人、0人(島根県)   10月31日、神楽奉納画像がオンライン配信で行われる:多根神楽団
 12月31日、コロナ感染者234,395人(全国)、207人(島根県)
死者:3,460人(全国)、0人(島根県) |
| 2021 令和3年 |
3月14日、松江で桜が開花する(過去最早:例年は3月31日)
5月 8日~2023年4月 多根神楽団定期講演開催
6月30日、コロナ感染者:800,517人(全国)、553人(島根県)
死者:14,797人(全国)、1人(島根県) 12月31日、コロナ感染者1,734,190人(全国)、1,756人(島根県)
死者:18,404人(全国)、5人(島根県) |
| 2022 令和4年 |
1月29日、道の駅ごいせ仁摩は仁摩・石見銀山IC付近にグランドオープンする
2月14日、子ご美の里は農林水産省の「つなぐ棚田遺産~ふるさと誇りを未来へ~」に選定される
6月30日、コロナ感染者9,332,216人(全国)、19,599人(島根県)
死者31,281人(全国)、16人(島根県) 7月1日、三瓶ダム、渇水により貯水率:36.5% とのこと、その後も貯水率が下がるも、19日以降の豪雨により回復する
7月、大田市文化財保存活用地域計画が発表される
8月12日、林春生さん功績をたたえる看板などが設置される、国民的アニメ「サザエさん」の主題歌などを手がけた大田市出身の作詞家
12月31日、コロナ感染者29,212,535人(全国)、137,840人(島根県) 死者57,266人(全国)、191人(島根県) |
| 2023 令和5年 |
3月20日、三瓶山西の原で火入れが行われる
3月21日、春の彼岸市(大田)が開催される(雨天)
5月8日、コロナ感染者33,830,420人(全国)、169,917人(島根県) 死者74,725人(全国)、304人(島根県) |
| 2024 令和6年 |
3月9日、山陰道の仁摩~静間~大田中央の道路開通する
11月27日~、三瓶山西の原「定めの松」が落葉する.上部を切り落とし防腐処理される.樹齢推定400年
  |

今から 年前~
 西暦 和暦 |
で き ご と |
| 2025 令和7年 |
3月25日、三瓶山西の原で火入れが行われる
4月13日、大阪・関西万博開催される
いのち輝く未来のデザイン |

参考資料や文献
 ・訂正出雲風土記 梅之舎大人 文化3年 国会図書館
・石見八重葎 石田初右衛門春律 文化14年
・島根県安濃郡誌 島根県安濃郡役所 大正4年7月7日 国会図書館
・出雲方言 文友社 後藤蔵四郎著 大正5年4月20日 国会図書館
・佐比賣村村史 安濃郡役所 大正7年7月
・三瓶山物語 石村禎久著 昭和37年10月15日
・三瓶山見たまま聞いたまま 今田俊英、今田見信著 昭和38年8月1日
・新修島根県史 島根県 昭和42年3月30日
・三瓶山の史話 石村禎久著 昭和42年7月1日
・ふるさと百年 多根老人クラブみかど会 大迫好市著 昭和44年8月10日発行
・さんべ 国立三瓶青年の家 昭和56年2月1日
・開校三十五年記念 北三瓶中学校記
北三瓶中学校開校三十五年記念事業実行委員会 昭和58年3月1日 ・三瓶山 歴史と伝説 石村禎久著 昭和59年8月
・大田市の文化財 大田市教育委員会 昭和61年3月発行
・石見銀山 戦国の争乱・鉱山社会・天領 石村禎久著 昭和63年6月20日発行
・北三瓶小学校改築記念小学校の百二十年
北三瓶小中学校改築推進協議会 平成8年2月25日発行 ・郷土の歴史資料集(第7版) 大田市教育委員会 平成10年3月1日発行
・島根県歴史大年表 郷土出版社 平成13年3月16日
・ふるさと読本 西部ブロック推進協議会 平成17年3月
・出雲国風土記 沖森卓也・佐藤信・矢島泉編著 山川出版 平成17年11月30日第1版
・群盲がなでた島根・三瓶火山 40余年でここまでわかった 松井整司著 平成20年8月
・旧山口村郷土の歴史 石橋悦雄著 平成21年7月
・渚の砂に魅せられた男の 鳴り砂放浪記 松井整司著 平成23年1月
・石見銀山ことはじめⅠ 大田市教育委員会 平成30年3月30日
・火山からの贈り物 三瓶山十二勝 尾添英二著 平成31年3月1日
 |

| Home | TopPage |
 泉
泉