
| あ | い | う | え | お |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| あかはぜ(魚) | ヒメジ(魚) 海の金魚 |
||||||
ヒメジ・wiki |
|||||||
| あくた | |||||||
| あご(魚) | あご野焼(島根観光ナビ) |
||||||
|
|||||||
| あさはん あさめし(食) |
朝 飯 朝の食事 |
||||||
間食(はしまん・あいまぐち)  |
|||||||
| あじうり 味瓜 |
マクワウリ、メロンの亜種で甘い瓜(wiki) | ||||||
| あしつぎ (民具) |
|||||||
| あじがき 味柿 |
*柿には甘柿と |
||||||
| あしなか | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| あぶらむし(虫) | 稲につく虫(ウンカ等)、ゴキブリ | ||||||
| あまさぎ(魚) | わかさぎ 宍道湖 |
||||||
| あまだい(魚) | アカアマダイ、Wiki | ||||||
お祝い事に欠かせない縁起の良いお魚 「一日漁」の甘鯛一夜干(岡富商店さん)  |
|||||||
| あまんぼし あまぼし ちーりんぼ つるんぼす |
つるし柿、干し柿、冬の保存食 # | ||||||
| あもち あんもち(食) |
餡入り餅 | ||||||
| あ | い | う | え | お |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
|
|||||||
| いたしい いたしげな |
なやましい、 |
||||||
| いついき | 常に、よどみなく | ||||||
| 三瓶の石清水はいついき湧き出て | |||||||
| いで、えで いでさらい |
井出(水田の用水路や堰)の掃除 田畑周辺の草刈り→ほとり刈り |
||||||
|
|||||||
| いなはで はでば |
稲ハデ、ハデ場 なだら、ヨズクハデ |
||||||
| あ | い | う | え | お |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 |
| うちねつ ~でだるーて |
何となく熱があるような(計ると平熱) |
| うべる 風呂に水を~ |
加える、薄める 風呂に水を入れてぬるくする |
| うむす かたらだんごをうむす |
蒸す かたら(さるとびいばら)の葉でくるんだ餅(だんご)蒸す |
| うわぱり うわっばり |
上に |
| あ | い | う | え | お |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 |
| えがま(民具) | まさかり、ちょうの しまねの民具 |
| えしこ、いしこ ええしこ えすこだがね |
良い具合、良い状況、良い状態 * わりしこ→悪い具合 |
| えっと、いっと えっと食べた |
たくさん、大食い 食べて満足した |
| えてかれい(魚) | ソウハチ、Wiki |
えてかれい一夜干し(スカイホテルさん) |
|
| えのすす | イノシシ(猪) |
| えのすすが |
|
| えんこう | カッパ、河童 |
| えんこうばな | |
| あ | い | う | え | お |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| おおあし 「たげた」の別名 |
|||||||
| おきいわし おききす |
ニギス(魚) | ||||||
沖いわしの干物 島根県、岡富商店さん |
|||||||
|
|||||||
| おしこみ おすこみ |
|||||||
| おどろ | くど(かまど)で使う小枝(束) おどろ(Weblio) |
||||||
| おみける おむける |
蒸し暑くなる、蒸し暑い ぼやけるとも→ |
||||||
|
|||||||
| おんぼらと | ほのぼのと、おだやかな、ぼんやり、温かい | ||||||
| か | き | く | け | こ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| かがち かがつ |
すり鉢 * | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| からすがい、たちがい | ドブ貝 | ||||||
| かやかす 大豆を「かやか」して |
水に浸す 大豆を水に浸して豆腐に |
||||||
| かやくめし(食) かやくごはん(食) |
|||||||
| からんま(食) からむま(食) |
思い出のからんま(田作り) 松江塩干魚さん |
||||||
| かんころ | 大根やサツマイモ等の切干し | ||||||
| かんらん(甘藍) | キャベツ(wiki) | ||||||
| か | き | く | け | こ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 |
| きだ | 鰓(魚のえら) |
国引き神話 |
|
| きなや(木納屋) | 薪、おどろ、炭(木炭)等の収納家屋 まや→牛馬を飼う家屋 |
| きねり しぶがき |
渋柿 |
| きびしょ (きびす) |
|
| きらず(食) | おから(豆乳を絞るときの搾りかす)、卯の花 |
| きんかいも (馬鈴薯) |
ジャガイモ、馬鈴薯 ジャガイモ(wiki) |
| か | き | く | け | こ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| くいさし のみさし |
食べ残し、食べかけ 飲み残し |
||||||
| くう(食) くうだわね くわっしゃい くっちゃらかい |
食べる 食べてね 食べてくださいね 食べようではないか |
||||||
| ※ 出雲では食べることを「くう」といいます | |||||||
| くぎる 焼け焦げ |
|||||||
| くずんば くずかずら |
クズ(wiki) |
||||||
 国引き神話  |
|||||||
| くちなわ | へび(蛇) | ||||||
|
・蝮は、出雲:まもす、石見:まむし・はみ とも云います |
|||||||
|
|||||||
| くべる | 小枝→おどろ |
||||||
| くよし くぐし |
田畑の草などの野焼き ぶと、ほび等の虫よけ |
||||||
| くわいちご(実) | 桑の実(5~6月) | ||||||
・食料難時に子供たちの空腹を満たした ポリフェノールを多く含む(wiki) |
|||||||
| か | き | く | け | こ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 |
| けやかす きやかす |
火を消す、電気を消す、書いたものを消す |
| げんがいい げんがわるい |
(縁起が悪い) |
| げんなり トマトの苗がげんなり |
しょげる、しおれる、元気がない |
| けんびき けんべき |
疲れからくる肩こりや頭痛 |
| か | き | く | け | こ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| こうせん(食) | はったい粉(wiki) 夏のはしまん |
||||||
・オオムギやハダカムギを炒り石臼などで挽いた粉.栄養満点で空腹を満たした
・ビタミンの取得、脚気予防に貢献した |
|||||||
|
|||||||
| こぉかちゃ(石見) かーかちゃ(出雲) |
カワラケツメイのお茶 こぉか茶(春光園さん) |
||||||
・カワラケツメイを乾燥後に、焙煎した香りの良い野草茶 |
|||||||
| こおりみず (氷水) |
かき氷 かき氷(wiki) |
||||||
| こごみ (山菜) |
クサソテツ(草蘇鉄)の若芽(wiki) 子ご美の里 |
||||||
| こごめ 小米 |
実入りの悪い米、精米時に砕けた米 | ||||||
| こさげる 鍋底をこさげて |
こすって落とす、削って取り除く | ||||||
こざさは粉雪、だんべらはべた雪 玉雪→粉雪→灰雪→綿雪→餅雪→べた雪→水雪 |
|||||||
| こたつ→炭火で暖をとる炬燵 小さくて簡便な炬燵 →ねここたつ 大人数でも暖をとる炬燵→ほんごたつ |
|||||||
| ごづ、ごぜ(魚) | ハゼ、宍道湖や中海で良く釣れる(島根県) * | ||||||
| ごっつお(食) | ご |
||||||
| こっとい | 子牛の雄、子牛→べんこ | ||||||
| さ | し | す | せ | そ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| さいのべ ~すーだわね |
足(脚)を投げ出して座る | ||||||
| さがりいちご (山菜) |
ナガバモミジイチゴ (木々@岸和田さん) |
||||||
| さつまいも りゅーきゅーいも |
薩摩イモ(琉球イモ)→甘藷、 | ||||||
・石見銀山とサツマイモ(石見銀山通信) |
|||||||
| さでかき(民具) | 竹でできた熊手のこと、家の女たちのブログさん | ||||||
| ささかれい(魚) | ササカレイ一夜干し 岡富商店さん |
||||||
|
|||||||
| さやぐ さやぎかぜ →しとりかぜ |
乾く 乾いた風 →湿った風 |
||||||
| さんとう | なます(酢の物) | ||||||
| さ | し | す | せ | そ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| しいたん(食) | 果物(梨など)の芯 | ||||||
| しいら(農) | 実入りの悪い籾(不念) 魚のシイラは「まんさく」 |
||||||
| しおけめし しょけめし そけめし そーけめし |
五目ご飯、炊き込みご飯 | ||||||
| しかけぶり むらさ |
雨が急に降りだす にわか雨 |
||||||
| しごする 魚をしごする |
いじめる、 魚をさばく * |
||||||
|
|||||||
| しじれる しじれた にしじれる |
煮詰まった 焦げる |
||||||
| しぶき(木) しびき(木) すぶき(木) |
ヒサカキ(wiki) 水しぶきではない * |
||||||
|
|||||||
| しろいか(魚) | ケンザキイカ、Wiki | ||||||
「一日漁」の白いか一夜干(スカイホテルさん) |
|||||||
| しょいこ(民具) | 背負い籠(かご) | ||||||
| しんざい しんざえ |
つらら、氷、なんりょ | ||||||
| さ | し | す | せ | そ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| すえる しぇる |
食べ物が (いたむ・腐る) # |
||||||
| すくも(農) | 籾殻、もみがら | ||||||
| すとかまぼこ(食) | スト |
||||||
すとかまぼこ(島根観光ナビ) |
|||||||
| すぼ、わらすぼ | 稲わらで編んだ入れ物 | ||||||
|
|||||||
| すもじ | 箱寿司はこちら |
||||||
| すんどり(石見) てみ(出雲) (民具) |
竹で編んだざる(ちりとり状)、箕(wiki) | ||||||
| さ | し | す | せ | そ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| せつい せつうない |
苦しくない * |
||||||
| せど | 家の |
||||||
| せんち せんつ |
便所、トイレ | ||||||
|
|||||||
| さ | し | す | せ | そ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 |
| そうめんかぼちゃ(素麺南瓜) | キンシウリ(金糸瓜、錦糸瓜)、 キンシウリ(wiki) |
| そえもの | 添え物、おかず |
| そくう | |
| そけくち | 煮しめ、茶口の煮しめ |
| ぞんぞがつく ぞんぞがさばる |
|
おぞげな話しにぞんぞがついてあばかんわ 横断歩道に子供がいて急ブレーキ! ぞんぞがつきましたわ!  |
|
| た | ち | つ | て | と |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| たいたい(幼) | 魚のこと | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| だしこ だしこして だしあいこ |
互いにお金(または物)を出し合うこと 出し合って * |
||||||
| だしまえ だしもん |
割り当て物(お金) 出費 |
||||||
| ただごめ(食) | うるち米 ※無料の米ではありません |
||||||
| だちがい(貝) | からす貝 * カラスガイ(wiki) |
||||||
|
|||||||
| たばこ たばこする |
注. |
||||||
|
|||||||
| たべさし たべくさし |
たべかけ、食べ残し | ||||||
| だんごむし 昆虫 |
ケシキスイ(虫) ユキワリイチゲの虫 北三瓶のユキワリイチゲ |
||||||
| だんべ だんべら だんびら |
べた雪・ぼたん雪 石見では→べたれ |
||||||
玉雪→粉雪→灰雪→綿雪→餅雪→べた雪→水雪 だんべらはすべーけんね!  おつらと運転せんと事故になーよ  |
|||||||
| た | ち | つ | て | と |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| ちゃぐち(食) | 茶菓子、漬物など お茶の口取り |
||||||
| ちゅうはん ひるめし(食) |
昼飯 昼の食事 |
||||||
間食(はしまん・あいまぐち)  |
|||||||
|
|||||||
| た | ち | つ | て | と |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| つげごめ | 返礼する その場で返礼を渡す |
||||||
| つばくら(鳥) つばくろ(鳥) |
燕、ツバメ、ツバメ(wiki) | ||||||
| つぼかきさん | 近年は墓掃除役 |
||||||
|
|||||||
| た | ち | つ | て | と |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
|
|||||||
| ててぽっぽ | |||||||
| てみ(出雲) すんどり(石見) (民具) |
竹で編んだざる(ちりとり状)の箕(wiki) | ||||||
| てっぺんかけたか | ホトトギス(時鳥)の鳴き声(サントリー鳥百科) | ||||||
| てれつくほーせ | よずく(ふくろう)の鳴き声 | ||||||
| てんぷらまんじゅう(食) | 紅白のまんじゅうを天ぷらにした郷土の食品 大田市のHP |
||||||
| た | ち | つ | て | と |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| どうまき | 帯状疱疹(たいじょうほうしん) | ||||||
|
|||||||
| とぎなし とびなし |
お返しなし えーもんもらたにとぎなしで |
||||||
| どまかす どまかしちゃえけんわね |
|||||||
| とやなし とやもない とやもねー とやばら話 |
途方も無い 根も葉もない、いい加減な |
||||||
|
|||||||
| な | に | ぬ | ね | の |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| なかい なかえ |
|||||||
| ながし ながしば |
台所 流し場 |
||||||
| ながまる | 横になる 座る→ねまる |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
| なつまめ (夏豆) |
そら豆、ソラマメ(wiki) | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| なんりょ まんりょ |
つらら しんざいとも云います |
||||||
| な | に | ぬ | ね | の |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 |
(民具) |
牛馬の背にくくり付けて荷物を運ぶ鞍 |
・牛馬の背骨に当たらないように工夫する、しまねの民具
・石見銀山では、銀10貫目入木箱をコモで包み両背に括り付けた(石見銀山ことはじめⅠ) やなしお道(石見銀山から尾道まで) |
|
| にょうば にょうばし にょうばのこ にょうばんこ えーにょばだね |
ご 女の子 女の子 |
| にわかしごと | やっつけ仕事 |
| な | に | ぬ | ね | の |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 |
| ぬーたくりゃ ぬーまくりゃ |
塗り重ねれば、味噌をぬーたくり |
| ぬいはり 雨の日の~ごと |
雨の日の針仕事 |
| ぬくい、のくい ぬくてえけんわ ぬくたらすてえけんわ |
温かい 暑くてかなわない * |
| な | に | ぬ | ね | の |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 |
| ねぎ こねると~がでて |
こねると粘り気が出て |
| ねこぐるま | 運搬用の |
| ねこごたつ (民具) |
こたつには「掘り炬燵」と「置き炬燵」があり、簡便な置き炬燵を「ねここたつ」とも云う ねこ用の炬燵では無い しまねの民具 |
| ねずみいらず | ねずみが入らないように密閉した部屋・倉庫 |
| ねたがえ | 寝違え |
| ねまる ねまらや |
座ろうよ(誘う) * 横になる→ながまる |
| な | に | ぬ | ね | の |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 |
| のーじた のーじした |
満足した(食べて満足した) |
| のっけに のつけに |
いきなり 突然に |
| のどぐろ(魚) | アカムツ |
アカムツ(島根県)、アカムツ(wiki) |
|
| のやき(食) | 竹輪の大きなもの、あごのやき:島根観光ナビ |
| のんのさん(幼) | 仏さん |
| は | ひ | ふ | へ | ほ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| はいごん はいぐん おおはいごん |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| はこぜん | 箱型のお膳 箱の内に食器を入れることができる |
||||||
| はこだん | 引き出しのついた段(上り段や階段) | ||||||
| はしま、 はしまん、 あいまぐち |
間食、軽い間食 夏のはしまんは「こうせん」 |
||||||
 |
|||||||
| はっとじ(虫) ヘコキムシ(幼) |
カメムシ(wiki) | ||||||
| はなぐり | 牛を 三瓶山 牛の放牧 |
||||||
| はなぐりいわ:船を係留する岩 温泉津の鼻ぐり岩(島根県)  |
|||||||
| ばはんもち | |||||||
| ばばひき | 田植作業時に苗を植える位置を示す線引き道具 | ||||||
| はやす ごぼうをはやす |
切る ごぼうをけさがけにする |
||||||
| はんだい | 食卓、食机 | ||||||
|
|||||||
| はんぼ(民具) | 飯櫃、おひつ | ||||||
・春・秋・冬:はんぼ(島根の民具)
・夏:めしそうき |
|||||||
| は | ひ | ふ | へ | ほ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
|
|||||||
| ひもおとし ふもおとし おびなおし |
|||||||
|
|||||||
| は | ひ | ふ | へ | ほ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 |
| ふけだ (ふけ田) |
山裾や谷奥の水田で常に水が湧き出て腰まで沈む深い田。田下駄を履いて作業をした |
|
・水が常に湧き出ているので旱魃には強く少量でも一定の収量があるの田んぼ
・足が沈み込まないように田下駄を履いて作業をした
・近年は農機具が入らない(沈み込む)ので廃田となる |
|
| ぶと (吸血虫) |
ブユ:wiki、噛まれると痒くなる くよし:ブユ等の虫よけ |
| ふまいつぎ (民具) |
|
| ふらもち(出雲) ひらもち(石見) |
※ 餡入りはあもち |
| は | ひ | ふ | へ | ほ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 |
| へかやき へかやき鍋 |
すき焼きの具材に魚を使用した「すきやき」 大田市の食 |
| へこきむし(昆虫) (はっとじ) |
カメムシ(wiki)。 |
| へたばる へたくなる |
座す、すわる、体力や気力が尽きて座りこむ |
| くたぶれたなーへたばってたばこしようやな | |
| べたれ(雪) | べた雪、ぼた雪 出雲では→だんべら |
| 玉雪→粉雪→灰雪→綿雪→餅雪→べた雪→水雪 | |
| べんこ(家畜) | 牛の子 こっとい(牛の雄) 三瓶山 牛の放牧 |
| べんとうがら | 空の弁当箱 |
| は | ひ | ふ | へ | ほ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| ぼうくた ぼーくた |
棒(役に立たない棒) | ||||||
| ほそびき | 細い綱 | ||||||
| ぼてぼてちゃ ぼてぼて茶 |
出雲地方に伝わる庶民の間食 ぼてぼて茶(神々のふるさと山陰) ぼてぼて茶(wiki) |
||||||
|
|||||||
| ほとびらかす | 水に浸して柔らかくする | ||||||
| ほび 吸血虫 |
ブユ(ブヨ、ブト) 農作業→くよし |
||||||
| ぼべ、ぼべ汁 ぼべ飯(食) |
カサガイ類(wiki) | ||||||
ぼべ飯は磯の香りがあふれます |
|||||||
|
|||||||
| ぼやける おむける 今日はおむけてこまーますわ |
蒸し暑い(軽い) 蒸し暑い 今日は蒸し暑くて困りますね |
||||||
| ほろせ ほろせがでた |
|||||||
| ほんごたつ 掘り炬燵 |
炭火で暖をとる堀炬燵 小さな炬燵→ねここたつ |
||||||
| ま | み | む | め | も |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||||||
|
|||||||||||
| まきだんご(石見) かたらだんご(出雲) |
→かたらだんご |
||||||||||
| まくれる さでまくれる まくらかす てんする(幼) |
強く倒れ転ぶ 転がす * |
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| まま(食) | めし、ご飯 | ||||||||||
| まむない(出雲) もむない(石見) |
不味い、美味しくない おいしい→まい、うまい |
||||||||||
| まもす、はみ | |||||||||||
|
・蝮は、出雲:まもす、石見:まむし・はみ とも云います |
|||||||||||
| まや | 厩舎、牛馬を飼う家屋、小屋 きなや→木納屋 |
||||||||||
| まやごえ | 厩肥(wiki)、牛馬飼育中にできる肥料(牛馬の糞や草など)、堆肥(wiki) | ||||||||||
| まんさく(魚) | しいら、シイラ(島根県) ※実入りの悪い籾(不念)→しいら |
||||||||||
| ま | み | む | め | も |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| みいりがすーわ みいりがすた |
筋肉痛になる | ||||||
| みてる | 注.石見では、無くなる、空になる、尽きる 注.出雲では、満てるの意 |
||||||
|
|||||||
| ま | み | む | め | も |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 |
| むすび(食) もすぶ(食) |
|
| むしろばた (民具) |
稲わらで「むしろ」を織る農具 「むしろ」は敷物で必需品 しまねの民具 |
| むらさ しかけぶり |
にわか雨、夕立、じぶり→本格的な雨 |
| ま | み | む | め | も |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| めいめい めいめいで めいめい皿 |
おのおの、個人個人、各自で | ||||||
|
|||||||
| めのは(海藻) | わかめ(若布)を乾燥・板状したもの | ||||||
| 魚の屋さんの「めのは」 | |||||||
| めほいと めぼいと |
目にできる |
||||||
| めんば | めだか(魚) | ||||||
| ま | み | む | め | も |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| もうむない もむない まむない |
まずい →ごっつお |
||||||
| もぐりめし | 五目御飯 酢めし→すもじ |
||||||
| もぐれる もぐれつく もぶれる もぶれつく |
まとわりつく 沢山ひっつく |
||||||
|
|||||||
| ものいり | |||||||
| もむない(石見) まむない(出雲) |
不味い、美味しくない おいしい→まい、うまい |
||||||
| もやい もりあい もりあいこ |
物を共有 共同で作業をする |
||||||
| もりおうてやろうやな! | |||||||
| もろふた | 木製の箱(蓋)、餅などを並べる、麹の発酵 | ||||||
| や | - | ゆ | - | よ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 |
| やいと やいとをすえる |
お お灸を据える |
| やおい、やわい | 柔らかい、 |
| やかんぱち やんぱち |
短気な方(者) |
| やきちゃな! やきちゃなー |
しまった、どうしょう |
| やけご やけごけ |
焦げ |
| やたき ~に欲しくなって |
無性に欲しくなって |
| やらし やらしーわ |
「い」の発音無し |
| やらやっと やっとこさで |
辛うじて、どうにかこうにか、どうやらこうやら |
| や | - | ゆ | - | よ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| ゆうたてて | そうは言っても | ||||||
| ゆうな、ゆうに | ゆっくりと、動きの遅い、おおらかな、豊かな | ||||||
| ゆうはん(食) ゆうめし |
夕飯 夜の食事 |
||||||
間食(はしまん・あいまぐち)  |
|||||||
| ゆきおこし | ひとつ |
||||||
| ゆきずり いきずり |
雪がずり落ちる 落雪 |
||||||
| 「雪ずりがすて戸があかんようになり・・・」 ※ 行きずりとは違います |
|||||||
|
|||||||
| や | - | ゆ | - | よ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
| よーたんぼー よいたんぼう |
酔っぱらい 泥酔者 |
||||||
| よあかし よおき よながよふて |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| よばれる よばれた |
招待されご ご馳走になった ※ 呼ばれるではない |
||||||
| よぼる よばる(出雲) |
液が垂れる、この |
||||||
| よろこび よろこびごと よろこびますわ |
お祝い お祝い事 うれしく思います |
||||||
| ら | り | る | れ | ろ |


| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
|
|||||||
| らしなし らしがない あのさんはらしなしで |
だらしない、 |
||||||
| らとう 螺灯:民具 |
石見銀山の間歩でサザエの殻に油を入れて火を灯す明かり | ||||||
 らとちゃん マスコットキャラクター 螺灯と鉱夫の衣装がモチーフ 世界遺産 石見銀山  Xらとちゃん |
|||||||
| らんきょ (野菜) |
ラッキョ(wiki) | ||||||
|
ヤマラッキョは花の百名山 三瓶山  |
|||||||
|
|||||||
| ら | り | る | れ | ろ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 |
| りーきえも りいきえも |
|
| りーじいっぱい りーじ一杯 |
精一杯 気持ちを込めて |
| ら | り | る | れ | ろ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 |
| るすごと | 鬼のいぬまに・・・ |
| ら | り | る | れ | ろ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 |
| れーがえし へんがえし |
お礼のお返し、 |
| れんぎばち れんぎぼー れんぎ |
擂り鉢の 連木 |
| れんげ さるご |
れんげ草→正しくは「ゲンゲ・wiki」 陶器のさじ |
| ら | り | る | れ | ろ |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 | ||||||
|
|||||||
| ろくすっぽ | |||||||
|
ろくすっぽ仕事せんな! 満足な仕事ができませんね  |
|||||||
| ろくにする | |||||||
| わ | を | ん | 終わりに | |

| 暮らし民具など | 意味や使われ方 |
| わかな | ぶりの幼魚 |
| わきざまし | 湯冷まし、お湯をさましたもの、燗酒の冷めたもの |
| わぐなる わぐねる くちなわがわぐなって |
うずくまる 輪のようになる 蛇がドクロを巻いて |
| わけ ねこわけ |
食べたり喰ったりして少し残したもの |
| わに(魚) | さめ、さめ(島根県) |
わにを しごして くーだわね ぶえん(島根県)だけんね、ごっつおだわ  いなばのしろうさぎ(出雲大社御案内) |
|
| わりき たき火にわりきをくべる |
たき火に薪を入れる |
| わりしこ | 悪い具合、悪い状況、悪い状態 えしこ→良い具合 |

暮らし民具ここまで Top↑
 石見の方言 |
 民具 |
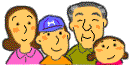 出雲の方言 |
終わりに・・・

山口町郷土館は廃館しました
 |
 |
 廃 館 案 内  平成30年(2018)4月9日の島根県西部地震(M6.1) で石垣が崩れ建物が傾き損壊する被害がありました(震央から4.2km距離)  誠に残念ですが「山口町郷土館」は廃館となりました  詳しくは北三瓶まちづくりセンター にお問い合わせください  電話:0854-86-0478(平日9~16時)  |
|

| Home | TopPage |

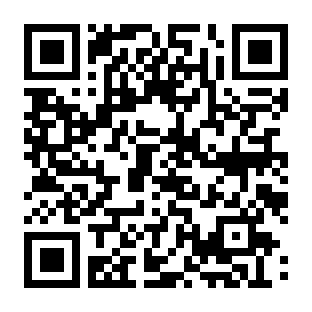
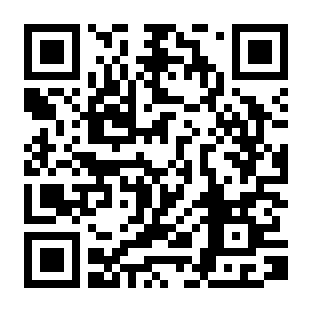



























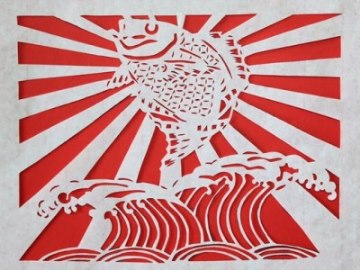






















 YouTube 実りの仕上げ ヨズクハデ作り 1分
YouTube 実りの仕上げ ヨズクハデ作り 1分

