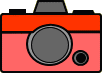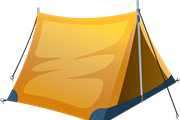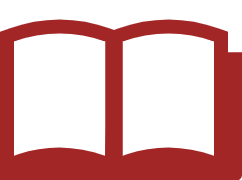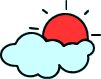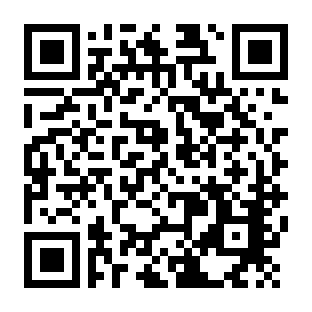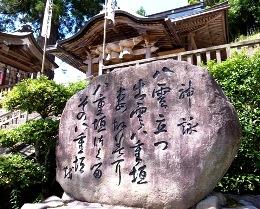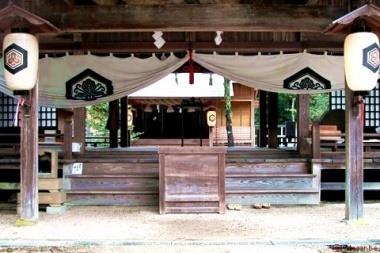八俣遠呂智 ・須佐之男命 神話

八俣遠呂智 ・須佐之男命 神話

|





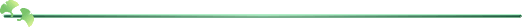
 スサノオのご縁 プロバスケット 島根スサノオマジックはこちら  |
 スサノオのご縁・プロバスケット  島根スサノオマジックはこちら  |
| 和銅3年(710) | |
| 元明天皇が平城京(奈良)に都を移す(遷都) | |
| 和銅4年(712) | |
古事記(Wiki)が太朝臣安萬侶によりによって献上される。日本最古の歴史書・文学書 ・アマテラスオオミカミ:天照大御神
・スサノオノミコト :建速須佐之男命
・アシナヅチ(老夫與):足名椎命、稲田宮主須賀之八耳神
・テナヅチ (老女) :手名椎命
・クシナダヒメ(童女):櫛名田比賣
・ヤマタノオロチ:八俣遠呂智
・クサナギノタチ:草那藝之大刀、天叢雲剣(Wiki)
|
|
| 和銅6年(713) | |
元明天皇の詔により風土記編纂が命ぜられる
 1.諸国の郡郷の名に”好字”をつける、
郡郷山野の名を3文字なら2文字に、 凶音をもつ名は好文字に変えるように →佐比買山は三瓶山に
→五十猛村は磯竹村に
2.郡内の産物の品目
3.土地の肥沃の状態
4.山川原野の名の由来
5.古老(ころう)が伝承している旧聞異事
|
|
| 養老4年(720) | |
| 日本書紀(Wiki)が完成する。奈良時代に成立した日本の歴史書(全30巻) ・アマテラスオオミカミ:天照大神
・スサノオノミコト:素戔男尊、素戔鳴尊
・アシナヅチ(老夫與):脚摩乳
・テナヅチ(老女):手摩乳
・クシナダヒメ(童女):奇稲田姫、稲田媛、
・ヤマタノオロチ:八岐大蛇
・クサナギノツルギ:草薙劒、天叢雲剣(Wiki)
|
|
| 天平5年(733) | |
| 出雲国風土記(島根県)が編纂され、聖武天皇に奏上される ・「
・スサノオノミコトは「須佐能袁命」(最多)や
「須佐能乎命」や「神須佐乃袁命」等 ・クシナダヒメは
「 |
|
| 延暦13年(794) | |
| 桓武天皇が平安京(京都)に都を移す(遷都) | |
須我の宮 須我神社

須我 の宮 須我神社

 ・
 ・「
 ・ |

 ・
 ・
|
|
 と31  これは  「やまとうた」さんのHP  須我神社さんのホームページ  須我神社(youtube:4分)  須我神社の場所:地理院地図  八雲山の場所:地理院地図  |

YouTube 8分  [須我神社参拝ガイド] 須我神社を地元民が解説 [須我神社参拝ガイド] 須我神社を地元民が解説よくわかる須我神社 前編 よくわかる須我神社奥宮 後編 |


船 通 山 ・鳥 上




毎年7月28日






奥出雲町観光協会・地理院地図

  亀石コース登山口 地理院地図 |
  鳥上滝コース登山口 地理院地図 |
  ・
 登山口の温泉・日本三大美肌の湯(wiki) 登山口の温泉・日本三大美肌の湯(wiki) |
天 叢 雲 剣


  ・熱田神宮のご祭神・熱田神宮さん
|

三 角 縁 神 獣 鏡

神 原 神 社 古 墳


    |


神 楽 の 宿


|
・
・
 |
 |

 |
|
・
 ・
|
須 佐 神 社
出雲国風土記「飯 石 郡 」の記述から
 そして  |

| : | ||
| : | ||
| : | おじいさん(老夫與)、アシナヅチ(wiki) | |
| : | おばあさん(老女)、テナヅチ(wiki) | |
|
・
・
・
|
||
 |
|
・
・
・
|


須佐神社さんHP、 地理院地図


出 雲 大 社 大 国 主 命
大国主大神
・別名:大穴牟遅神 ・大穴牟遅 、大 物 主 神 、八千矛神 など多数
・別名:大穴牟遅神 、大己貴命 、大物主神 、八千矛神 、など多数
・正妻 :須勢理毘売命 ・須世理毘売命 ・・・建速須佐之男命 の娘

案内地図:出雲大社(Mapion)、 出雲大社銅鳥井 (地理院地図)

|
YouTube 竹田恒泰に教わる
    YouTube 竹田恒泰に教わる出雲大社
10~14分
    |
全国のスサノオノミコト神社
全国のスサノオノミコト神社

素 盞 雄 神 社
(御祭神:素盞雄大神、東京)




素盞雄神社(東京荒川区):上、下

 |
||
| 須我神社 | 須佐之男命 | 島根県雲南市大東町須賀:JR松江駅 |
| 須佐神社 | 須佐能袁命 | 島根県出雲市佐田町須佐:JR出雲市駅 |
| 八重垣神社 | 素盞嗚尊 | 島根県松江市佐草町:JR松江駅 |
| 熊野大社 | 素戔嗚尊 | 島根県松江市八雲町熊野:JR松江駅 |
| 日御碕神社 | 素盞嗚尊 | 島根県出雲市大社町日御碕:JR出雲市 |
| 彌榮神社 | 須佐之男命 | 島根県鹿足郡津和野町:JR津和野駅 |
| 素鵞神社 | 素戔嗚尊 | 茨城県小美玉市:JR石岡駅 |
| 氷川神社 | 須佐之男命 | さいたま市大宮区高鼻町:JR大宮駅 |
| 素盞雄神社 | 素盞雄大神 | 東京都荒川区南千住:JR南千住駅 |
| 須賀神社 | 須佐之男命 | 東京都新宿区須賀町:JR四ツ谷駅 |
| 津島神社 建速須佐之男命 | 愛知県津島市神明町:名鉄津島駅 | |
| 八坂神社 | 素戔嗚尊 | 京都市東山区祇園町:京阪祇園四条駅 |
| 須賀神社 | 素盞鳴尊 | 和歌山県みなべ町:紀勢線南部駅 |
| 祇園神社(神戸・平野) 素盞嗚尊 | 神戸市兵庫区上祇園町:JR三ノ宮駅 | |
| 廣峯神社 | 素戔嗚尊 | 兵庫県姫路市広嶺山:JR姫路駅 |
| 素盞嗚神社 | 素盞嗚尊 | 広島県福山市新市町:JR上戸手駅 |
| 小倉祇園八坂神社 素盞嗚尊 | 北九州市小倉北区:JR小倉駅 | |
| 須佐能袁神社 素戔鳴尊 | 福岡県久留米市草野町:JR筑後草野駅 | |
| 須我神社 須佐之男命 | |
| 島根県雲南市大東町須賀:JR松江駅 | |
| 須佐神社 須佐能袁命 | |
| 島根県出雲市佐田町須佐:JR出雲市駅 | |
| 八重垣神社 素戔嗚尊 | |
| 島根県松江市佐草町:JR松江駅 | |
| 熊野大社 素戔嗚尊 | |
| 島根県松江市八雲町熊野:JR松江駅 | |
| 日御碕神社 素盞嗚尊 | |
| 島根県出雲市大社町日御碕:JR出雲市 | |
| 素盞雄神社 素盞雄大神 | |
| 東京都荒川区南千住:JR南千住駅 | |
| 須賀神社 須佐之男命 | |
| 東京都新宿区須賀町:JR四ツ谷駅 | |
| 氷川神社 須佐之男命 | |
| さいたま市大宮区高鼻町:JR大宮駅 | |
| 津島神社 建速須佐之男命 | |
| 愛知県津島市神明町:名鉄津島駅 | |
| 熱田神宮 素盞嗚尊 | |
| 名古屋市熱田区神宮一丁目:JR熱田駅 | |
| 八坂神社 素戔嗚尊 | |
| 京都市東山区祇園町:京阪祇園四条駅 | |
| 須賀神社 素盞鳴尊 | |
| 和歌山県みなべ町:紀勢線南部駅 | |
| 祇園神社(神戸・平野) 素盞嗚尊 | |
| 神戸市兵庫区上祇園町:JR三ノ宮駅 | |
| 廣峯神社 素盞鳴尊 | |
| 兵庫県姫路市広嶺山:JR姫路駅 | |
| 小倉祇園 八坂神社 素盞嗚尊 | |
| 北九州市小倉北区:JR小倉駅 | |
| 須佐能袁神社 素戔鳴尊 | |
| 福岡県久留米市草野町:JR筑後草野駅 | |

全国のクシナダヒメ神社
八 重 垣 神 社
(御祭神:素盞嗚尊、稲田姫命)

YouTube  八重垣神社の巫女舞(5分) 八重垣神社の巫女舞(5分)  鏡の池占い(4分) 鏡の池占い(4分) |
YouTube  八重垣神社の巫女舞(5分) 八重垣神社の巫女舞(5分)  鏡の池占い(4分) 鏡の池占い(4分) |
| 須我神社 | 稲田比売命 | 島根県雲南市大東町須賀:JR松江駅 |
| 須佐神社 | 稲田比売命 | 島根県出雲市佐田町須佐:JR出雲市駅 |
| 八重垣神社 | 稲田姫命 | 島根県松江市佐草町:JR松江駅 |
| 稲田神社 | 奇稲田姫之命 | 茨城県笠間市稲田:JR水戸線稲田駅 |
| 氷川神社 | 稲田姫命 | さいたま市大宮区高鼻町:JR大宮駅 |
| 六所神社 | 櫛稲田姫命 | 神奈川県中郡大磯町:JR二宮駅 |
| 櫛田神社 | 櫛稲田姫命 | 富山県射水市串田:JR新高岡駅 |
| 木田神社 | 稲田姫命 | 福井市西木田:福武線商工会議所前 |
| 八坂神社 | 櫛稲田姫命 | 京都市東山区祇園町:京阪祇園四条駅 |
| 須賀神社 | 櫛稲田姫命 | 和歌山県みなべ町:紀勢本線南部駅 |
| 祇園神社 | 櫛稲田姫命 | 神戸市兵庫区上祇園町:JR三ノ宮駅 |
| 廣峯神社 | 奇稲田媛命 | 兵庫県姫路市広嶺山:JR姫路駅 |
| 櫛田宮 | 櫛稲田姫命 | 佐賀県神埼市神埼町:JR神埼駅 |
| 須我神社、稲田比売命 | |
| 島根県雲南市大東町須賀:JR松江駅 | |
| 須佐神社、稲田比売命 | |
| 島根県出雲市佐田町須佐:JR出雲市駅 | |
| 八重垣神社、稲田姫命 | |
| 島根県松江市佐草町:JR松江駅 | |
| 稲田神社、奇稲田姫之命 | |
| 茨城県笠間市稲田:JR水戸線稲田駅 | |
| 氷川神社、稲田姫命 | |
| さいたま市大宮区高鼻町:JR大宮駅 | |
| 六所神社、櫛稲田姫命 | |
| 神奈川県中郡大磯町:JR二宮駅 | |
| 木田神社、稲田姫命 | |
| 福井市西木田:福武線木田四辻駅 | |
| 八坂神社、櫛稲田姫命 | |
| 京都市東山区祇園町:京阪祇園四条駅 | |
| 須賀神社、櫛稲田姫命 | |
| 和歌山県みなべ町:紀勢本線南部駅 | |
| 祇園神社、櫛稲田姫命 | |
| 神戸市兵庫区上祇園町:JR三ノ宮駅 | |
| 廣峯神社、奇稲田媛命 | |
| 兵庫県姫路市広嶺山:JR姫路駅 | |
| 櫛田宮、櫛稲田姫命 | |
| 佐賀県神埼市神埼町:JR神埼駅 | |
YouTube 9分 |


奥出雲おろちループ

ヤマタノオロチをイメージした日本最大規模の二重ループ方式の道路
とぐろを巻く大蛇 のようですね





国道314号 福山市~三刀屋町 総延長140km
左方は 道の駅 奥出雲おろちループ
左方は 道の駅 奥出雲おろちループ



紅葉に映える三井野大橋 10月31日
紅葉見頃情報:日本気象協会



一重目のループ橋



トロッコ列車「奥出雲おろち号」道の駅から遠望

標高差162m:距離約6.4km:ニッポン旅マガジン


ヤマタノオロチをイメージした日本最大規模の二重ループ方式の道路
とぐろを巻く大蛇 のようですね





国道314号 福山市~三刀屋町
総延長140km
総延長140km



紅葉に映える三井野大橋 10月31日
紅葉見頃情報:日本気象協会



一重目のループ橋



トロッコ列車「奥出雲おろち号」
道の駅から遠望
| 出雲坂根← | JR木次線 | →三井の原 |
| 標高564m | 標高726m |
標高差162m:距離約6.4km
ニッポン旅マガジン
ニッポン旅マガジン
出雲坂根駅の愛称は 天真名井
三井野原駅の愛称は 高 天 原


もう一つの スサノオ神話

島根県 大田市 五十猛町

 ・
・しかし、ここに
・ |

神 島 と 神 上
神島 と神上
 ・
  ・726年(
|

|
五十猛 (地理院地図) |

YouTube 島根県大田市五十猛町 |

和田珍味本店からの眺め
国土交通省とるぱの全国人気ランキング第1位

「VIEWCAFE&SHINWA」からの眺めは最高です
カフェでコーヒを頂きながらの眺めは、日中はもとより
夕日の眺めはすばらしい!
夕日の眺めはすばらしい!
ご参考:松江の夕日時刻
是非一度の眺望をお勧めします

神 別 れ 坂
 |
 |
| 神別れ坂 | 坂から見る神島・神上 |
 ・
 ・
それぞれの  ・ここを
場所:地理院地図
|
|



 ・
 ・
それぞれの  ・ここを
|
左:神別れ坂、地図:地理院地図

韓 神 新 羅 神 社
 |
 |



  ・
 ・
 ・
 |


五 十 猛 神 社

逢 浜

大 屋 姫 命 神 社

(大田市大屋町)
 |
 |
 ・
 ・当地において建築に務められといわれる
  ・場所:地理院地図
|
|





・鬼岩の場所:地理院地図

・明治22年 町村制 の施行 により鬼村は、迩摩郡大屋村 (大国村の一部、大屋村、鬼村) となる
・昭和31年9月 大田市第3次合併で、大田市大屋町鬼村となる
・全国 で鬼村 と名 ずくのはここだけ

 YouTube 大屋神楽社中-「田村」   ダイジェスト 鬼岩祭り (15分) ダイジェスト 鬼岩祭り (15分) |

| 鬼村の鬼岩はこちら |
国引 き神話 (三瓶山西の原の看板)
国 引 き 神 話
(三瓶山西の原の看板)

| Home | TopPage |