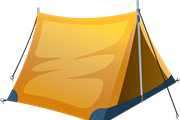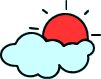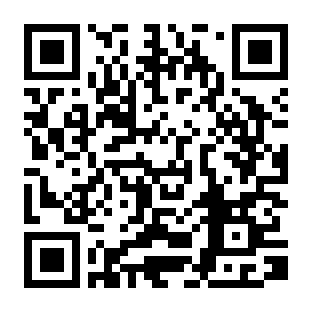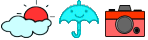龍 源 寺 間 歩
り ゅ う げ ん じ ま ぶ   ・
  ・間歩の横などに、銀鉱脈を追って掘った間歩(ひおい坑)があります
 ・観光ガイドと巡る石見銀山 龍源寺間歩 島根観光ナビ
前編(石見銀山公園~遊歩道) → 後編(豊栄神社~龍源寺間歩)
   ・
  ・間歩の横などに、銀鉱脈を追って掘った間歩(ひおい坑)が多くあります
       |





 |
||
| 地理院地図 | 貸し自転車 | |
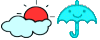 天気予報天気予報 天気予報天気予報 |
ぎんざんカート |





|
|
|
|



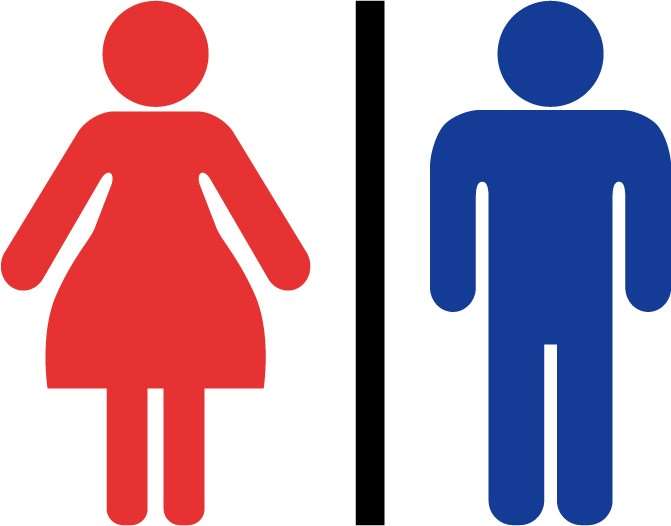
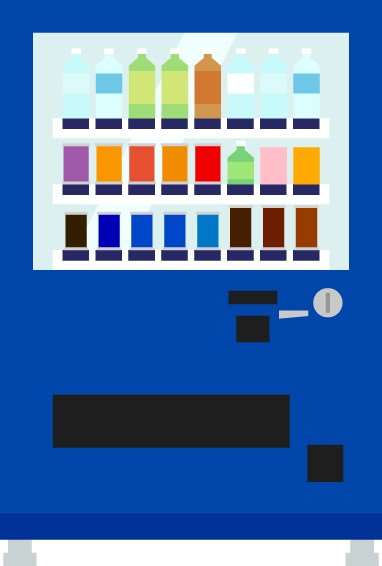

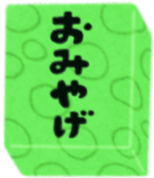

|
必見!
  ↑
    |
石見銀山公園
 ・観光パンフレット(必見)
銀山ゾーン編(銀山公園~龍源寺間歩)
石見銀山みてあるきマップ
(散策地図) 銀山ゾーン編
(銀山公園~龍源寺間歩)   Google 航空写真
 |

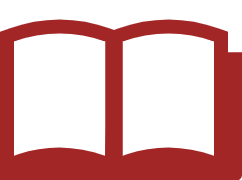 お勧め本
お勧め本『しろがねの葉』(新潮社)
石見銀山舞台 女性の一代記 直木賞の千早 茜 さん
文庫本 新潮社 電子書籍あり
『輝山 』澤田瞳子著 「石見銀山」濃密な群像劇
(徳間書店)産経新聞 2021.11.14

・世界遺産級の銀鉱石標本発見 石見銀山の江戸期産出品 世界一だった往時の姿ベール脱ぐ 産経新聞 2017.5.19







 |
||
 YouTube( 3分)石見の火山が伝える悠久の歴史 大田市 YouTube( 3分)石見の火山が伝える悠久の歴史 大田市 |
||
|
石見の火山が伝える悠久の歴史
・現代によみがえる縄文の森
・豊かな暮らしを育んだ三瓶火山
・火山が生んだ石見銀山
11.大江高山火山
12.石見銀山遺跡(仙ノ山の福石鉱床)
13.大森銀山地区
14.琴ヶ浜
・暮らしを支えた火山のめぐみ
| ||
|
注.石見銀山の銀鉱床は 約100万年前に、大江高山火山群の火山活動を引き起こしたマグマから発生した熱水によってできた鉱床(しろがねの山)
山陰・島根ジオサイト 地質百選 |
||
 YouTube(3分)石見の火山が伝える悠久の歴史 YouTube(3分)石見の火山が伝える悠久の歴史 |
|
・現代によみがえる縄文の森
・豊かな暮らしを育んだ三瓶火山
・火山が生んだ石見銀山
11.大江高山火山
12.石見銀山遺跡(仙ノ山の福石鉱床)
13.大森銀山地区
14.琴ヶ浜
・暮らしを支えた火山のめぐみ
|
|
注.石見銀山の銀鉱床は 約100万年前に、大江高山火山群の火山活動を引き起こしたマグマから発生した熱水によってできた鉱床(しろがねの山)
山陰・島根ジオサイト 地質百選 |
 YouTube (3分) 大田市
 ♪大田市観光PR動画フニクリ・フニクラ大田市版
 ♪Oda city PR Movie - Japan Funicli, Funicula Oda City
   |
 YouTube (3分) 大田市 |
♪大田市観光PR動画
フニクリ・フニクラ大田市版 |
♪Oda city PR Movie - Japan
Funicli, Funicula Oda City
|
  |
 |
 YouTube   第2話  第3話  第4話  第5話  「  公益社団法人 石見大田法人会 著作 アニメでわかる!石見銀山 |
| YouTube |
 第2話  第3話  第4話  第5話  ・ ~  ・公益社団法人 石見大田法人会 著作 アニメでわかる!石見銀山 |




大 久 保 間 歩
お お く ぼ ま ぶ  ・
   |


・バスを降 りて登 ること3分



・右手 に金生坑跡 (水抜 き用 ・鉱石 を運 ぶ坑道 )
注.××間歩 (~江戸時代 )
××坑 (明治 ~)
と名付 けているようです
××
と



|
・
・ |

 |
 |




|
・
・カメラは
・
・
・ |




銀鉱石の堀出し間歩。大きいですね

|
・
・
|




| クリック表示:上、下 ・
・ |



|
・
・
|



|
・ツアーに
・『しろがねの葉』(新潮社) 石見銀山舞台 女性の一代記 直木賞の
|
清 水 谷 精 錬 所 跡
 |
 |
|
左:清水谷精錬所跡(傾斜地を利用)
右:間歩の入口(銀山地区で600以上ある)
・清水谷精錬所跡 るるぶ
|
世界遺産石見銀山の案内

マスコットキャラクター「らとちゃん」
マスコットキャラクター |
「らとちゃん」 |

五百羅漢 と大森の町並み


資料やパンフレット(必見)
石見銀山の知識を得る・深める
| 石見銀山のバーチャルミュージアム (マップ・歴史・開発・絵巻・銀貨など) |
車で石見銀山へ行く
交通規制(パークアンドライドついて) 世界遺産センター、バリアフリー・駐車場  カーナビの設定 Tel:0854-89-0183 iタウンページ  石見銀山バスマップ |
石見銀山・三瓶山 バス案内
石見銀山遺跡までのタクシー料金
大田市駅から石見銀山遺跡(世界遺産センター)までの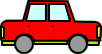 タクシー料金:NAVITIME タクシー料金:NAVITIME |
YouTube を紹介します

YouTube しまねっこCH ・世界遺産の町に息づく人と営み~歩いて巡る世界遺産
  ・もっと知りたい!世界遺産・石見銀山
    |
やなしお道・茶縁原 から三瓶山 遠望
やなしお道・茶縁原 から
三瓶山 遠望


・やなしお道は、石見銀山から赤名峠 を経て瀬戸内海の尾道 まで産出銀を人馬で運ぶ銀山街道(起点の銀山に近い部分)


・美郷町観光協会:別府里あるきマップ

・ご参考サイト:やなしお月例ウォーク

・ご参考サイト:銀の道(銀山街道):笠岡市
ちょっと寄り道ですが・・・
・石見銀山の産銀量がピークとなる:1690年:612.840貫、1691年:625.705貫(石見銀山ことはじめⅠ)
・1貫=3.75Kgで換算すると古文書ネットさん
612.840貫=2,298.15kg≒2.3t
612.840貫=2,298.15kg≒2.3t
・駄馬で運ぶと、どうなるのでしょうか?
銀10貫目入木箱をコモで包み両背に括り付けた(石見銀山ことはじめⅠ)
612.84貫/20貫≒30.6頭にもなります
銀10貫目入木箱をコモで包み両背に括り付けた(石見銀山ことはじめⅠ)
612.84貫/20貫≒30.6頭にもなります
・1768(明和5年)年10月の輸送量は、灰吹銀12箱(180貫目)、年貢銀8箱(77貫目)、銅208箱(2,496貫目)で、 それに使用された馬は全体で140頭にもおよんでいる(石見銀山ことはじめⅠ)

・文化年間(1804~1818年)には銅の生産は年間5000貫目以上に達し宿駅や助郷村ではこの輸送が大きな負担となった(石見銀山ことはじめⅠ)

・ちなみに銀1貫の価格は現代で約125万円とのこと(古文書ネットさん)
→612.840貫(1690年)×125万円=7億6600百万円にもなります
→612.840貫(1690年)×125万円=7億6600百万円にもなります
仙ノ山 から三瓶山 遠望
仙ノ山 から三瓶山 遠望



1月17日、Wide、地理院地図、遠望距離 16.4km
・石見銀山世界遺産センターの背後の山は仙ノ山(標高538m)です
・仙ノ山展望台(標高328m)は、同山の中腹にあります
・展望台に行く場合は同センターで、道順等をお尋ねください
石見銀山みてあるき(世界遺産石見銀山センター)
石見銀山みてあるき(世界遺産石見銀山センター)




(1124m)、(961m)、(907m)
1月17日、Wide、地理院地図、遠望距離 16.4km

・石見銀山世界遺産センターの背後の山は仙ノ山(標高538m)です
・仙ノ山展望台(標高328m)は、同山の中腹にあります
・展望台に行く場合は同センターで、道順等をお尋ねください・地図
三瓶山 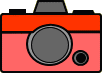 |
||
| 絶景スポット | ・ | 山麓の四季 |

大江高山火山群・ 銀 の山 を遠望
大江高山火山群・
銀 の山 を遠望

| Home | TopPage |
|
Copyright © 2003- 北三瓶会 All Rights Reserved.
Never reproduce or republicate without written permission. 無断転載禁止
|
|
Copyright © 2003- 北三瓶会
All Rights Reserved.
Never reproduce or republicate without written permission. 無断転載禁止
|
 泉
泉