| 明治時代に海軍が軍備を整えるべく、海外から船を購入し始める頃、丁度錨の種類が増え始め、 日本にも様々な錨が輸入される。この頃の日本では錨の種類を十字型(ストックアンカー:イギリス海軍の呼称にならいアドミラルティーア
ンカーと読んでいた)、十山字型(マーチンスアンカー等の様な形状)、山字型(ストックレスアンカー)と呼び分けており、商船や大型の 郵便船などでは人員削減を目的にかなり早い時期から山字型を導入していたようである。 日本海軍は数ある山字型アンカー(Tyzack, Smith, Inglefield, Dunn, Hall, Baldt等)の中からHall型(ホールパテントアンカーと呼んで いた)を採用し小型艦で使用し始める。大型艦には1902年にイタリアで起工された「日進」「春日」に採用されたのが最初の様である。ただ明治40年の海軍兵学校教科書によると、 |
 十字型(ストックアンカー) |
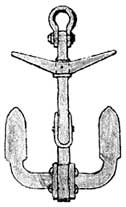 十山字型(絵はマーチンスアンカー) |
|
| 通常の軍艦に装備しているアンカーはアドミラルティーアンカーとマーチンスアンカーが多かったようである。イギリス海軍が使用していたとは言え、ストックレスアンカーに対する把駐力の不信感が拭い切れず、採用数の伸びはゆっくりとしていた様である。 Hall型はシャンクヒンジを固定するピンの構造に特許があり、パテントアンカーと呼ばれていたが、日本においてその特許出願が成されていない事や、イギリスの製造会社にとって日本の鉄工所の事など気にも止めていなかった事、特許の審査が非常に甘かった事もあり、神戸製鋼所がシャンクヒンジを固定するピンの入れる方向を変えただけで、姿形から性能まで全く同じコピー商品を作り、神戸製鋼所式無カン錨として明治40年に実用新案として申請している。日本は他国の技術を取り込み、独自の技術へと進化させてより良いものを作る事が得意であるが、錨においては何の改良も無くただコピーしただけで終わってしまった。神戸製鋼所はこの錨を日本海軍へ売り込み、多くの船へ艤装されていく。この時、形が同じためにHall型=パテントアンカー=神戸製鋼所型となり、日本海軍ではこの形の錨全てを海軍型として呼称して行く事になるのである。 |
 山字型(ストックレスアンカー) |
||
| 昭和26年にチェーンメーカーである国光製鎖の社長大畠小市氏が出した原案を基にチェーンについての標準規格(JIS規格)が作成される事になり、これに伴ない錨についてもJIS規格を作成する事になる。元々チェーンの基準を作る目的で人を集め、審査を行っていたため、錨に対しての検証は全く行っておらず、多くの船が使用していた事を理由に、海軍型をJIS型と命名し採用したのである。この時から錨に対する虚構の安全神話が生まれるのである。 昭和40年代になってイギリス海軍の研究機関が考案したAC-14アンカーがやってくる。JIS型に比べて把駐力も高く、イギリス海軍が開発した事もあり、東京チェーンアンカー㈱が昭和50年に特許契約をし、AC-14の製造を始める。しかし、かなり短い期間に製造したAC-14が3回ほど爪を折る事故を起こし、その信用を失ってしまう。これをきっかけに負債を返済する事が出来なくなり倒産してしまう。事故原因は鋳造技術が劣っていたため爪の部分に亀裂があり、爪に加わった力に耐えられなかったためとされているが、元々AC-14アンカーはイギリス海軍が軍艦用に開発した軽量アンカーであるため、爪が薄く自慢の把駐力を発揮してしまうとその力に耐え切れず、曲がったり折れたりしてしまう錨なのでる。しかし、2000年に日本船舶標準協会は、JIS型を採用した時と同じように、錨に対しての調査などをほとんど行わないで、錨を鋳造する企業体の意向だけでAC-14型アンカーをJISに認定してしまう。現在JIS型をJIS-A、AC-14型をJIS-Bとしている。 日本で製造、使用されている錨のほとんどが、外国で長い時間と莫大な費用を費やして研究開発して来たもので、日本で開発したアンカーはDA-1を除いて全く存在しない。ただ、これまで何の研究もしていなかったわけではない。各商船学校や政府機関で海外の研究機関に負けないぐらいの時間とお金をかけ、様々な錨を開発してきている。単に商船で使えるほどの性能と信頼性を持ち得なかっただけなのである。 今や、錨も錨鎖も中国などからの安い製品が輸入されている(JISがあるため簡単に海外製品が国内で使用できる)ため、日本の製造メーカーは衰退の一歩を辿っている。AC-14型等は曲損や折損事故をよく起こすが、その修理すらできなくなっているのが現状である。 日本における錨の歴史とは、とても海洋大国、造船大国のものとは言えない歴史だが、21世紀になり過去とは比べ物にならない高い技術力と開発力を手に入れた今、新たな歴史を築き上げるのが我々の使命ではないだろうか。 |
|||