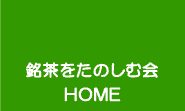
◇ 中国雲南省お茶の旅(Ⅲ)
~少数民族ジノー族の茶農家での体験~
|
バスに揺られて数時間、古代プーアル茶、六大茶山、基諾亜諾村へ到着。 |
|
| |
|
| 村では、茶の摘採から完成まで(毛茶)を生産、出荷して生計を立てている。 ここ数年”プーアル茶“の需要が特に欧米や日本で高まり、生産農家は豊かな暮らしが出来るようになったらしく、5年前とは全く赴きが変わり、住居は新しくなり、若者は外車(ほとんどが日本車)に乗り、がんがんと大きく音楽をかけながら走っている、という現状である。 一昔前までは、教育が受けられずにいた村人達の子供たちは、街の学校で立派な高等教育が受けられるまでになっている、と伺った。生活水準が上がることは、いいことではあるがそれに伴い代々受け継がれてきた素晴しい文化がなくならないことを切に願うばかりである。 この村、ジノー族の茶農家で、伝統的な茶の作り方を体験させてもらいながら取材する ことができた。 まずは、原料となる茶を摘む。 |
|
| |
|
| 早々、茶畑へ向かう。村から15分程度歩いたところ。斜面に茶の木が栽培されている。 日本で見るようなきれいに整然と並んでいて手入れも行き届いた、という状態ではないが、とても自然にどちらかというと、野生の茶木といった状態である。 今日必要な分量のみを、丁寧に手で摘む。 |
|
| |
|
| 私も一芯二葉(未だ開かない新芽と二つの若葉)で摘んでいく。 本当に数十分で終了。これで今日の使用量は充分とのことである。何となく無駄のない摘 採量で納得できる。自宅に持ち帰り早速茶作りを教えていただく。 1つ目。 涼伴茶(りょうばんちゃ) |
|
| |
|
| ① 生の茶葉を手で軽く揉み、竹製の筒(縦半分に割った容器)に入れ、棒でさらに揉ん だり、突いたりしながら茶汁や風味を出す。 |
|
| |
|
| ② その中にどくだみの葉・八角(野生)にんにく・柑橘系の葉をいれ、よく混ぜ、その上 から沸き水(やかんで一度沸かしたもの)を入れる。味付けは唐辛子と塩のみ。塩辛 味、にんにく風味のスープの出来上がり。 ※ 日常的に作ることはなく、お祭りや年間行事・来客時に作って、おかずとしてい ただくもの。 2つ目。 焼き茶 |
|
| |
|
| ① バナナの葉に生茶葉・にんにく・等を入れて包み、囲炉裏のなかへそのまま入れる。 表面がこげたら、引き上げ丁寧に中身を取り出し、竹筒にいれて湯を差し飲用。 |
|
| |
|
| 3つ目。 竹筒香茶 (?茶:こうちゃ) ① 竹筒を50~60cmくらいにカットしたものを用意。 |
|
| |
|
| ② その中に生茶葉と水をいれ、薪に火をつけ、その中へ入れ、時々回しながら均一に 火が廻るようにし沸騰させる。焙ばしい香がしてきたら取り出し、グラス又は竹筒に 移して飲用。野外で農作業時休憩、昼食時に作る。 |
|
| |
|
| これらを一同に試飲させていただいた。 ①の涼伴茶は本当におかずになるような、スープ。とてもおいしい。塩辛くてさっぱりお いしい。 ②の焼茶は焙ばしく、さっぱりなんにでも合わせやすい、日常のお茶。 ③の竹筒香茶はやはり野外で簡単に作れる便利さがさすがに生活に密着してい食後に ぴったりのすっきりタイプ。 どれも、こちらの風土・気候・用途に合っているからこそ長い年月続けられ、大切にされて いるお茶の形であった。これからもずっと守っていって欲しいと心から切に願いながら 取材を終えた。 次回はこの村の生活とお茶について書いてみたい。 |
|