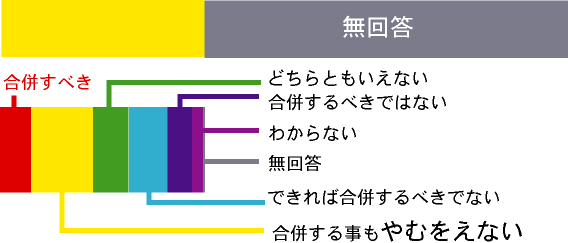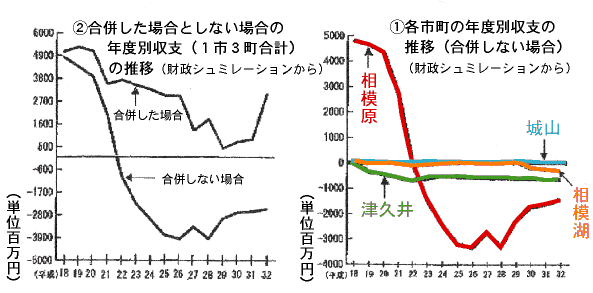|
合併したら、藤野は相模原市に「大切に」扱ってもらえるのでしょうか。
私にはそうは思えません。何しろこの合併、住民がそれによって幸福になるかどうかなんかはどうでもよく、とにかく『合併したいから合併する』ものに見えてならないのです。
相模湖町では町長選挙では合併推進の候補が僅差で当選しましたが、この町長の公約である、合併の是非を問う住民投票を行った結果、今度は僅差で合併反対が多数になりました。しかし、相模湖町の町長は、この結果を無視して合併を強行しようとしています。
特に一番問題だと思うのは、『合併しなければやっていけない』という雰囲気を煽って、住民を不安に陥れて合併を推し進めようとする動きがあることです。(始めは藤野町だけだと思ってましたが、どこの町でも同じ事が起こってたようですね)
どこの町でも、いきなり降って湧いたかのように『この町は財政破綻寸前だ。合併しなければもうやっていけない』という主張が一気に高まりました。確かに財政状況が厳しい町もある事はありますが、いずれの町も都心への通勤圏でもあり、それなりに税収もあり、本気で財政改革に取り組めば、決して『やっていけない』という状態ではなさそうです。
私には、全く産業もなければ観光資源もない、都会から遥かに離れた地方の過疎の町村が、『いよいよこれではやっていけない』と言うのなら判るのですが、少なくとも津久井郡の各町が、『合併しなければやっていけない』と言うのは諦めが良過ぎるように思えます。
もしくは自らを改革する意欲がないとか。
『合併しないとゴミの回収に来てくれなくなる』
藤野町も含め、これもよく広まった噂でした。
噂どころか、実際に相模原市の市長は、急いで行う合併に批判的な城山町の町長に対して、「合併に参加しなければゴミ処理は受け入れない」と言って来ました。結局、城山町の町長が、「ゴミの回収を引き受けないと脅迫されている状態では、城山町民に合併の是非を問う住民投票はできない」とつっぱねた為に、「城山町が単独で残っても、ゴミ処理に応じる」と言って来ました。じゃあ、始めの「合併に参加しなければゴミ処理は受け入れない」という理屈はなんだったんだろう。
津久井郡4町は、ゴミ処理や消防・救急などの行政サービスを広域組合を作って行って来ました。確かに相模原市との合併が成立すれば、この組合は解散して、相模原市の組織と一体化する事になります。しかしだからといって、これらの行政サービスを合併に反対する勢力に対する脅迫の材料に使うというのはどうでしょう。まるで、住民を追い出すために生活基盤を破壊しようとする地上げ屋の手口です。
相模原市は中核市、将来は政令指定都市を目指しています。それだけ、その地域の中核を担う役割を自認しているわけです。
総務省は、たとえ合併を選ばなかった自治体であっても、それによって広域行政サービスの低下するような事態を許さないよう通達しています。
熊本や山口では、合併しない事になった自治体が、合併した自治体と新しい広域事務組合を設立する事例や、事務依託の協定を探る事例もあります。
これが本来の『中核市』が採るべき姿勢であって、肩書きに見合った人格・徳だと思います。肩書きに見合った人格のない人間は世の中にありふれてますが、上司の選べない会社の話ならともかく、わざわざこちらから合併して配下につきたがる事もなかろうと思います。
それくらい、今の合併は露骨に脅迫的な圧力で進めらているのが目につきます。
「無理を通せば道理が引っ込むだろう」と言わんばかりの強硬なやり方がどんどんまかり通り、合併への道筋が粛々と作られて行くのが悔しいのです。合併せずに単独でやって行くのは怖いと言う人もいるかもしれませんが、こんな脅迫で出来た市に組み込まれる事の方が、今の私には恐怖に感じさせます。
●
|