| 1 顔の見える距離 |
|
夏目漱石の『坊ちゃん』で、江戸っ子の主人公が教師として赴任した田舎町で散歩すると、次々と知っている人と出くわし『どうも狭い町だ』とぼやく場面が出て来ます。私も藤野町を車で走ると、よく知ってる人とすれ違って手を振ります。 これは役場にも当てはまります。 |
| 2 政治の自浄能力 |
|
リコールなどの、住民が政治に対して直接的な要求をする場合、自治体の人口が3万人を越えると、その成功率は急激に減ると言います。言い換えれば、直接請求ができる状態が欲しければ、自治体の人口は3万人を越えてはいけないという事になります。(下の図は、人口規模別に見た、直接請求の成功数のグラフです。) 直接請求の法定署名達成件数 (1947〜1984) 水色は議会の解散 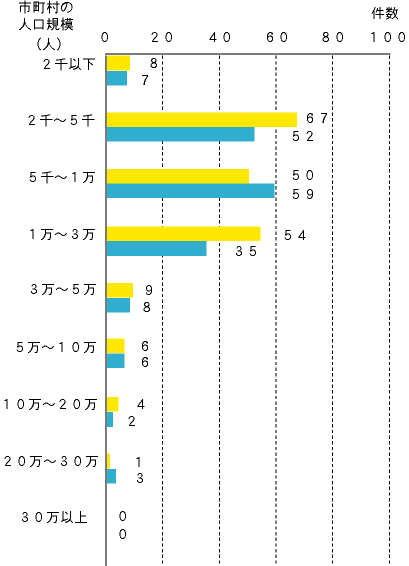 巨大な町になると、たとえ町に対して意見があっても、自分の意見がとても小さく、全体から見れば採るに足らない物に感じてしまいます。選挙でも、 人口以外に、面積が拡大する事によって、政治から住民が遠ざかる傾向もあります。例えば、面積の広い自治体では、議会の傍聴に行くにも、遠方の住民には負担が重くなります。 自治体の広さには、政治の自浄能力が発揮できる限界があります。逆に言えば、自浄能力が発揮しやすい人口と広さの町も、想定できます。今の藤野町は、なかなか理想的な位置にいると思います。 石橋湛山の言葉
|
| 3 その土地に即した、きめ細かな行政 |
|
これは1の『顔の見える距離』と関わってますが、例えば介護でも、10人の職員が100人の人を面倒みるのと、100人の職員が1000人の面倒を見るのでは、数の比では同じでもその内容は違ってきます。 行政サービスは、単に自治体が大きくなれば効率化できると言うものではありません。人口密度、その土地の産業、住民の暮し、その土地の特性に合わせて最適化したほうが、効率化は図れると思います。逆に、異なる地域特性の町に同じ行政サービスを適応させようとすると、かえって無駄も増えると思います。 例えば、津久井郡4町は相模原市の3倍以上の面積があるにも関わらず、人口は相模原市の10分の1です。介護サービスにしても、大都市であれば民間の業者が沢山ありますが、藤野では人口密度が低くて採算があわないのか、なかなか民間の業者が来てくれない現状があります。これは保育園や幼稚園も同じです。 また、その地域が目指している方向性の違いも重要です。 自治体の人口が増え、面積が拡大するほど、その土地の抱える固有の問題は軽視されがちになると思えてなりません。 |
| とりあえず今回は、行政に関する『小さな町の良さ』を幾つか挙げてみました。他にもまだまだある事でしょう。行政以外にも、生活面での『小さい町の良さ』もある事でしょう。今後も思い付くたびに追加していきます。 |
| これらに関連して 「住民をやる気にさせる町の大きさ」も「雑文」の所に追加しました。 |