�s�n�o�hCS
�������ނ�����
2025/3
2025/3
����̏t�̉Ԃ���������
�I�E�o�C
�_���R�E�o�C
�t�T�U�N��
�I�E�o�C
�_���R�E�o�C
�t�T�U�N��

�����R
2025/1
2025/1
�R���ɗ����Ă����̎�
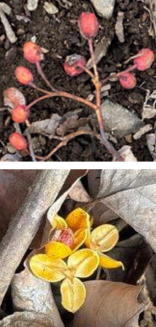
���_���x
2024/12
2024/12
�Ԃ��݂̂��C�ɂȂ�܂����B

�K�}�Y�~�i���j

�}���~�i���j
��O�Y�x
2024/11
2024/11

�ォ��
�z�R���_�P
�R�E���{�E�L�i����ⴁj
�z�R���_�P
�R�E���{�E�L�i����ⴁj
���F��
2024/10
2024/10

�����h�E
2024�i�ߘa6�j�N�x�̊���
�������ނ�����
2025�N3��15���i�y�j
�V��F�܂�̂����J
�V��F�܂�̂����J
�V�C�\��͉J����܂�ɁB�R�s�͓V�C���݂��B�����o�[�̂Ă��ς��Ƃ����s���ŗ\���葁���o���B�����n�߂͉��X��_�Ђ̎O�{���i�V�R�L�O���j���o�}���Ă��ꂽ�B
�ނ������̗͍�̈ē������Ɍ��ď������ƃR�[�X�L�����N�^�[���T�r�\�̈ē��@������B�H����͏����L�c�C�B�o�肫��Ɣp���Ղ̃g���l�����B���͓��_�����݂̂��ߎ��މ^���p�Ƃ��ė��p���ꂽ���̂����A���̈�\�����������ɁB�����̖ʉe���c�����H�A�����̎B�e�ɖZ�����B
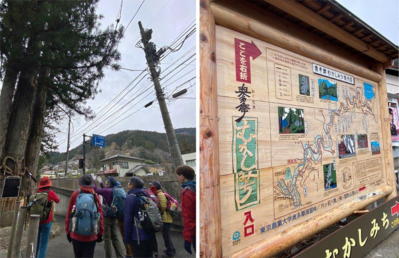
���X��_�Ђ̎O�{���Ƃނ������ē���

�p���Ձ@�g���l���ɐ��H
�Ŗi�����������j�̋����ɂ����`���Ɗ������A�s���̏��ցB���ꂢ�ȃg�C���ɗU�f����ĉ��l���g�C���^�C���BNHK�Ԃ�^�����ł��K�ꂽ���E�_�Ђ̑��̑O�ŏW���ʐ^���B��B

���H�̗����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ŗ�

���E�_��
�ٌc�̘r�ʂ���ɘr��ʂ��A���_�l�A����͕��̋����ɏH�̍g�t��z�����Ȃ���ʂ肷����B

�ٌc�̘r������@�r�ʂ����������H

���_�l
�₪�đҖ]�̃_�C�t�N�ցB�O�����ė���ł��������肳��̑啟���Ԍɂɂ������B������ɔ��������`�B�A��D�]�������B

1��100�~ ���肳��̑啟
�y�x�̕s�������߂���ƍŌ�̃g�C���̊ŔB�S���Ńg�C���^�C���B�������̃g�C���͓��{�ꂫ�ꂢ���������B��������̒��͏����h��邪���炵���y�x�k�J���]�߂�B���̓������͊�]�ґS���������̌��B�ȑO�͂P���5�l������������2���܂ł��B
12����菭���O�A���v�ۂ̐�Ԃ���O�x���`�t�߂Œ��H�ƂȂ����B

�����ω��̑O�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������̒���

�y���������`�^�C��
�n�C�L���O�R�[�X������ƎR���炵���Ȃ��ďI�_�̏��͓��_���߂Â��B
�������ΔȂʼn��U�̗\�肾�������V�C�̉������ƃo�X�����̃^�C�~���O�Ő����o�X��ɂďI���Ƃ����B
�������ΔȂʼn��U�̗\�肾�������V�C�̉������ƃo�X�����̃^�C�~���O�Ő����o�X��ɂďI���Ƃ����B

���������I�_ ���͓��_���Ɖ�������

�����o�X��ʼn��U
����̓n�C�L���O�R�s�̗ǂ��ŁA�A�����W�}�b�v�ƃ��T�r�\�𗊂�ɖ����̈ē���
��ǂ�A�B�e������A������ׂ肵����ŁA�t�̉Ԃ������Ȃ����̂̓��X�Ɍ�
�̉Ԃ��炢���B�y�����A���₩�ʼn��₩�ȎR�s�������B
 ���T�r�[
���T�r�[�������R�[�X
�������w�c�������ނ����������c�Ŗi�����������j�c�s���̑�c���E�_�Ёc�������c���v�ۂ̐�Ԃ���O�x���`�i���H�j�c�����o�X��i���U�j
�Q����18�� ��4����50���i�x�e�܁j
�j���R 626.5m
2025�N2��15���i�y�j
�V��F����
�V��F����
�����O�܂Ŋ��g�Ŋ������������Ă������A��]���č����͓����t�̗z�C�Ƃ̕�B����̎R�s�͒����S���̊F��w�W���Ŕj���R���B
�є\�w����̒��ҍs�d�Ԃ͍��G���Ă����������S�����ʂ��������B�F��w�ɂĎQ���҂��m�F���o�X�œo�R���ƂȂ�������O�ɁB�N���}�Ō��n����Ƀ����o�[��������21���ŏo���B
�є\�w����̒��ҍs�d�Ԃ͍��G���Ă����������S�����ʂ��������B�F��w�ɂĎQ���҂��m�F���o�X�œo�R���ƂȂ�������O�ɁB�N���}�Ō��n����Ƀ����o�[��������21���ŏo���B

�����D��34�� ������
�Q����o�蒁���D��34�Ԃ̐����������ɒ����Q�q�B�����̑��Ɛg�x�x�𐮂�����Ó���o���Ă����B�g�̂͊��݁A�r���Ő����⋋�ƈߗޒ������D�����ɗ��B

�����t�̓�������n�߂�

�D�����̐����łƏ����Ȋω��l
�Ó��̎D�����B�����Ȋω����ɘa�܂����B�ꑧ���ׂ��f�|���ĕ����W�]��ցB
����̔@������߂��������𑫌��ɋC��t���Ȃ���W�]��ɓ����B
�����s�X�n���L���蕐�b�R���V���G�b�g���ɖ]�߂��B
����̔@������߂��������𑫌��ɋC��t���Ȃ���W�]��ɓ����B
�����s�X�n���L���蕐�b�R���V���G�b�g���ɖ]�߂��B

�U�b�N���f�{���ēW�]���

�@�@����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����W�]��

�����W�]�䂩��̒��߁@�����~�n�ƕ��b�R
�ʐ^���B������A�W�]���y����ł��烄�Z�������D�����܂Ŗ߂�j���R�֓o��B
�R���ł͊�O�ɕ��b�R�����Đ����ɗ��_�R�ȂǁA�Y��Ȍi�F�߂Ȃ��璋�H���Ƃ�B
�R���ł͊�O�ɕ��b�R�����Đ����ɗ��_�R�ȂǁA�Y��Ȍi�F�߂Ȃ��璋�H���Ƃ�B

�N�T���̋}���߂�

�j���R�R���@�y���������`�^�C��

���_�R��]��

���������R��A�������̋���]��
�W���ʐ^���B��n���̑������Z�����𑫌��ɒ��ӂ��ĉ���B���̉���Ɏ��Ă�����̉���������A���ˋx�e�ɂɗ\���葁�߂ɒ������B
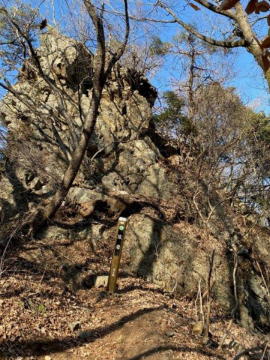
����

�����܂�ōŌ�̋x�e
�Ō�̋x�e���Ƃ��Ă��牺�R���̖���̓��ɉ��肽�����U�B��]�҂͉��������
�y����ł���A�r�ɏA�����B
�������R�[�X
�D���O�c�������c�D�����c�W�]��c�D�����c�j���R�c���˕���c���ˋx�e�Ɂc����̓��i���U�j�@�@�Q����21�� ��4����25���i�x�e��90���j
�����R 982m
2025�N1��25���i�y�j
�V��F����i���܂�j
�V��F����i���܂�j
�劦���߂��A�{���Ȃ犦������Ԍ������͂����A���̓��͒g�����g�������₩�Ȉ���B
�Q����20���ƂȂ�R�ǕҐ��ō����R�����������B
�Q����20���ƂȂ�R�ǕҐ��ō����R�����������B
����w�ŏ����̑������ďo���A���Ă̏h�꒬�̖ʉe���c���b�B�X���𓌂֍s���B���W����������Ă��ēo�R�҂ɂ͂��肪�����B�o�R���Q�[�g�ɒ����ߕ��̒����ŏ��x�~�B

�ߗޒ������ĎR���ɓ���@�@�i�o�R���Q�[�g�t�߁j
�������r�͖h���H�����Œr�Ȃ̐��ʂɓ��e�����������X�̗����邱�Ƃ͂ł����c�O���B���̌�́A�������𗁂ёۂ̗�ῂ���������i�ށB
���H������ɒ����B�Ε�������悤�Ƀp���t���b�g�ɂ͋L�ڂ��Ă��邪�A�Ռ`���Ȃ��Ȃ��Ă���B
���H������ɒ����B�Ε�������悤�Ƀp���t���b�g�ɂ͋L�ڂ��Ă��邪�A�Ռ`���Ȃ��Ȃ��Ă���B

�ۂނ����n�莟��Ɏ��т̒���
�͗t�œo�R�����������Ă��Ă킩��ɂ����B�E�̘H��o��B�͗t�A�|�̘H�𒍈ӂ��Ȃ���o���Đ�l�����Ւn�ŁA���x�~�B���̐́A��l���������Ă����Ƃ������A���݁A�ʉe�͂Ȃ��B

���t��œo��

�|���܂����@�܂��@�܂���

���邢�������@���������ō����R���I

�s���~�_���ɖ]�ޑq�x�R
�R����O�A�}�o�̃q�m�L�т����\����������B�����ɏo�āA�ЂƓo��ō����R�̎R���ɒ����B�C���͂T���A�������Ɋ����݂�Ȉꖇ�H�D��B
�u�x�m�R�G����i�v�̎R�Ȃ̂ŁA�y���݂ɂ��Ă������A�_���o�ĕx�m�]�߂��c�O�B
�u�x�m�R�G����i�v�̎R�Ȃ̂ŁA�y���݂ɂ��Ă������A�_���o�ĕx�m�]�߂��c�O�B

�Ō�̓o��@��C�ɍ����R����

�x�m�R�͉_�B��@�c�O

�R���Œ��H�x�e
�R���Œ��H�x�e�̌�A�ǂ��Ƃɂ��Ɨ����H������B
�r���A��l�����Ւn�ƌ��H������ŏ��x�~�B�Q�[�g�ɖ߂�A��ܑ͕����H��w�ɖ����������ĉ��U����B
�r���A��l�����Ւn�ƌ��H������ŏ��x�~�B�Q�[�g�ɖ߂�A��ܑ͕����H��w�ɖ����������ĉ��U����B

���t���ς芊��₷���}��̉���

�������ӂŐT�d�ɉ��R����
���U��A���l���͐�l�䂩��̓X�Ɋ��A�����̓V���ɂĊ��t�B
����ꂳ�܁I
����ꂳ�܁I
�������R�[�X
����w�c�o�R���Q�[�g�c���H������c��l�����Ւn�c�����R�c��l�����Ւn�c���H������c�o�R���Q�[�g�c����w�i���U�j�@�@�Q����20�� ��6���ԁi�x�e��70���j
���_���x 1169m
2024�N12��7���i�y�j
�V��F����
�V��F����
�A�N�Z�X�͐V�h���̍����o�X�B�荏�ɏo���������A�r���̎��̏a�Ɋ������܂�A�����R�o�R���i�o�X��j��1���Ԓx��œ����B�d�Ԃƃo�X�Ō��n�W�����������҂����Ă��܂����B

�����R�o�R���ŏo���O�̈��A
�S��������ăX�^�[�g�B��30���̓o�肪�I���ƌ�͒����Ő������B�K�C�h�u�b�N�ɂ͎R�X�̒��]���y���ނƂ������̂ɁA���ۂ͎��͂̃n�R�l�U�T���S���ȏ�Ɉ炿�A����̐�ȊO���������Ȃ��B

��q�ւ̌����@�@�@�@�@�@�@�@�@�����������o���Ă���
��q�ŋ����R���疾�_���x���q�������O�֎R�̗Ő��ɗ����A���_���x�����ցB�������Ԃ���悤�Ƀn�R�l�U�T�����������B

�n�R�l�U�T�̓��@�@�@�Ő��������[���n�R�l�U�T�����E���Ղ�
�Ő����ΑŐΎR����܂ŗ��ăA���p���^�C���B���̕ӂ肩����͎͂��R�тƃN�}�U�T�ɑ���A�g�t�┖�̊Ԃ����O�J�̔�����]�ށB
��x�k���Ɋ����ƁA���x�͔��Α��̒O��A���Y��Ɍ�����B
��x�k���Ɋ����ƁA���x�͔��Α��̒O��A���Y��Ɍ�����B

�ΑŐΎR����ŃA���p���^�C��

���������Ό��u�Ƒ�O�J�̕���

�O��R��̎R����]�ށ@�E�[�͑�R
����Ɖ_�������Ă����B���_���x�܂ł͊��x�����s�[�N���z���A�܂����܂����Ǝv���ĕ����A����Ƃ̎v���Ŗ��_���x�̒��ɒ��B

�����O�֎R�Ƌ����R�@���������2�����x�e��
�c�O�Ȃ���x�m�R�͉_�ɉB��Ă������A�����R�����P�x�A���͘p�z�ɂ͑哇�܂œW�]���L�����Ă����B�R���t�߂͑吨�̐l�ň�t���B
������H�ׂĂ��邤���ɗ₽�����ŃJ���_���₦�Ă����B
������H�ׂĂ��邤���ɗ₽�����ŃJ���_���₦�Ă����B

�����R�̐�ɉ_����x�m�@���_���x����]��

���͘p�̐�ɑ哇��]��
�R���ŏW���ʐ^���B���đ��X�ɉ��R�J�n�B�������x�Ƃ̕���́A�}�ȉ��肪�����T�d�ɉ����B�ꎞ�Ԕ��قǂ��ĕʑ��̐Ԃ������������ė������A���ꂩ�炪�܂�����������B
�₪�āA�ې������Ί_��A�s���N�F�̗����t������t�ɕ~���l�߂�ꂽ����������B�ƂĂ����͋C���ǂ��B

�{���։���}��@�@�@�@�@�@�@�H�F���܂��c���Ă����@
����Ɖ��R���̃o�X��ɒ����ƁA�����Ƀo�X�����āA�A�H�ɒ������B
�������R�[�X
�����o�R���c��q��10�F30�c�ΑŐΎR����c���_���x�c����c�{���c�Ə��o�X��
�Q����14�� ��6���ԁi�x�e�܁j
��O�Y�x�i�������R�j 1058,3m
2024�N11��9���i�y�j
�V��F����
�V��F����
�g�t�̃V�[�Y�����߂Â��A�b�{�w�̃o�X�^�[�~�i���͑��ւ�������A�ό��n���勬�Ɍ������l�Œ�����B����Ȃ��Ă��Ȃ�Ƃ��\��ʂ�̃o�X�ɏ��A30���ʂŏ��勬���ɓ����B

���勬���o�X��ŏ�������
�o�R����胏�C���[�Q�[�g���J���ĕ����n�߂�ƁA�܂��͍����̃��[�g�ň�Ԃ̋}�o�ƂȂ�B��E���܂��肾���A�������蓥�݂��߂ēo��B�ѓ��֏o��ƁA���S�������̂悤�ɁA��b���͂��ށB�ĂюR���ɓ���ƃz�R���_�P��R�E���{�E�L��ڂɂ���B

�S�n�悢�C��̒�����

�z�I�m�L�i�p�̖j�̗��t���

�O���m��

���t�̒���o���čs��
����ŁA�A���p���^�C�����Ƃ������ƁA�܂������R��ڎw���B
��O�̓W�]�䕪��œ�A���v�X�Ȃǂ̓W�]���]�߂�L���ꂽ�Ŕ����ڂɂǂ�ǂ�����R�i�k�m�s�̒�R�j�̂悤�Ȕ����̒n�ʂցB
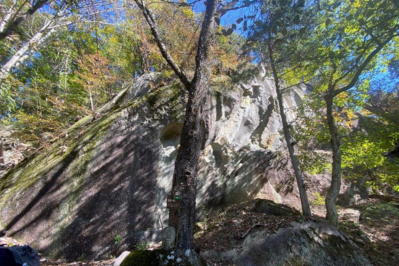
���H����
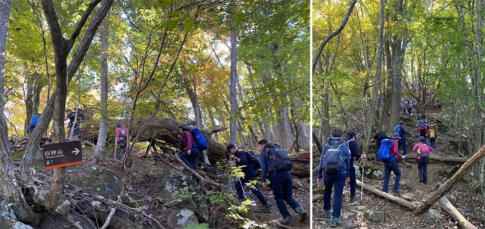
�������ѓ��@�����R��ڎw���ēo��
�����ɖ�O�Y�x�Ȃǂ������钸��́A��������̐l�B�����ƏW���ʐ^���Ƃ��āA�e�X�ꏊ���݂��Ē��H���ς܂���O�Y�����B�r���̃r���[�X�|�b�g�Ŗ]�x�m�R�����܂�ɂ����ꂢ�Ŏʐ^�Ƀp�`���B

�����R���病�����R��]��

�����R����̏G��x�m
�p�m���}��Ńg�C���x�e��A������̓W�]��ӂ�ɉׂ��f�|����O�Y�x�����B
�̊K�i��o��A��̊Ԃ����蔲���Ō���o���Ƒ傫�Ȉꖇ��̎R���ɁB
�̊K�i��o��A��̊Ԃ����蔲���Ō���o���Ƒ傫�Ȉꖇ��̎R���ɁB

�ׂ��f�|���Ė�O�Y�x��

�傫�Ȉꖇ��̖�O�Y�x�R��
��͉����ŁA�b���x�����A���v�X�A�x�m�R�܂ő����f���炵�����߂ɁA��̏�ɗ��F����A�|����Y��đ労���B

��O�Y�x����]�ށ@��A���v�X�@�b���x��P���O�R

��O�Y�x����]�ށ@�\��i�r��_���j�@�����ɋ���R

��p�m���}�̓W�]�ɂ���������
�����Ղ�W�]���y����Ńp�m���}��ɖ߂�A���R�̓��[�v�E�F�C�𗘗p�A�~�藧������M��w�ʼn��U����B
������菸�勬���y���ސl�A���߂̃o�X�Ɠ��}�ɏ�Ԃ���l�ȂǁA���ꂼ��̃y�[�X�ŋA�H�ɂ����B
������菸�勬���y���ސl�A���߂̃o�X�Ɠ��}�ɏ�Ԃ���l�ȂǁA���ꂼ��̃y�[�X�ŋA�H�ɂ����B

���勬�@��M��i���j�@�@�@�@�@�@�@���̏�������̕��i
�g�t�ɂ͏��������������V��Ɍb�܂�A�f���炵���i�F�����\���邱�Ƃ��ł����B
�������R�[�X
���勬���c�O���m��1�c����c�����R �c�p�m���}��c�W�]��c��O�Y�x�c�p�m���}��w
�`���[�v�E�F�C�ʼn��R�@�@��M��w���U
�`���[�v�E�F�C�ʼn��R�@�@��M��w���U
�Q����13�� ��4����25���i�x�e�܁j
���F�� 2057m
2024�N10��12���i�y�j
�V��F����
�V��F����
����Ɖ����B���N�̎R�s�́A���V�C�Ɍb�܂�Ȃ����Ƃ������������A���̓��́A�����Ȃ���D�̓o�R���a�B��7��40���A�b���a�w�ɂ��ꂼ��W���B�o�R�q�������A�A�N�Z�X�̃o�X�͑�������A�\����30����������쓻�ɓ��������B
�����𐮂���ǂɕ����ꃍ�b�W�����q�O���y���ɃX�^�[�g�B

����쓻���픭�@�܂��͕�����Ɍ���
30���قǂŕ�����O�ɓ����B�x�e�����āA���������̋}�o��o��B�Ԃ����Ȃ����A�^���ԂȎ��������}���V�O�T���A�l�ڂ������B�����ɂ��A���傤�Ǖx�m�R�ɉ_��������A�U��Ԃ��Ă��x�m�R�͌����Ȃ����A�R���݂ɕ����ԉ_���������B

������O�ň�x��

����������o��
1���ԗ]�肩�����Ď�Ő���̗���ɁB���߂��ǍD�B�ʐ^�^�C���̋x�e��A���F������B�����ŃJ���V�J�ɑ����B�l�̋C�z�ɂ��т��邱�ƂȂ��A�I�X�Ƒ���H�ׂĂ����B

�Ő���̗���ɓ���

���F��R���W���@�@�@�@�@�@�@�t�߂ő��������J���V�J
���F��R���͎��т̒��Œ��߂��Ȃ��A�ʐ^���B���đ��X�ɗ���Ɉ����Ԃ��A���H�x�e�B�c�O�Ȃ���A�x�m�R�́A���̂����肪���������邾���B����ł��ቺ�ɍL����i�F�́A�f���炵���B�������͐l�C�̎R���B

����ɖ߂�@���H�@�@�x�m�R�͉_�ŎՂ��Ă���
����́A���F���ցB�����`���̓��������܂Ō��n���ċC�������悢�B�R�[�X�Ɋ�������A�T�d�ɒʉ߂���B

���₩���Ő����̉͌��Ɍ����ĉ���

�O���̈ƕ��������������̉͌�

�̉͌�����]�ޑ��F������

���F������
�̉͌��i�����F���j���o�ĉ�R���������F���ɗ\���葁���������B
��́A��������o�ďo���_�ɖ߂邾�����B

���F������
�攭�g����������߂���ƁA�Ȃ�ƌ㔭�g�����̗ѓ����D�u�ƕ����p������B�u�������̂ق����悩�����v�ƁA�R��������攭�g����́A�{���L�̐����B

���R�H
����쓻�o�X��ɂ͌㔭�g���撅�A�܂��Ȃ��攭�g���������Ė����R�s���I���B
�A�H�̃o�X���Վ��ւŁA������Ԃ��邱�Ƃ��ł����B
�A�H�̃o�X���Վ��ւŁA������Ԃ��邱�Ƃ��ł����B
�������R�[�X
����쓻�c������c����c���F��c����c�̉͌��c�e�s�m�̓��c.���F���i��R���j�c������c����쓻�o�X��
�Q����17�� ��4����50���i�x�e�܁j