TOPICS
2020年
筑波山 1月

杉の巨木が立ち並ぶ
御幸ヶ原登山道
御幸ヶ原登山道

ガマの油売りの口上
金剛ノ滝・今熊山
2019/12
2019/12

最初に訪れた広徳寺境内の木の葉の裏に祈願が書かれていた

フユイチゴ(冬苺 )バラ科
この時期低山でよく見かける

イワタバコ(岩煙草)の葉
イワタバコ科
金剛の滝の周りの岩に自生
イワタバコの花は
夏に咲きます
夏に咲きます

7月の高尾山で
赤ぼっこ 11月

ヤブコウジ(藪柑子)
サクラソウ科
サクラソウ科
別名、十両(ジュウリョウ)

ミヤマシキミ(深山樒)
ミカン科
ミカン科
大岳山 10月

シロヨメナ(白嫁菜)
キク科

アキノキリンソウ
(秋の麒麟草) キク科

リンドウ (竜胆)
リンドウ科

カメハヒキオコシ
(亀葉引起し) シソ科

マムシグサ(蝮草)の実
サトイモ科 有毒植物

ツルシキミ (蔓樒) の実
ミカン科 有毒植物
ミカン科 有毒植物
雁ガ腹摺山 9月

ウスユキソウ(薄雪草)
キク科

ノハラアザミ(野原薊)
キク科
蝶はシジミチョウ
キク科
蝶はシジミチョウ

アキノキリンソウ
(秋の麒麟草) キク科

ノコギリソウ(鋸草)
キク科

マスタケ?
日向山 8月

登りでニホンザルに遭遇

キバナノヤマオダマキ
(黄花ノ山苧環) キンポウゲ科

タマガワホトトギス
(玉川杜鵑草) ユリ科

キノコ 名?
要害山 536m
2022年3月19日(土)
天候:晴れのち曇り
金曜、土曜と雨の予報で心配をしていたが、家を出るときは雨は上がり、眩しい朝日の中を集合場所に向かった。高尾駅8時2分発の列車は少し遅れたが、バスには間に合い車中からは丸い形の要害山がよく見える。
尾続バス停で下車し、甲府から移築された「甲府き典館」の門を見て、山道にかかる。
高度を上げると上野原の町並みが見え、左手には富士山を望むことが出来た。広葉樹の下を尾続山、コースの最高点実成山(609m)と歩き、眺望の良いコヤシロ山に着く。富士山を正面に眺めることが出来るのだが、雲に隠れて見ることができなかった。足元にはシュンランが咲いていた。ここから狭く急な下りとなり、ロープに気をつけながら間隔を取って歩く。鞍部から風の神様までの上りもロープがあり、ゆっくりと登る。木のかわいい祠があり360度の展望で談合坂SAがよく見える。狭い稜線を降り、登下への鞍部から少し登ると要害山に到着する。コブシの花が咲き始めていた。富士山は雲が掛かって残念だったが、眼下の街を眺めながら昼食をとる。
写真撮影後、途中サンシュユやスミレを見ながら下山する。建て直して綺麗になった山神社に参拝し民家の庭の梅や桜、ムシカリやスイセンを見ながら鏡渡橋に着き、解散する
尾続バス停で下車し、甲府から移築された「甲府き典館」の門を見て、山道にかかる。
高度を上げると上野原の町並みが見え、左手には富士山を望むことが出来た。広葉樹の下を尾続山、コースの最高点実成山(609m)と歩き、眺望の良いコヤシロ山に着く。富士山を正面に眺めることが出来るのだが、雲に隠れて見ることができなかった。足元にはシュンランが咲いていた。ここから狭く急な下りとなり、ロープに気をつけながら間隔を取って歩く。鞍部から風の神様までの上りもロープがあり、ゆっくりと登る。木のかわいい祠があり360度の展望で談合坂SAがよく見える。狭い稜線を降り、登下への鞍部から少し登ると要害山に到着する。コブシの花が咲き始めていた。富士山は雲が掛かって残念だったが、眼下の街を眺めながら昼食をとる。
写真撮影後、途中サンシュユやスミレを見ながら下山する。建て直して綺麗になった山神社に参拝し民家の庭の梅や桜、ムシカリやスイセンを見ながら鏡渡橋に着き、解散する



2022年2月19日(土)
天候:曇り
天気予報が曇り後雨とのこと。また、残雪の情報もありで少々心配な出だしでした。定刻8:30分集合 16名の参加者でしたので二班に別れて、一班はSサブリーダーを先頭に8名、二班はKサブリーダーを先頭に8名で出発しました。なお、準備体操は大垂水峠が狭いので各自で事前にお願いしました。出発してすぐ残雪があり注意しながら慎重に足を運び、5分後衣類調整(軽アイゼンを付ける人もあり)大洞山に着く・コンピラ山のリック掛けと・中澤山のスイセンに心なごみました。その後残雪も消え時々薄日がさす天気となりベンチ(見晴台)でアンパンタイム・津久井湖の一部が真下に見えました。
残念ながら富士山は見えませんでしたが、雪の大室山は大変美しく感動しました。途中,思いのほか多くの登山者とすれ違い、草戸山もほぼ満席の中で、昼食・写真撮影をしました。その後四辻まで、アップダウン、階段ありの思ったよりきつい山行でした。
下山時刻も、予定より早く(一班と二班10分差あり)楽しい山行でした。皆様のご協力に感謝いたします。
残念ながら富士山は見えませんでしたが、雪の大室山は大変美しく感動しました。途中,思いのほか多くの登山者とすれ違い、草戸山もほぼ満席の中で、昼食・写真撮影をしました。その後四辻まで、アップダウン、階段ありの思ったよりきつい山行でした。
下山時刻も、予定より早く(一班と二班10分差あり)楽しい山行でした。皆様のご協力に感謝いたします。




2021年11月30日(土)
天候:晴れ
天候:晴れ
禾生駅から登り田野倉駅へ下るコースを歩いた。
当日は、風もない快晴で、絶好のコンデション。新会員の方の紹介、九鬼山のコース説明の後、体操をし、2班に分かれて出発。最初の愛宕神社で衣類調整。先頭の班と間が開いたので、ゆっくり歩いた。すれ違いもほとんどない。富士山の見える天狗岩に寄り道する。素晴らしい眺望が広がていた。
九鬼山山頂でも展望を楽しみ、集合写真を撮り下山開始。最初の急坂の下りは一番の難所、ロープも有るが間隔を開けるよう、落ち葉の下の石が隠れているなどベテラン会員から次々的確な指示有り、慎重に安全に降りることができた。
紺屋の休み場で昼食、その後も慎重に歩き、林道を駅までのんびりした里歩きでした。
当日は、風もない快晴で、絶好のコンデション。新会員の方の紹介、九鬼山のコース説明の後、体操をし、2班に分かれて出発。最初の愛宕神社で衣類調整。先頭の班と間が開いたので、ゆっくり歩いた。すれ違いもほとんどない。富士山の見える天狗岩に寄り道する。素晴らしい眺望が広がていた。
九鬼山山頂でも展望を楽しみ、集合写真を撮り下山開始。最初の急坂の下りは一番の難所、ロープも有るが間隔を開けるよう、落ち葉の下の石が隠れているなどベテラン会員から次々的確な指示有り、慎重に安全に降りることができた。
紺屋の休み場で昼食、その後も慎重に歩き、林道を駅までのんびりした里歩きでした。

登録有形文化財 駒橋発電所 落合水路橋

水路橋をくぐり抜けて登山口へ

愛宕神社の鳥居前で衣類調整

天狗岩入り口で休憩

天狗岩から望む富士山

紺屋の休み場でゆっくり昼食

林道に下りてきました。駅までのんびり里山あるきです。
天気が良く富士山もバッチリ望めて素晴らしい山を楽しめた一日でした。
物見山 375.4m
2021年10月30日(土)
天候:晴れ
天候:晴れ
コロナ禍の緊急事態宣言で7月以来の会山行となった。
当初は健脚向けの本仁田山の予定だったが、より多くの会員が参加出来るように一般向けの山に変更し、7つの小ピークを超えて登る物見山にした。
7ピークを登る1班10名と観音岳と愛宕山は巻き道を行く2班6名の16名の大人数での山行になった、
武蔵横手駅を出発、林道を10分ほど歩き、バリルートに入る、長尾根山,五常山を経て、沢山峠で一旦合流した。班編成を確認し西大峰に登った後、2班は巻き道を通って北向地蔵で1班を待ったが、1班は愛宕山から鎌北湖方面にハプニングがあったが無事に合流。今度は2班が先行し、東ムカイ山、小瀬名富士を経て物見山に到着、5分後1班も到着。昼食、集合写真撮影後、1班先行で駒高へ出発、駒高から
バリルートを歩き、高麗駅には20分お差がついたが、同じ電車に乗れた。
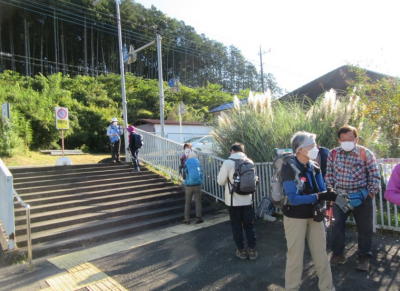
これから登山口に向かう。

途中に柚子の販売所があった。

キツイ上りです、頑張ろう!

2座目の五常山、写真を撮って行きます。

4座目観音岳 少し疲れましたか?

天気も良く遠くの山並みが綺麗に見えます。

こんな岩が鎮座してました。
物見山は人気の山だけに北向地蔵から駒高までは人数も多かったが、それ以外のバリルートは静かな
山歩きとなり、天気にも恵まれ楽しい山行きでした。
横瀬二子山 882.7m
2020年7月10日(土)
天候:晴れ
天候:晴れ
コロナ禍の緊急宣言が続き、半年ぶりの会山行となった。
ぎりぎりまん防下で決行可能というのに連日の雨予報、当日は車窓一杯に青空が広がり、参加者は久々の会山行に喜びを隠せない。
雌岳直下に滑り易い急斜面があり、雨続きで渋滞が予想されたので、第一班を脚の早い3名で出発、5分後に第二班6名が出発。山に入るとすぐ急登になり汗が噴き出す。下見の時には水の少なかった沢も音を立てて流れている。一時間程登った頃からそれぞれ自分のペースで登り、自然と間隔が空いて一時は三班に分かれた。尾根に出ると風が気持ち良い。一班は早くて姿も見えない。難所の急登はロープも有るが大勢が登り、滑ってツルツルドロドロなので、脇の斜面を慎重に登る。雌岳の手前を左に行き先に雄岳に登頂。一班と合流し昼食、武甲山が良く見える。後方と連絡を取ると雌岳で待つという。昼食後雄岳で合流、集合写真を撮って下山開始。直下の急な岩場を慎重に下る。浅間神社からは秩父市街、遠くもう一つの二子山も見える。電車の音が聞こえて来ても、まだまだ急な下りは続いて低山で時間は短くても、登りも下りも急な山です。解散後道の駅で地ビールやアイスクリームを楽しみ、帰路に着いた。

駅でリーダーより行程を聞いて出発です。

西武秩父線下のトンネルを通っていざ登山開始

急登の連続でひと休み、汗を拭く

二子山は武甲山が近くに見えます。

浅間神社まで降りて来ました。もう少しです、頑張ってね!

ここで登山終了します。ビール・アイスが待ってるよ!!

芦ヶ久保道の駅ここで解散です。お疲れ様でした。
解散後道の駅で地ビールやアイスクリームをめいめいが楽しみ、帰路に着いた。
丸 山 960.4m
2020年2月8日(土)
天候:快晴
天候:快晴
冬晴れの快晴、絶好の登山日和。奥武蔵の展望の山、丸山に登る。
芦ヶ久保駅下車、ら30分ほど車道を歩き赤谷から登山道に入る。大野峠までの山道は昨年の台風で倒木も多く、沢も崩れていた。車道と出合う大野峠をスルーして、尾根をたどる長い階段を一気に登りパラグライダーの飛び出し台(テイクオフポイント)のある展望地に。筑波山や榛名富士、遠く日光白根山?など遠くの山も望め感動する。
次のピークが丸山。頂上展望塔からは段々状に雪が積もった武甲山、西側にはギザギザの両神山などとお馴染みの山も見え、暖かいのでゆっくりと昼食と甘酒を楽しんだ。
下山は駅まで南東尾根を下る。日陰には3週間前の雪が凍って残る場所もあり、20m程を滑らないように慎重に降りる場面もあった。山里には梅も奇麗に咲く。舗装路となった下り道を、三々五々お喋りをしながらのんびりと歩き、芦ヶ久保駅前で解散した。
次のピークが丸山。頂上展望塔からは段々状に雪が積もった武甲山、西側にはギザギザの両神山などとお馴染みの山も見え、暖かいのでゆっくりと昼食と甘酒を楽しんだ。
下山は駅まで南東尾根を下る。日陰には3週間前の雪が凍って残る場所もあり、20m程を滑らないように慎重に降りる場面もあった。山里には梅も奇麗に咲く。舗装路となった下り道を、三々五々お喋りをしながらのんびりと歩き、芦ヶ久保駅前で解散した。

出発前、リーダーから今日の行程を聞く

赤谷からの登山道 昨年の台風で倒木も多く沢も崩れている

樹林の中で立ち休み ホット一息

パラグライダーのテイクオフ点がある展望地

先月登った筑波山 靄がかかっているが見えていた

丸山山頂の展望塔 武甲山・両神山・筑波山など眺望を楽む

丸山からの武甲山

山頂での昼食タイム

昼食後のお楽しみ コーヒータイム

雪が凍って歩きにくい 東尾根コースの下り

今回参加の皆さん
近くの山で冬の一日を楽しみました。昼食後のお楽しみ甘酒タイム(、たいへん美味しかったです。
係の方ありがとうございました。
筑波山 877m
2020年1月18日(土)
天候:曇り・小雪
天候:曇り・小雪
天気は朝からどんより曇り、時々小雨がちらつく中、大型バスに23名乗り込み令和2年初の山行。
久しぶりに会う会員も多い。筑波山神社前に乗り付け、まずは今年一年の安全登山を神社に祈願。
ラジオ体操の後いよいよ御幸ヶ原コースを登り始める。杉の巨木の間の登山道を進む。バスケットボール部などの学生の団体にどんどん抜かれるが、こちらはマイペースでうっすらと雪が積もる登山道を慎重に進む。
2時間ほどで開けた御幸ヶ原に出て、すぐ男体山御本殿に登る。遠くは見れないが麓は結構よく見える。
風が強く気温も低いため、会員が便宜を図ってくれ、お茶屋さんで弁当を食べることができた。ありがたい。
紫峰杉、男女川源流を見た後、女体山へ。雪が付いた岩の上を歩き山頂到着。安全のため崖の近くは立ち入り禁止になっていた。下山はここからつつじヶ丘駅まで歩く予定であったが、雪がついた大きな岩の登山道を下らねばならず、危険なため全員ロープウエーで下山した。帰路の途中入浴し、早めに西東京に帰った。
久しぶりに会う会員も多い。筑波山神社前に乗り付け、まずは今年一年の安全登山を神社に祈願。
ラジオ体操の後いよいよ御幸ヶ原コースを登り始める。杉の巨木の間の登山道を進む。バスケットボール部などの学生の団体にどんどん抜かれるが、こちらはマイペースでうっすらと雪が積もる登山道を慎重に進む。
2時間ほどで開けた御幸ヶ原に出て、すぐ男体山御本殿に登る。遠くは見れないが麓は結構よく見える。
風が強く気温も低いため、会員が便宜を図ってくれ、お茶屋さんで弁当を食べることができた。ありがたい。
紫峰杉、男女川源流を見た後、女体山へ。雪が付いた岩の上を歩き山頂到着。安全のため崖の近くは立ち入り禁止になっていた。下山はここからつつじヶ丘駅まで歩く予定であったが、雪がついた大きな岩の登山道を下らねばならず、危険なため全員ロープウエーで下山した。帰路の途中入浴し、早めに西東京に帰った。

筑波山神社

御幸ヶ原コースを登る

うっすらと雪をかぶった登山道

男体山への登り

男体山山頂

御幸ヶ原のお茶屋、ここで昼食

紫峰(しほう)杉
筑波山の雅称である紫峰から名づけられたという
筑波山の雅称である紫峰から名づけられたという

男女川源流
生水ですので「手洗い場」としてご利用ください と記されている
生水ですので「手洗い場」としてご利用ください と記されている

女体山山頂、この先立ち入り禁止

立ち入り禁止の柵の先はこんな感じ お〜怖!!

つつじヶ丘まではロープウエーに乗る
天気には恵まれなかったが、ベテラン会員による筑波山の歴史、逸話の説明を受け、改めて筑波山の魅力を認識した山行であった。やはり快適なバスでの山行は面倒がなく楽しい。
金剛の滝・今熊山 505m
2019年12月7日(土)
天候:曇り
天候:曇り
数日前の天気予報では雪のマークが出ていて心配したが、何とか一日曇りの予報になった。
武蔵五日市の駅に集合し、まずは広徳寺に向かう。広徳寺は臨済宗建長寺派の古刹で1373に創建されたとのこと。山門にも風格がある。山門をくぐると大銀杏があり、その大きさに驚かされる。寺の裏手からは武蔵五日市の市街を眺めることができる。しばらく歩くといよいよ金剛の滝の分岐が現れ、降りていくと先の台風・大雨で川が土砂、石で埋まり、石の上を歩いて滝まで行くことができた。雌滝は落差4メートルで右に手彫りのトンネルがあり、そのトンネルをくぐると雄滝に行けるようになっている。雄滝は落差18メールある。中ほどの左側に不動明王の像が祀られている。行ったん分岐まで戻り今熊山を目指して登り始める。山頂手前は結構な勾配で、汗をかくアルバイトを強いられた。山頂には今熊神社の奥宮があり、前は広場になっておりテーブル椅子もあって、ゆっくり昼食をとることが来た。この辺りはまだ紅葉が残っており、黄色、赤のグラデーションのモミジを楽しむことができた。下山口からはバスで駅まで戻った。
武蔵五日市の駅に集合し、まずは広徳寺に向かう。広徳寺は臨済宗建長寺派の古刹で1373に創建されたとのこと。山門にも風格がある。山門をくぐると大銀杏があり、その大きさに驚かされる。寺の裏手からは武蔵五日市の市街を眺めることができる。しばらく歩くといよいよ金剛の滝の分岐が現れ、降りていくと先の台風・大雨で川が土砂、石で埋まり、石の上を歩いて滝まで行くことができた。雌滝は落差4メートルで右に手彫りのトンネルがあり、そのトンネルをくぐると雄滝に行けるようになっている。雄滝は落差18メールある。中ほどの左側に不動明王の像が祀られている。行ったん分岐まで戻り今熊山を目指して登り始める。山頂手前は結構な勾配で、汗をかくアルバイトを強いられた。山頂には今熊神社の奥宮があり、前は広場になっておりテーブル椅子もあって、ゆっくり昼食をとることが来た。この辺りはまだ紅葉が残っており、黄色、赤のグラデーションのモミジを楽しむことができた。下山口からはバスで駅まで戻った。

五日市街道から広徳寺に向かう

広徳寺の古刹らしい山門

雌滝の前で 右に手彫りの雄滝に続くトンネルが見える

雄滝へのトンネルをくぐる

落差18メールトルの雄滝

今熊山山頂の奥の院

山頂広場

まだ紅葉を楽しめた

山頂からの眺め
この時期は日も短く、近くの低山に行くことが多いが、このコースは古刹、滝、展望の良い山と盛りだくさんで、冬の一日を過ごすには大変良いところでした。
山行後は山行会の忘年会が地元であり、山行に来られなかった方も多数参加し楽しい時を過ごした。
奥多摩 赤ぼっこ 409.8m
2019年11月16日(土)
天候:晴れ
天候:晴れ
今年は台風、大雨の被害が我らが愛する山々にも及び、残念ながら10月、11月初めに予定されていた山行が登山道崩落、道路の通行止め等で中止になってしまった。今回の山行は青梅市街の南に位置する要害山、天狗岩、赤ぼっこを巡るコースで奥多摩の山々、青梅市街の眺望が楽しめるハイキングコースである。
稲荷神社に参拝した後梅ヶ谷峠入り口から登り始めるとすぐに林道が崩落しているところがあり、車が通れなくなっていた。こんなところにも台風の影響があったのだ。笹薮、杉林を一時間ほど登ると尾根に出た。尾根道をしばらく行くと天狗岩との分岐。天狗岩は南に突き出た岩場で、大岳山、日出山、青梅市街の展望が素晴らしい。赤ぼっこも尾根から外れたところにあり、杉の木が一本立っているだけで見晴らしの良いちょっとした広場。ここで昼食。雲一つない快晴無風で遠く都心のビル群も見え、素晴らしい眺望を楽しみながらの昼食休憩となった。するとマウンテンバイクに乗った一団がやってきた。こんな山道を自転車で登ってくるなんて、すごいものだ。下山は馬引沢峠、旧二ッ塚峠を経由して青梅駅まで。駅近くではお祭りの最中であった。

宮の平駅前を、いざ出発

尾根道を行く

尾根にはススキがあり晩秋の風情を感じさせた

天狗岩からの眺望、大岳山から日出山、青梅市街

天狗岩にて

望遠レンズでとらえた大岳山(一番左)、日出山(一番右)

赤ぼっこ

展望の赤ぼっこ頂で昼食

旧二ツ塚峠で休憩
今回のルートはある程度アップダウンもあり、展望もよく、整備された良いコースであった。
家族連れでもお勧めである。(完)
家族連れでもお勧めである。(完)
大岳山 1266.5m
2019年10月5日(土)
天候:晴れ
天候:晴れ
6月8日雨で中止した大岳山の再挑戦は、明日から天気も下り坂と言う貴重な好天の一日で実現した。
武蔵五日市駅発の藤倉行きのバスは本数が少なく、指定のバスにみんな乗れるか危惧したが、その心配は無用であった。白倉バス停に13名が降り立つ。大岳神社で準備体操を済ませ少し先の登山口から山道入る。馬頭刈分岐まで樹林の中を時折り見える富士の姿に励まされ、休憩を入れながらひたすら登る。
尾根に出ると道は平坦になり大岳山山頂への巻き道を行く。一部危険な箇所もあったが無事通過。鋸尾根分岐に来ると多くの登山者が大岳山山頂へ向かい、山頂は鋸尾根縦走路から来る人も加わり結構な賑わい。山頂での富士山は半分しか見えないが多くの人が休んでいて昼食とする。
食後岩場の下りを注意して降りる。登り来る人も多くここも時間がかかる。岩尾根を通過するも相変わらず人の交差が多い。天狗の腰掛け杉に着いたのは15時過ぎ。この先は神苑の森を20分ほどで抜け御岳山の随身門に到着。ここで解散としケーブル山頂駅に向かった。
武蔵五日市駅発の藤倉行きのバスは本数が少なく、指定のバスにみんな乗れるか危惧したが、その心配は無用であった。白倉バス停に13名が降り立つ。大岳神社で準備体操を済ませ少し先の登山口から山道入る。馬頭刈分岐まで樹林の中を時折り見える富士の姿に励まされ、休憩を入れながらひたすら登る。
尾根に出ると道は平坦になり大岳山山頂への巻き道を行く。一部危険な箇所もあったが無事通過。鋸尾根分岐に来ると多くの登山者が大岳山山頂へ向かい、山頂は鋸尾根縦走路から来る人も加わり結構な賑わい。山頂での富士山は半分しか見えないが多くの人が休んでいて昼食とする。
食後岩場の下りを注意して降りる。登り来る人も多くここも時間がかかる。岩尾根を通過するも相変わらず人の交差が多い。天狗の腰掛け杉に着いたのは15時過ぎ。この先は神苑の森を20分ほどで抜け御岳山の随身門に到着。ここで解散としケーブル山頂駅に向かった。

白倉バス停で下車

まずは大岳神社に参拝

登山道は樹林帯を登る

馬頭刈分岐でコースをチェック

時折り見えた富士山

鋸尾根分岐

大岳山へ向けて急登

賑わう大岳山山頂

天狗の腰掛け杉
今年は雨が多く、いったん中止になった山行であったが、この日は天気に恵まれ、秋の花々が登山道を彩り素晴らしい山行であった。 (完)
南大菩薩連嶺 雁ガ腹摺山 1874m
2019年9月28日(土)
天候:晴れのち曇り
天候:晴れのち曇り
雁ガ腹摺山と聞くとすぐ思い浮かべるのが旧500円札の裏に印刷された富士山の撮影地であるということだ。ただこの山の名前を知っているが意外と登った人は少ないのではないか。その理由は最寄りの駅からのアクセスの悪さである。バスは途中までしか通っておらず、ほとんどはマイカーを大峠に止めてピストンである。
今回はタクシーで大峠まで入り、下山口の金山鉱泉からもタクシーを使い、雁が腹を摺った尾根道を山頂から下った。
今回はタクシーで大峠まで入り、下山口の金山鉱泉からもタクシーを使い、雁が腹を摺った尾根道を山頂から下った。
大峠は富士山方向に開けており、すでに旧500円札の富士山の端正な裾野を見せていた。ここから山頂まではコースタイム1時間の登りである。ミズナラなどの樹林帯を進むと一気に開けた草原の斜面が現れ、その一番上が山頂である。すでに何組かの先客がおり、集合写真のシャッターを押してもらった。富士山を背景に入れるため、逆光での撮影になったのでフラッシュを使った。山頂までは快適な登りで、肝心の富士山は山頂に雲がかかっているもののその裾野の美しさは秀逸であった。
下りは結構な勾配のコースタイム3時間10分の尾根道を延々と歩いた。ところどころに大きな岩が転がり、大木が倒れていたり、大きなキノコがあったり、秋の花もいろいろ咲いており、変化があってそれなりに楽しかった。
下りは結構な勾配のコースタイム3時間10分の尾根道を延々と歩いた。ところどころに大きな岩が転がり、大木が倒れていたり、大きなキノコがあったり、秋の花もいろいろ咲いており、変化があってそれなりに楽しかった。

大峠からの富士山の眺望 この時だけ山頂の雲が取れた

「熊出没注意」の看板が立つ登山口

渓流にかかる橋を渡り樹林帯を進む 雰囲気良し!

ところどころに奇岩がある これもその一つ 「足洗石」

雁ガ腹摺山山頂に至る草原を行く

山頂より富士山を望む 冨士山頂付近は雲に隠れていた

記念写真 ハイポーズ

倒木が多い急傾斜を下る

ようやく昼食 この後も長くて急な下りであった
「雁ガ腹摺山」 名前をよく聞くが行ったことがない山の一つだろう。とても一人ではいけない。山行会ならではであろう。みんなで行けば熊も道を譲る。そんな山行であった。 (完)
南アルプス前衛 日向山 1660m
2019年8月3日(土)
天候:晴れ
天候:晴れ
夏休み初めての週末で、天気も良く高速道路の渋滞を心配したが、予定通り道の駅「はくしゅう」に到着。
矢立石登山口まではジャンボタクシーを使った。登山道はよく整備されており、家族連れも多い。先月登った北アルプス蝶ヶ岳とは標高も気温も大違いだ。カラマツ林が美しい。約2時間で8年目にして念願の登頂。
過去何回か挑戦したがすべて天候が悪く登頂できていなかった。雁が原はまるで真っ白なビーチ。風化した花崗岩が砂になり、前方は切れ落ちて蟻地獄のようで、谷底に吸い込まれそうだ。
周辺を少し散策するが遠く雷鳴も聞こえてきたので、昼食後すぐに下山した。
矢立石登山口まではジャンボタクシーを使った。登山道はよく整備されており、家族連れも多い。先月登った北アルプス蝶ヶ岳とは標高も気温も大違いだ。カラマツ林が美しい。約2時間で8年目にして念願の登頂。
過去何回か挑戦したがすべて天候が悪く登頂できていなかった。雁が原はまるで真っ白なビーチ。風化した花崗岩が砂になり、前方は切れ落ちて蟻地獄のようで、谷底に吸い込まれそうだ。
周辺を少し散策するが遠く雷鳴も聞こえてきたので、昼食後すぐに下山した。

盛夏の山行の為尾白川駐車場から矢立石登山口までジャンボタクシーに乗る

矢立石登山口

カラマツ林の緑の中を登る

日向山三角点(1659.9m)にタッチ 雁ヶ原はここから少し先だ

花崗岩砂礫の雁ヶ原に飛び出す

雁ヶ原 西側は切れ落ちている

雁ヶ原 花崗岩と白砂の景観 右上部が最高地点

無事、矢立石に下山
8年越しでやっと登れた日向山。
残念ながら甲斐駒や八ヶ岳はもやって見えなかったが、次回に期待しよう。 (完)