|
理想的な町の大きさ 『U字説』というのがあるそうです。 『なんだ、この小学生が書いたような、幼稚でいい加減なグラフは』 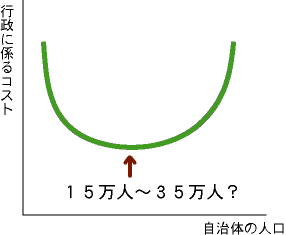 縦軸は行政に係るコスト、横軸は自治体の人口規模です。自治体の人口が増えて行くに従って、行政の効率化が図られて、コストが安く上がるようになります。 つまり行政の単位は、やたら大きければ良いというわけではなく、最も効率的に行政運営ができる理想的な町の大きさ、というのがあるようなのです。じゃあ、その理想的な町の大きさは人口何人かと言うと、これもいろんな学説や計算の仕方でまちまちみたいで、ある説は『15万〜20万』と言うし、ある説は『30万〜35万』と言ってます。 ただ、町は何も効率だけを優先して形を決めればいいというものではありません。町は利益追求の組織ではなく、弱者の救済であるとか、公的な使命も担っています。また『小さい町が好きな理由』で書きましたが、政治の自浄能力を望めば、人口15万でも多すぎるのです。 だからこの『U字説』、あまりに大都市だけを念頭に置いた、あまりにも概念的な説で、たとえこの説が正しくても、『だから理想的な町の大きさは人口15〜35万人だ』とは言えないのですが、一方、『町はでかけりゃ効率化できるというもんじゃない』という主張には使えそうですね。 この説で行くと、人口62万人の相模原市は、行政の効率化を求めようと思えば、町を2つか3つに分割すれば良いと言う話にもなります。 |