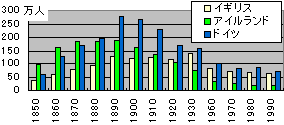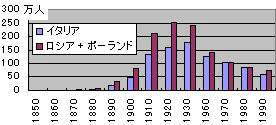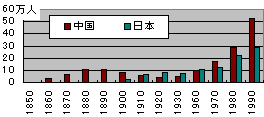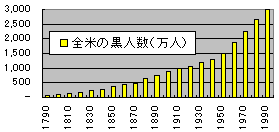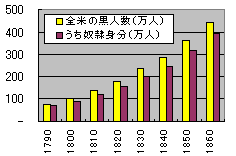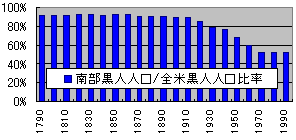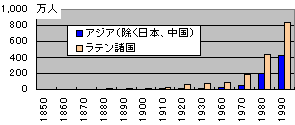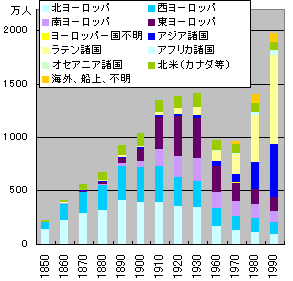「自由の女神」の台座に刻まれた、「エンマ・ラザルス」(Emma Lazarus)が詠んだ詩「New Colossus」の一部です(田原正三氏訳)。擬人化された「女神」が、世界中の貧しい、自由を求めている人々を、アメリカに呼び寄せているという内容ですよね。自由の女神がそびえるリバティ島の隣には、移民の玄関口=移民事務所があった「エリス島」。 「イースト・ビレッジ」を含むマンハッタン島東側は、アメリカ移民たちがいったん住まいとした「ローワー・イースト・サイド」とよばれたエリア。「イースト・ビレッジ」は、19世紀半ばにはドイツ人移民の住居でした。 「自由の女神」が、1885年に現在のリバティー島にその姿を現すはるかに前から、北米大陸に招きよせていた移民たちの大きな流れは大別して、四つの「移民時代」、そして「国内移動」時代があります。
<「植民」時代−独立獲得(1783)以前> 現在のアメリカ合衆国の母体は、イギリスの旧植民地であった東海岸でしたので、当然ですが「イギリス系」の移民が非常に多い。 また宗教的な避難が多かったのも特徴です。 バージニア植民地を核とする南部は「英国教徒」中心でしたが、マサチューセッツ植民地を中心と州は英本土での圧力から避難してきた「清教徒」。 例外としては、「ペンシルバニア」(創設者ウィリアム・ペンが名称の由来)は「クエーカー教徒」、そして「メリーランド」(メリー=聖母マリアが名称の由来)は「カソリック教徒」(創設者バルティモア卿がカソリック)、と英本土から宗教的に避難してきた人々が建設した植民地でしたが、両方とも「信仰の自由」があったようです。 他の民族で、少数なものの、宗教的理由で、アメリカそしてNY近郊に渡来した有名な移民グループは、 「フランス系ユグノー」と「スペイン/ポルトガル系ユダヤ人」。 前者は、フランスのルイ十四世による、1685年「ナント勅令廃止」=カソリック強制、により圧迫されたカルバン派のプロテスタントで、いったんはオランダに亡命し、1689年初渡米。 後者は、「ポルトガル/スペイン」のカソリック圧力により、1492年にまずはオランダへ亡命。その一部が、南米のオランダ植民地へと1633年に渡りますが、ポルトガルが侵攻してきたため、1654年に、ニュー・アムステルダムであった現NYへと、27人が亡命してきました。 NYでは1614年にハドソン川の中流に「ニュー・ネーデルランド」(現在のオルバニー)に、そして1626年マンハッタンに、「オランダ系」の人々が入植してきました。彼らの中には、1664年のイギリスによるNY占領、そして独立戦争を経ても「名家」として続く家系があり、その一つが、「セオドア」そして「フランクリン」の二人の大統領を輩出した、「ルーズベルト」一族です。 (移民空白の時代−欧州の混乱、第二次英米戦争)
アメリカは国外中立を取っていましたが、英、仏、ともにアメリカを味方につけようと画策しつつ、大西洋では海上封鎖が行われます。 特にフランス革命政府から派遣された特使は、アメリカ政府を反英行動へと向かわせようとしましたが失敗、その後アメリカの民衆に反英蜂起を扇動したりしまして、1798年に帰化法が改正され、「危険人物」の追放を可能とし、必要居住年数を14年としました。 しかし1802年に再度改正され、必要最低居住年数は5年となり、それは現在まで続いています。 中立していたアメリカも欧州の混乱に巻き込まれ、1812年にイギリスに宣戦しカナダ英植民地に侵攻しますが撃退され、以降はイギリスの攻撃にされされましたが1815年に終戦。ようやく、アメリカがヨーロッパから移民を受け入れる時代が訪れました。 <「旧移民」時代−「北欧系」「西欧系」: 「農業移民」と「インフラ工事移民」(1820年頃−80年頃)>
一方、東海岸に留まった移民たちは、商工業に従事するか、NY州の「エリー運河」(1825年開通)を筆頭として、「鉄道」などのインフラ整備工事で職を得ていたようです。 都市部であるNYに残ったドイツ系移民は商工業に、アイルランド系移民は鉄道建設などの準公共事業の職に就いていました。 さて1850年以降について、参考データを「アメリカ国勢調査局」のサイトで見つけることができました。 10年毎に行われる「国勢調査」(census)中の、1850-1930年、そして1960-90年の「外国生まれ」(foreign-born)人口の全米データです。そこから抽出した数字を、fujiyanがグラフ化したものを以下、順次お届けします。まずは、「北欧」系代表の「アイルランド系」、「西欧」系代表の「ドイツ系」、そして「イギリス系」を添えてみたグラフをご覧下さい。 このデータは「フロー」=その年の「帰化数」ではなく、「ストック」=その年の「住民人口数」です。 つまり新たに市民権を得た人々の「積算」。棒グラフの、前年と比した「増加部分」は、 ・「新たに帰化した人数」−「死亡した人数」−「帰化したもののその後アメリカから去った人数」 ということになり、増加部分が「フロー」を示している、ということになりますね。 調査が10年刻みであることも考えると、実際に渡米してからこのデータに参入されるためには、5年から10年程度の「ラグ」があることになります。
上述の「ラグ」を合わせて考えると、1840-50年代の渡米者数は非常に大きく、60年前後からやや鈍化し、70-80年代には「アイルランド生まれ」の「米市民の死亡者数」 +「アメリカから他国へ移住した人数」と同程度の移民数となり、その後アイルランドからの移民数は激減していく、というわけですね。 一方、ドイツ系移民は、1840年頃から移民数が増加し始めるのはアイルランド系と同様。しかし、人口数がピークとなるのは1890年でその後は激減。データのラグを考えると、移民のピークは1870年代から80年代頃ですね。これは、鉄血宰相ビスマルク率いるプロシアが、フランスを普仏戦争で破り、フランス傘下にあった南ドイツの諸法を統合、ドイツ帝国が1871年に成立、混乱した南ドイツから移民が増加したためでしょう。
<「新移民」時代−「東欧系」「南欧系」: 「農業移民」終了、低賃金労働者としての移民(1880年頃−1920年頃)>
また、1890年頃、西方への領土拡大、いわゆる「フロンティア」も消滅し、新たな農業地獲得も終わり、基本的に「農業」移民は終了します。
グラフには、「南欧」代表として「イタリア」系、「東欧」代表として「ロシア」と「ポーランド」を合算した数字を掲載しました。 グラフはどちらも1900年−20年にかけて急上昇。上述したデータの「ラグ」を考えますと、1880年代から1900年代にかけて大量に渡米したと推測できます。「旧移民世代」のグラフと比較していただきますと、ちょうど入れ替わっているように見えますよね。 「ロシア」と「ポーランド」を合わせた数字に、どの程度「ユダヤ系」が含まれているのかはということですが、ご承知の通り「ユダヤ系」とは国籍ではなく、信仰する「宗教」です。例えば、「旧移民世代」の「ドイツ系」の数字にも、少なからず「ユダヤ系」は入っています。 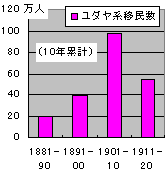 「Americans All.Com」に、「アメリカ移民局」を出所とした、1881年から1920年まで単年度刻みでのユダヤ系移民数データがありました。それを10年単位の累積にfujiyanが加工しグラフ化したものが右です。これは「外国生まれ」データが「累積」であるのとは相違して、入国した人数の「フロー」ですのでご注意ください。この当時は信仰する宗教を移民局がヒアリングしていたんですねぇ。1901-1910年までの10年間で、100万人が移民しています。 NYでは、「イタリア系」そして「ユダヤ系」の人々は、その頃勃興した「衣料産業」の低賃金・長時間労働に従事していたのが有名です。また「高架式鉄道」、「地下鉄」などの準公共工事などでも、働いていました。
<移民制限と、「国内移動」時代:1920年頃−1960年頃> (移民制限−出身国別、そして人種別の移民割当制度) 「自由の女神」が照らす、「黄金の扉」が閉じる時代が来ました。 「植民」時代と「旧移民」時代にアメリカに移民してきた、「北欧」系(イギリス系など、アイルランド系など)、「西欧」系(ドイツ系など)の人々は、急増する「新移民」系、つまり「東欧」系(ロシア、ポーランド、ユダヤ系)や「南欧」系(イタリア系など)が、自分たちが築き上げてきた「アメリカ的」な文化を破壊するのではないか、と恐れはじめました。
この「アメリカ的」なものを守るという大義名分をかざした移民規制は、「アジア系」には既に19世紀半ばから厳しく向けられていました。中国系は1848年のカルフォルニア・ゴールド・ラッシュのころからアメリカ西海岸に移民してきましたが、差別に遭い続け、1882年に「Chinese Exclusion Act」(直訳:中国人排斥法)で移民が不可能となります。 一方、日本人ですが、1868年からハワイ、そして一部はその後アメリカ本土西海岸へと移民してきましたが、「黄禍」として差別にあい、1907年日米政府間の「紳士協定」で法制化はしないものの、日本政府はハワイ以外にパスポートを発行せず、アメリカ政府はハワイから本土への日系移民の移動を認めない、ということになりました。 1924年上記の国籍別割当制度が強化された「Johnson-Reed Act」(ジョンソン・リード法)が成立。「出身国籍」ではなく、「人種」別データに応じて、移民数を配分し、対象をヨーロッパのみではなく全世界に広げるというもの。
日本を仮想敵国としたアメリカ、中国の同盟関係により、1943年に中国人排斥法は撤廃されたものの、中国系移民割当はわずか105名でした。 そのため、中国系、日系ともに、1960年代の移民法改正を待つことになります。
(「国内移動」時代−プエルトリコ系、そして南部黒人の「移動」) この移民制限の時代は、アメリカ国内移動の時代でもあります。fujiyanの推測に過ぎませんが、移民制限により、低賃金労働者の数が不足し、アメリカ国内でその種類の職に就く人々の移動が発生したものと思われます。 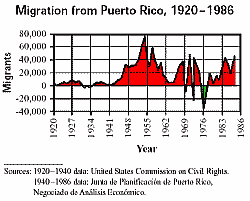 1898年の米西戦争の結果、スペインからプエルトリコがアメリカに割譲され、1917年にプエルトリコの人々はアメリカ市民権を得ました。従って、「プエルトリコ系」の人々がアメリカ本土に渡るのは「移民」(immigration)ではなく「移動」(migration)と言うわけです。 1898年の米西戦争の結果、スペインからプエルトリコがアメリカに割譲され、1917年にプエルトリコの人々はアメリカ市民権を得ました。従って、「プエルトリコ系」の人々がアメリカ本土に渡るのは「移民」(immigration)ではなく「移動」(migration)と言うわけです。人数ですが、「Americans All.Com」から、1920-86年までの、「移動数」のグラフがPDF方式でありましたので、コピーをしたものにfujiyanが色づけしたものをご案内します。このデータは「フロー」ですので、赤色部分の面積=累積が「純流出」、緑の面積がプエルトリコへのいわば「里帰り」と言うことが出来ますね。1960年代まではほとんど全員がNY市に居住したと言ってよいそうです。 一方、「黒人」系、正確には「アフリカン=アメリカン」系と呼ばれている人々は、大別して三種類。
・アフリカ大陸から自らの意思でアメリカ移民をした人々とその子孫。 ・アメリカ以外の旧英国植民地に奴隷として連れてこられてきた人々の子孫で、自らの意思でアメリカに移民してきた人々とその子孫。主として「ジャマイカ」。 最初の種類の人々が最大でありことは、想像がつきますね。さて、アメリカ国勢調査局からの、黒人関連データに基づき、黒人人口のグラフを掲載しました。
しかし「奴隷解放宣言」後もアメリカ南部に住んでいた黒人たちは、「黒人差別」が続いたにもかかわらず、南部の土地と気候を愛し、その地を離れたがらなかったそうです。しかし20世紀に入り彼らは南部を離れ、北部、西部の大都市へと移動します。これは、「Great Migration」(直訳:大移動)と呼ばれまして、1960年頃まで続きました。 黒人の地域別人口データもありましたので、それをグラフ化したものをご案内します。これは「南部の黒人人口」の、「全米の黒人人口」に対する比率の推移です。
1960年代は、黒人公民権運動の時代。 1963年に、マルティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師による、「I have a dream」スピーチが行われ、1964年に公民権法が成立したことを受けたと思われますが、1970年で南部の黒人比率は50%まで低下したのち、安定しています。
<「最新移民」時代:移民法の割当制度の改正 1960年頃−>
1965年の移民法改定により、全ての国に解放され、ヨーロッパなど「東半球」12万人、アジアなど「西半球」17万人となります。ここから、ヨーロッパ以外の国々からのアメリカ移民が増加していきます。 1975年には、地球の東西半球での割当が撤廃、1990年には年間移民数が70万人に引き上げられることになりました。 こうして1960年代以降、アメリカ移民は急増していきますが、その主軸は中国系のみならず「アジア系」、そして「ラテン系」の人々です。
アメリカ本土も含めた「旧イギリス植民地」出身の「黒人」、すなわち「アフリカン=アメリカン」との人種的な違いですが、旧イギリス植民地では白人と黒人の混血は、基本的に認められていませんでしたが、旧スペイン植民地では、白人、黒人そして現地人との混血が行われていたことにあります。 また「ラテン系」の母国語は「スペイン語」。 アメリカに移民してくるラテン系の人々は中米が多数で、その主軸は「メキシコ系」です。しかし彼らは、カルフォルニアなど西側に多く住んでおりまして、NYでの「最新移民」であるラテン系は、圧倒的に「ドミニカ系」の人々が多いようです。
最後に右のグラフで、「外国生まれ人口」の地域別人口と総計をご覧下さい。 しかし、NYにはもっと多くの国々からの移民たちとその子孫が住んでいます。その一部しか拙サイトではご紹介できていませんことを、お詫び申し上げる次第です。例えば、イタリア系移民と同世代である「南欧」の「ギリシャ系」の人々も大きな勢力ですが、ご紹介できていません。 さてアメリカへと移民してくる人々の理由は、二通りあると思います。 一つは、迫害、圧力からの避難。 ユダヤ系移民はその典型ですし、「植民」時代でご案内した「フランス系ユグノー」は、ルイ十四世の時代に全盛を迎えたフランス絶対中央集権体制の財政基盤を支えた知識、技術層であるにもかかわらず、母国を後にしなければなりませんでした。ちなみに、「ユグノー」はその知識、技術のためNYを始めとする北米イギリス植民地で暖かく迎えられ、特に当時の南部のサウス・カロライナ植民地では、地中海農産物の生産ノウハウの提供を期待され、熱狂的に迎えられたそうです。 もう一つは、経済的、というか職を求めた貧困からの脱出。 アメリカに移民してきた人々は、まずは低賃金の単純労働に就くのがほとんどでした。そして努力して、当人あるいは子、孫の代で、貧困から脱出し、教育を受けて「アメリカ化」していく。そして次世代の新しい移民が単純労働からスタートする、というという構図です。 貧困から脱出した人々とその子孫は、次世代の新しい移民に対して冷淡な場合が少なくなかったようです。自分たちあるいはその祖先が苦労してきたんだから、この程度の苦労は当然だ、というわけですね。体育会系のイジメに似ているかな(笑)。 「イタリア系」移民の添書きで触れましたが、同じカソリックである彼らに、先住の「アイルランド系」の人々が教会を貸さない、というのは、同じカソリックでもアイルランド系の儀式と、イタリア系の儀式が相違しているから、と一般的に説明されていますが、これは建前だったようです。アイルランド系としては、プロテスタントに攻撃され続けた苦難の歴史がオレ達にはあるんだ、甘えるんじゃない、悔しかったら自分たちで教会の一つでも建ててみろ、あるいは買ってみろ、というところとにらんでいます。 一方残念ながら貧困から脱出できなかった人々は、単純労働を奪われるあるいは賃金が上がらないとして、次世代の新しい移民に対して冷淡どころか憎悪を持ってしまう。特に民族的な相違があった場合はそれが増幅する。 「黒人系」は大部分が自発「移民」ではなく、奴隷として連れてこられた人々とその子孫ですが、彼らに対する、いわゆる「プアー・ホワイト」(poor white 貧困白人層)による憎悪の歴史は、ご承知の通りです。 また、「旧移民」時代の子孫たちである工場労働者が19世紀末頃にストライキを行うと、資本家がスト破りに使う代替労働者は「新移民」である「東欧系」の労働者でして、「旧移民」の子孫たちは「新移民」である「東欧系」に憎悪を持つ、特に「新移民」が「ユダヤ系」の場合には、宗教上も理由もあいまってそれが加速してしまうわけですね。 なんてことを、NY在住時に思っていましたが、日本に帰国してみて良く見たら、膨大な国、地方の借金で「箱物」「橋」「道路」を建設してその返済は「次世代」任せ、老齢年金も「次世代」から巻上げ「次世代」が老齢になったらおそらく年金は貰えない、不況になったらまずは新卒の若い人たちの採用を縮小、と、まあ「次世代」に冷淡なのは、「アメリカ移民史」とあまり相違がないことに気がつきました(苦笑)。 それとも、戦後60年間の歳月で、日本の考えが「アメリカ化」したのかもしれませんね(苦笑)。
|
| 「マンハッタンを歩く」 のメニューへ |
トップページへ |