![]()
新陰流と合気
日本伝では他の大東流とは違って、対比する剣術を新陰流に置いています。それは合気の原理が新陰流にあると考えているからです。全てが新陰流にあるという訳ではありませんが、「重心の合気」とでも言うべき理合いが新陰流の甲冑剣術の中にもあり、合気も同じ理合いを使っています。
甲冑剣術の場合、TVや映画の場面で誤解されがちですが、太刀で武者をバッタバッタと切り捨てるなどというのはあり得ません。武具で守られた部分にはまさしく「刃もたたず」、刃が滑っていってしまいます。傷つけるためには、道具外れを狙うか突くしか有効打はないわけです。
そのため鎧や具足に刀を打ちつけるのではなく、刀が触れたところから相手の重心を崩し、相手の体勢が崩れたところをついて切ったり突いたりする技術が必要でした。
新陰流では古い勢法の中にそれがあり、日本伝ではそれを合気の技術の一つとして考えています。そのためには自分と相手の重心を合わせ、自分の重心を操作することによって相手の重心を操作し、下に崩したり上にのけぞらせたりと、様々に相手を崩していくのです。
江戸期の「素肌剣術」は切ることが技術の大半であり、その系譜を引く現代剣道では想像も出来ないですが、戦国期の甲冑剣術は刀を切ったり突いたりするためだけの道具とは考えていませんでした。その技術を精緻なものにした新陰流では、刀を僅かに触れた状態から相手の重心を操作して、一瞬のうちに地面に叩きつけるようなことさえ可能にする方法を編み出していたのです。
それと同様な技術が大東流にもあり、いわゆる「触れ合気」の奥義として存在しています。
たとえば指先で触れるだけで相手をその場所で動けなくする。それは相手の重心を制御することによって、相手を「水平に落ち続ける」状態に追い込み、相手はそれを嫌って必死にその場に「居着き続けようとする」防御反射を引き出すことです。
あるいは二ヶ条を使って「相手の握った手を離さなくする」というような柔術的な「搦める」用法ではなく、自分が相手の小手に触れた指先を離れなくするのと同様な技術を使って、触れた木刀の先を離れなくして相手を自由自在に崩していき、最後には地面にはいつくばらせてしまうことも可能になるわけです。
これらの技術は文章化はもちろん、映像化も困難となります。それはどんなに至近距離で解説をしながら撮影しても、体内での重心操作などというのは撮影が不可能だからです。
そのためこの技術の公開は、主に講習会を通じて実際に触れて教えるという形を取らざるを得ませんでした。実際に触れることでしか、体の重心の合わせ(いわゆる「合気」のかかった状態)や、「胸骨の理」や「骨盤の理」においてどのように胸骨や骨盤を操作し、そのためにどの筋肉をどう使うかを、教えることが出来ませんでした。
柳生新陰流、日本伝合気柔術八景学院支部(共催)東京講習会(新陰流と合気)
1)日時:平成22年10月11日(月・祝日) 9:30〜16:30(午前の部 新陰流 午後の部 大東流)
2)場所: 中央区立総合スポーツセンター 地下武道場
午前の部 第2武道場(剣道場) 午後の部 第1武道場(柔道場)
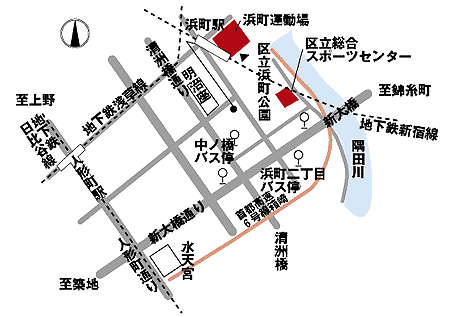
3)日本伝では他の大東流とは違って、対比する剣術を新陰流に置いています。それは合気の原理が新陰流にあると考えているからです。全てが新陰流にあるという訳ではありませんが、「重心の合気」とでも言うべき理合いが新陰流の甲冑剣術の中にもあり、合気も同じ理合いを使っています。
この講習会では、剣術と大東流を対比させることにより、合気の理合いを詳細に公開していきます。
4)講師:日本伝合気柔術金沢八景学院支部師範 岡本 眞
5)講習会費は8000円です(午前・午後の部のどちらかのみ参加の方は5000円です)
なお午前の部に参加される方は木刀・袋撓をご持参下さい。お持ちでない方は、申込み時にあらかじめお申し出下さい。