やってしまいました.....。以下の添書きは9800文字強です。いつもながら、長くてゴメンナサイ!!
また、まったくの素人ながら「寄り道:製鉄の方法」なるものを、2900文字の別ページで 作ってしまいました。重ねてゴメンナサイ!!(寄り道へのリンクは、本文中にもあります。) NYでは歴史的に、「大富豪」が居住し「フィランソロピーphilanthropy」と呼ばれる社会貢献を行ってきました。今回の「アッパー・イースト・サイド」散歩での「豪邸」達の中に、「鉄鋼王」アンドリュー・カーネギー(Andrew Carnegie 1835-1919)の「豪邸」が出てきましたが、彼は「起業家」であると同時に、「カーネギー・ホール」を設立するなど、「フィランソロピストphilanthropist」=「篤志家」として有名ですね。NYの「大富豪」の例として、彼の人生を見てみたいと思います。 こちらで「アメリカ大富豪」ランキングをご覧いただけます。"American Heritage"という雑誌の、1998年10月号のアメリカ人富豪ベスト40から、fujiyanが、5位までとそれ以下は抜粋したものです。円換算はfujiyanがしました。カーネギーは現在換算11.9兆円で、「石油王」ロックフェラーに次いで第二位。 第一位のロックフェラーは、後日ご紹介する予定。第三位バンダービルトは、「グランドセントラル・ターミナル駅」の前身を作った「鉄道王」で、第9位ジェイ・ゴウルドとの「エリー鉄道攻防戦」など、その経営人生は波乱に満ちていてfujiyanはどこかで書いてみたいんですが、出来るかどうか自信がありません(苦笑)。第四位ジョン・ジェイコブ・アスターは毛皮商人そしてNY「不動産王」。「マレーヒル散歩」でちょっと触れていますのでご興味のある方はご覧下さい。で、第五位は、ご存知マイクロソフト社ビル・ゲイツ。 ちなみに、27位の「ヘンリー・クレイ・フリック」(Henry Clay Frick 1849-1919)の「豪邸」も「アッパー・イースト・サイド」にありますが、彼はカーネギーの右腕となり、そしてカーネギーの人生を大きく左右することになります。また23位の「金融王」J.P.モルガン(1837-1913)も、この稿に登場します。 <アメリカ移民後「ペンシルバニア鉄道」勤務。「南北戦争」−北米「産業革命」の時代。> 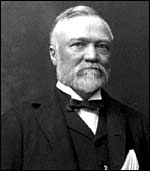 彼は1835年、手織職人の子として英国スコットランドの古都ダンファームリンに生まれました。しかし、産業革命の波が1847年スコットランドに押し寄せ蒸気機関による機械織が進むと、一家は貧困に喘ぐことになり、1848年に母の姉妹の住む、米国ピッツバーグへと移住しました。 彼は1835年、手織職人の子として英国スコットランドの古都ダンファームリンに生まれました。しかし、産業革命の波が1847年スコットランドに押し寄せ蒸気機関による機械織が進むと、一家は貧困に喘ぐことになり、1848年に母の姉妹の住む、米国ピッツバーグへと移住しました。翌1849年に電報配達人として働き始めますが、街の地理を頭の中に叩き込み迅速丁寧な配達をし、会社で認められすぐに電信オペレーターへと昇進しました。電報局のお客で、「ペンシルバニア鉄道」の西地区監督で、後に副社長、社長となる「トーマス・A・スコットThomas Alexander Scott(1823-81)」がカーネギーの能力を認め、1853年カーネギーを個人秘書兼電信オペレーターとしてスカウトします。以降彼の経営人生は、「ペンシルバニア鉄道」とともにありました。 スコットの元でバリバリと仕事をし、様々なアイデア−たとえば鉄道事故の後、事故車両を「燃やして」片づけやすくし、あっという間に運転再開させた−など、で認められ、1859年スコットが昇進した後の、ペンシルバニア鉄道の西地区監督の座を引き継ぎました。その間、父を1855年失い、二十歳にして一家を養っていくことになります。 1856年初めての「投資」を行いました。 「寝台列車」がこれから儲かる、と思ったカーネギーは銀行から借入れして「寝台列車会社」に出資。217.0ドルの投資が大成功、年間5,000ドルの収入につながり、これはサラリーの3倍だったとか。すでに将来儲かりそうな分野を見抜く、という「起業家」としての才能を見せはじめます。 さて「南北戦争」(1861-65)は開戦当初、アメリカ経済に深刻な影響を与えますが、北部アメリカでは、戦争中から「軍需景気」?とでも言いましょうか、「産業革命」が本格化します。 それを見抜いたカーネギーは開戦同年に、寝台列車会社への投資で儲けたお金を、まずは「石油」−ペンシルバニア州の油田地帯(Oil Region)に11,000ドル投資し、一年で17,868ドルの利益をあげました。 そして「鉄」ー「フリーダム製鉄」社を同年に創設しました。推測に過ぎませんが、この「フリーダム」=「自由」という点から、奴隷開放に繋がる南北戦争での北軍の勝利に貢献しよう(同時に「儲けよう」?(笑))、というカーネギーの意気込みが伝わってきますね。 一方北軍(Union Army)は、前線、つまり南部までの輸送、電信を、カーネギーの上司であるスコットに委ね、カーネギーはその「副官」となります。これはfujiyanの推測に過ぎませんが、輸送、電信の担当ということで軍事情報を得ることが出来るわけですので、大いにカーネギー(そしてスコット)の「個人投資」に役立ったのではないかと思います。彼は、収入の半分を「石油産業」に、残り半分を「鉄道会社」に投資していきます。 <「起業家」カーネギー誕生> 南北戦争終戦後の1865年、カーネギーは「ペンシルバニア鉄道」を円満退社し、「起業家」となります。 同年に「キーストーン・ブリッジ」社を創設します。「キーストーン・ブリッジ」社は、それまでの木製の橋を、耐久性に優れた鉄製にしていくというのがビジネスの目標でした。南北戦争は「鉄」の産出を飛躍させたわけですが、そのインフラを「平和目的」?に利用しよう、という考えでした。元上司スコットは、この会社創設時に、カーネギーの出資額の半分、80,000ドルをカーネギーに融資しています。 1867年「キーストーン・テレグラフ」社創設に繋がります。 「ペンシルバニア鉄道」の電線網に並列して、電信線を張り巡らす許可を得ました。(これは現代の日本でも、電気会社、鉄道会社が自身のルート沿いに電話線、光ファイバーなどを張り巡らりしているのと一緒ですよね)。ペンシルバニア州全域に張り巡らした電信網の価値は高く評価され、創設後すぐに「パシフィック・アンド・アトランティック・テレグラフ」社に買収され、三倍の投資利益となりました。 1868年彼は自分のライフ・プランを、自分自身への「手紙」という形式で書いています。35歳(1870年に相当)でビジネスを引退し、それまでに年間50,000ドルの収入を確保できるようにしておき、残りは社会貢献と自分自身への教育に注ぎたい、という内容でした。この「夢」はこの後約30年間達成することができませんでした。カーネギーは、「製鉄業」へと本腰で乗り出すことになるからです。 NYの「SoHo」地区は、「鋳鉄Cast-Iron」で出来ているビルで有名です。この「鋳鉄」は「硬い」のですが「脆(もろ)い」。ビルを高層にしたら「ポキッ」と折れてしまうかも知れませんね。鉄の「硬さ」は製鉄する過程で「純粋な鉄」に合金される「炭素」量の大小で決まるんだそうです。炭素の量が大きいと「硬くて脆い」、少ないと「柔らかい」。程好い「炭素」量が含まれ、程好い「硬さ」と程好い「柔軟性」を持つ、「鉄鋼」つまり「スティール steel」が高層ビル、橋などの大型建築物に適している、というわけです。 程好い硬さと柔軟性を持つ「鉄鋼」つまり「スティール steel」の大量生産が技術的に可能な方法を、英国で「ベッセマ−」という発明家が1856年発見し、それが実用化された後の1875年に、カーネギーは大型近代製鉄所を設立し、「鉄鋼王」への道を登り始めます。ちなみに1883年完成の、NYの「ブルックリン・ブリッジ」は、まさに「鉄鋼:スティール」による大型建築の見本ということができますね。 こちらに「寄り道:製鉄方法の歴史」としてまとめてみました。(2900文字程度)
まったくの「素人」が作ったものですが、よろしければご覧になってみて下さい。 (「寄り道」には、この「添書き:カーネギー」へ戻るリンクが貼ってあります。) <「鉄鋼王」、そして「労働者の味方」カーネギー> 1872年イギリスに「里帰り」したカーネギーは、ベッセマーの製鉄工場を見学、そして「鉄鋼」で作られていく英国のインフラを目の当りにし、今後アメリカで「鉄鋼:スティール」に莫大な需要があると判断しました。カーネギーが「フリーダム製鉄」社を設立した1861年は、「南北戦争」による鉄需要が見込まれ、終了した1865年に、鉄鋼の「平和利用」先として、「キーストーン・ブリッジ」社を立ち上げた一方で、製鉄方法はすでに「ベッセマー法」を用い始めていましたが、小規模なものだったようです。 カーネギーは鉄鋼業に莫大な投資を行うことを決意します。彼はビジネスチャンスがあると確信すると、一気に莫大な投資をすることを、信条としていました。 - カーネギーの言葉:「最初の人は牡蛎(カキ)を得、二番目の人はその殻を得る。」− 1873年の経済恐慌を経た1875年、カーネギーは「ベッセマ−方式」を用いた近代的で大規模な「Edgar Thomson Works エドガー・トムソン工場」をペンシルバニア州のピッツバーグのすぐ東にあるブラッドドック(Braddock)に立ち上げます。製鉄所の名前は、カーネギーがお世話になった、「ペンシルバニア鉄道」の社長の名前であり、 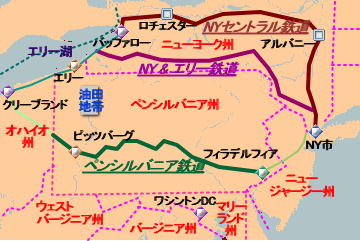 その社長、そして当時副社長のトーマス・スコットなどが出資者で、最初の注文は「ペンシルバニア鉄道」からの2000本のレールであり、その後も鉄道レールを「スティール」に変えていきます。 その社長、そして当時副社長のトーマス・スコットなどが出資者で、最初の注文は「ペンシルバニア鉄道」からの2000本のレールであり、その後も鉄道レールを「スティール」に変えていきます。「ペンシルバニア州」は、石油、石炭の産出地でもあり、鉄鉱石が多く眠る五大湖周辺にも近く、水運・鉄道運送にも恵まれていたため、当時のアメリカの工業中心地でした。 大量輸送を「ペンシルバニア鉄道」に発注し、しかもその役員がカーネギーの製鉄会社の大株主ですから、輸送運賃は割引(正確には「リベート」での払い戻し)で、近代大型工場での製品のコストの安さもあいまって、鉄鋼の価格競争力は高い。1883年には、ピッツバーグ近郊のライバル製鉄会社「ホームステッド工場」の買収を行うなど、企業体の規模を拡大していきます。 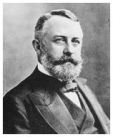 一方、製鉄に必要な「コークス」(「石炭」を蒸し焼きにしたもの)ですが、ペンシルバニア周辺では、「ヘンリー・クレイ・フリック」(Henry Clay Frick 1849-1919)が支配していました。フリックもカーネギーと同様に鉄鋼を中心とするコークスへの潜在需要を読んで、1873年の金融恐慌時に競争会社を次々と買収していました。もちろんカーネギーの製鉄業はフリックにとって最大のお得意さんでした。相互利益を図ろうということで、カーネギーはフリックと提携を試みます。カーネギーは、1881年にフリックのコークス会社に、資本の過半数の出資を行い、そしてフリックを「右腕」として迎えます。 一方、製鉄に必要な「コークス」(「石炭」を蒸し焼きにしたもの)ですが、ペンシルバニア周辺では、「ヘンリー・クレイ・フリック」(Henry Clay Frick 1849-1919)が支配していました。フリックもカーネギーと同様に鉄鋼を中心とするコークスへの潜在需要を読んで、1873年の金融恐慌時に競争会社を次々と買収していました。もちろんカーネギーの製鉄業はフリックにとって最大のお得意さんでした。相互利益を図ろうということで、カーネギーはフリックと提携を試みます。カーネギーは、1881年にフリックのコークス会社に、資本の過半数の出資を行い、そしてフリックを「右腕」として迎えます。この頃、産業化による貧富の差の拡大、つまり「資本家」と「労働者」の対立が激しくなっていきますが、カーネギー」は、「労働者、庶民の友である資本家」と見なされていました。 カーネギーは社会貢献を行っていきます。1882年、故郷のスコットランドのダンファームリンに、後に2,509を数える図書館寄贈の第一号を行い、1891年にはNYに「カーネギー・ホール」を100万ドルの資金で設立します。 そして彼は、 1886年に民主主義と資本主義を称える「Triumphant Democracy」(「勝利に満ちた民主主義」、ですかね?)を、そして、富裕層は社会に奉仕する道徳的責任を負うと述べた「Gospel of Wealth」(「富の福音」、ですかね?)を1889年に出版するなど、「庶民、そして労働者の味方である資本家富豪」として世間に受け止められました。 また当時の資本家としては画期的なことでしたが、「労働組合」の結成を支持したエッセイを1886年雑誌に発表し、翌1887年にフリックが「反ストライキ」で会社同盟を作ろうとしたときに激しく反対し、最後は「大株主」としてフリックを恫喝して諦めさせたこともあります。 しかし大企業体の「経営者」で「大富豪」であると同時に「労働者の友」というのは、矛盾することであり難しいものであった、と後年言われることになります。カーネギーはその当時の資本家としては、飛びぬけて労働者に理解が深かったものの、カーネギーの工場では、やはり低賃金、長時間労働でした。 <カーネギーの転機:「ホームステッド工場のストライキ(Homestead Strike」> 1892年「ホームステッド製鉄工場」でストライキが起こりました。 当時のアメリカでは、貧富の差が社会問題となり左翼的な労働運動が活発となっている上に、経済は長い不況になっていました。カーネギーとフリックは、低迷する経済状態、そして鉄鋼価格の下落を考慮した結果、労働者の要求に対して拒否することを基本線とします。そしてカーネギーはフリックに、「君の行うことは全面支持する」という手紙を残し、欧州旅行へと出かけている間に、悲劇は起こりました。  フリックは工場にフェンスを巡らし「ロックアウト」しますが、労働者側が工場の周りをガード、地元警察も排除。フリックは強硬手段に出ます。「ピンカートン探偵社」という、「警備会社」というか、多くの資本家が雇う御用達の「私設警察」を雇いました。「ピンカートン探偵社」の使途の一つがストライキ対策でして、工場の内部に入って確保させ、外部から別途採用した労働者(当時の「新移民」であった東欧系が大方だったそうですが)を送り込んで操業を再開するという、当時としては「標準的」な方法だったようです。 フリックは工場にフェンスを巡らし「ロックアウト」しますが、労働者側が工場の周りをガード、地元警察も排除。フリックは強硬手段に出ます。「ピンカートン探偵社」という、「警備会社」というか、多くの資本家が雇う御用達の「私設警察」を雇いました。「ピンカートン探偵社」の使途の一つがストライキ対策でして、工場の内部に入って確保させ、外部から別途採用した労働者(当時の「新移民」であった東欧系が大方だったそうですが)を送り込んで操業を再開するという、当時としては「標準的」な方法だったようです。 「探偵社」は深夜にボートで工場に近づいて中に入る予定でしたが、労働者側が川の上のボートを発見、ボートの内外で銃撃戦が始まってしまいました。14時間に渡る「戦闘」の最後には、労働者側は、燃え盛る列車をボートに向け突っ込ませ、そしてダイナマイトを放り込みボートを爆破、「探偵社」側は降伏しました。「探偵社」側3名、労働者側9名が死亡。 「探偵社」は深夜にボートで工場に近づいて中に入る予定でしたが、労働者側が川の上のボートを発見、ボートの内外で銃撃戦が始まってしまいました。14時間に渡る「戦闘」の最後には、労働者側は、燃え盛る列車をボートに向け突っ込ませ、そしてダイナマイトを放り込みボートを爆破、「探偵社」側は降伏しました。「探偵社」側3名、労働者側9名が死亡。血塗られた「戦闘」に勝利し意気上がる労働者側でしたが、事態を重く見たペンシルバニア州知事は「州兵」すなわち「正規兵」を派遣し、労働者側は鎮圧されました。 当時の労働運動に対して「資本家」たちは、基本的に強硬姿勢で臨んでおり、フリックが特別に高圧的であったわけではありません。カーネギー自身も「ピンカートン探偵社」を雇って別のストライキを粉砕したことが、これ以前にあります。しかし「戦闘状態」になったこの事件をきっかけに、カーネギーは「労働者の友」というイメージを失うことになってしまいました。 カーネギーはこの後、この事件に心が非常に傷ついた心境を友人宛ての手紙で打ち明けています。6年後、このホームステッドの地に戻ったカーネギーは、図書館、コンサート・ホール、体育館、水泳プールなどを寄贈します。しかし、彼はこの事件をその心に引きずり続けていくことになりました。 一方で、フリックはこの事件後、むしろこの事件の影響を利用しながら関連会社の労働組合を周到に解体へと追い込んでいきます。事の是非は置いておいて、フリックの資本家としての高い能力の一面です。しかし「労働組合」に関しては、意見の相違がもともと多いカーネギーとフリックでしたが、彼らには緊張関係が増していくことになります。 <カーネギー引退:フリックとの摩擦と、J.P.モルガンの買収> 「ホームステッド・ストライキ」以降、1900年には「カーネギー技術研究所」(現カーネギー=メロン大学)を700万ドル強で設立するなど、カーネギーはさらに「社会貢献」を行いました。 また国際平和活動にも乗り出しました。アメリカ・スペイン戦争(1898年)でのアメリカの勝利に終わりました。その終戦条約の内容はスペインから領土を得るものであり、アメリカは「領土拡張主義」「帝国主義」化したと、カーネギーは、小説家マーク・トウェインらとともに反対します。アメリカはスペインからフィリピンを2,000万ドルで購入することになったのですが、カーネギーは、フィリピン側に同額を寄贈し、フィリピンがスペインから自分自身を買い取りなさい、という提案をしました。結局、提案は採用されず、フィリピンとアメリカは戦争状態(1899-1902)となります。 一方、事業家としてのカーネギーですが、鉄鋼のみならず、それを加工した最終製品事業に乗り出そうと傘下の会社の再編成を行い、1899年「カーネギー製鉄」社を創設しました。しかしここでカーネギーとフリックの間の緊張関係が頂点となります。カーネギーは「ホームステッド・ストライキ」事件の責任をフリックに蒸し返して問いますが、フリックは「カーネギーが全面支持したではないか」、と泥仕合も。フリックは「カーネギー製鉄」を辞任。続いてフリックが保有する「カーネギー製鉄」株式の買取値段に関して、フリックは時価を、カーネギーは過去に得た恩恵を考慮という論点でそれよりもはるかに安い値段を主張、二人は争い、裁判沙汰になりますが、和解が成立しました。 1900年、カーネギー製鉄の生産量は、イギリス全体のそれを上回ることになりました。  しかし「カーネギー製鉄」を外側から狙っていた人物が居ました。「金融王」J.P.モルガン(1837-1913)です。電器、鉄道、通信など様々な業界の「統一」=「独占」を試みる彼は、鉄鋼業界統一を目指して「カーネギー製鉄」の買収に乗り出し、カーネギーに攻撃を仕掛けます。事業に疲労を覚える67歳という年齢を考慮し、社会貢献そして家族との生活を選んだカーネギーは、1901年モルガンに「カーネギー製鉄」を自分の「言い値」4億8000万ドルで売却。モルガンは言いました、「おめでとう、あなたは世界一の金持ちだ。」 しかし「カーネギー製鉄」を外側から狙っていた人物が居ました。「金融王」J.P.モルガン(1837-1913)です。電器、鉄道、通信など様々な業界の「統一」=「独占」を試みる彼は、鉄鋼業界統一を目指して「カーネギー製鉄」の買収に乗り出し、カーネギーに攻撃を仕掛けます。事業に疲労を覚える67歳という年齢を考慮し、社会貢献そして家族との生活を選んだカーネギーは、1901年モルガンに「カーネギー製鉄」を自分の「言い値」4億8000万ドルで売却。モルガンは言いました、「おめでとう、あなたは世界一の金持ちだ。」そしてモルガンは同年「カーネギー製鉄」を母体とし、「US スティール」社を創設、鉄鋼業の「独占」へと乗り出します。「US スティール」の役員の一人に、フリックが迎えられました。後年フリックはビジネスから引退し、「アッパー・イースト・サイド」の豪邸で、亡くなるまでの数年間を美術品のコレクションなどに明け暮れることになります。 <引退後のカーネギー:社会貢献と平和活動> ビジネスから引退したカーネギーは、1901年NYに居住を始め、33歳であった1968年に持っていた、35歳で引退し「社会貢献」したい、という「夢」を65歳で実現しました。母国であるイギリスと、アメリカに、数々の「社会貢献」機関を設立していきます。以下、名称はfujiyanの和訳付きで主なものをあげますと、 ・(1902) 「ワシントン・カーネギー研究所」(2000万ドル:全米の大学のためのリサーチ機関) ・(1903) 「カーネギー・ダンファームミン基金」(400万ドル:彼の故郷の生活向上目的) ・(1904) 「カーネギー・ヒーロー基金」(2000万ドル:人命救助を行った「ヒーロー」達等を表彰する機関) ・(1905) 「カーネギー教育年金基金」 :教師の地位向上目的機関。当初は教師の年金を中心。 その後、「カーネギー教育振興財団」という一般的なリサーチ機関へ。) そしておそらく自分の死後を考え、社会貢献事業の中心機関として ・(1911) 「ニューヨーク・カーネギー財団」:1億5000万ドル。当初は、カーネギーの社会貢献の 中核である図書館の寄贈が中心で2509ヶ所達成。その後、幅広い活動を行う。 ・(1913)「英国・カーネギー財団」:1000万ドル。当初は「図書館」寄贈中心で、その後幅広い活動。 そして、アメリカを含み「帝国主義」国たちの摩擦が激しくなり、きな臭くなるなかで、カーネギーは戦争抑止のための平和事業に力を注ぎます。「League of Nations」(「民族による連合」)を提唱した、最も初期の人間でした。 1910年、「カーネギー国際平和基金」を1000万ドルで創設。これは、全米最古の公的平和機関です。 1913年にはオランダのハーグに「平和宮殿」を設立、現在「国際司法裁判所」となっています。 そしてニューヨークに有識者を集め「平和会議」を開催した1914年、「チャーチ・ピース・ユニオン」(現「カーネギー倫理・国際問題評議会」)を設立、キリスト教ら宗教的な団体を、平和のために大連合させようという目的でした。 しかしカーネギーの願いもむなしく、「チャーチ・ピース・ユニオン」が1914年8月1日、ドイツ国内で会議を開催しようとしたその当日、ドイツがベルギーに侵攻、第一次世界大戦が勃発してしまいました。 カーネギーの妻、ルイーズによりますと、カーネギーはこの開戦の知らせにより、「心が砕け」てしまったそうです。彼の自伝日記は、第一次世界大戦の開戦日で終わってしまっています。 1916年にマサチューセッツに購入した住居で、1919年に亡くなりました。彼が生前に、社会貢献に注ぎ込んだのは、資産の90%に相当する3億5000万ドルでした。 彼はビジネス引退後の口癖は、「金持ちのままで死んだ者は、不評・恥辱のうちに死す。」 −−−− カーネギーを「偽善者」とする人々もいます。カーネギーも資本家であり、ペンシルバニアの資本家たちと連合し、鉄道の割引システムなど、有利なビジネス環境での大資本投下による良質、低価格で他の企業を圧迫してきました。また庶民を劣悪な条件で労働させていましたし、ストライキ対策として数々の手を打ってきました。しかし、これはフリックら当時の資本家は全員同じでした。 しかし、カーネギーにはやはり心の葛藤があったんでしょうね。引退後の、晴れ晴れとした社会貢献でのお金の「使いっぷり」は、やっぱり見事だと思います。ちょっとばかり使いすぎちゃって、(たぶん税率上昇もあいまって)彼の死後、未亡人ルイーズは「カーネギー・ホール」を売却しちゃうくらいに、財産を残してくれなかったんですから(笑)。 さてカーネギーは「フィランソロピストphilanthropist」でしたが、これは「篤志家」と一般的に日本語訳されています。一方fujiyanはこの稿で、彼の行為である「フィランソロピーphilanthropy」を訳すのに、「篤志」を使わず「社会貢献」としてみました。「社会貢献」には、「チャリティーcharity」と「フィランソロピーphilanthropy」があり、日本語、英語でも同様の意味合いで使われてしまっているようですが、ニューヨーク・カーネギー財団のサイト内「用語集」によると、本来この二つは相違しているそうです。 「チャリティー」は「誰かを問わずに困難に直面している人への即効の援助」のことで、日本語では「慈善」とおそらく訳されます。「飢餓」対策の「募金」などは即効性があり、「チャリティー」=「慈善」ですよね。 一方、「フィランソロピー」とは、「人間の進歩への促進援助」だそうで、人間が達成すべき「目標」を(達成には時間がかかるが)援助したい、というものです。「図書館を建設して、そこで万人が知識を得て欲しい」というのは、「フィランソロピー」ですよね。fujiyanとしては「志(こころざし)」が「篤(厚((あつ)い」い「行為」=「篤志行為」という訳が適正だと思います。しかしこの表現は、ちょっと馴染みが無いように思えましたので、「社会貢献」と訳してみました。ご了承下さい。 さらにニューヨーク・カーネギー財団の「用語集」によりますと、「フィランソロピー」に「富裕層が行うもの」という定義が近年含まれてしまいましたが元来は違うそうです。しかしカーネギーら欧米のお金持ちが巨額に行ってきた歴史があるため、そういう意味が入ってきてしまったようですね。ところで日本では「会社が行うもの」という定義が横行していますが、欧米の「富裕層」に匹敵する「個人」は日本ではいないので、「会社」、ということなんでしょうか?(苦笑)。
|
| 「マンハッタンを歩く」 のメニューへ |
トップページへ |