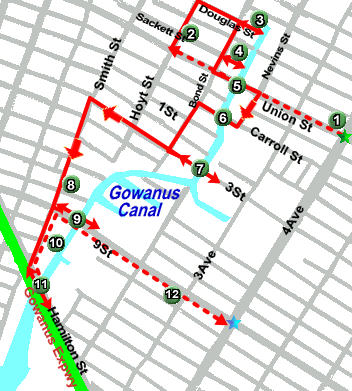| 地図中の数字付きボタンにて、JavaScriptを使用して写真をご案内しております。 全て新規画面設定ですので、まめに閉じてくださいネ。 |
||||
| このエリアが、NY近郊で、どのあたりかお知りになりたい方は、こちらをクリック! | ||||
今回は、「ブルックリン」の産業地帯である、ゴワナス運河 Gowanus Canal周辺を散歩して、運河にかかる橋とその周辺の工場、そしてグラフィティ(graffiti 落書きのような壁画)を拝見します。 緑の星印である、地下鉄N,R,MラインのUnion St駅からお散歩開始です。 (実は、Smith St沿いに、F,Gラインが走っていますので、その駅からスタートする方法もあります。) 駅から地上に出たら北側(地図では上)の遠くに、(1)大きな建物を拝見してお散歩スタート。
Union Stを西に歩きます。ここで、早速運河を橋で渡りますがまた戻ってきますので、なるべく見ないように通り過ぎます(笑)。 Hoyt Stで右折。大きな(2)教会を通り過ぎ、Douglas Stを右折して(3)運河のスタート地点を拝見。 Sackett Stは、(4)行き止まりです。隣の、(5)Union Stで橋を渡りまして、運河の東側のNevins Stを経由して、個性的な(6)Carroll Stの橋で西側に戻ります。 Bond Streetで運河に平行に下り、(7)3rd Streetの橋に向かいます。3rd Street Bridgeはモダンな橋ですが、ここから後の橋は、運河を下るにつれて大型になっていきます。 ここから運河は西に大きくカーブしますのでSmith Streetまで、大きく西にでます。(8)地下鉄の高架、を見ながらしばらく歩きますと、(9)9th Streetの橋に辿り着きます。 (10)スクラップ工場の向こうに高架が見えたら、運河の最後の(11)Hamilton Stの大型の橋です。これで運河の散策はおしまい。 (9)9th Street Bridgeに戻って、9th Streetを東へと渡り、(12)壁画を拝見して、4Aveの地下鉄の駅で、お散歩終了です。 このお散歩は、運河沿いの旧工業地帯の中を歩きます。あまり人通りの無いエリアでしたので、ご注意下さい。fujiyanの持つお散歩本には、運河見物は、運河の西側を中心に歩いた方が治安的に良い旨、述べていました。 「ゴワナス運河 Gowanus Canal」は、インディアンの酋長の名を採った「ゴワニーズ川 Gowanees Creek」と呼ばれた小川の、「ゴワナス湾 Gowanus Bay」へと注ぐ河口に作られたものです。 ニューヨークのオランダ統治時代である、1600年代前半の「ニューアムステルダム」当時、この河口は牡蠣の名産地だったそうです。あるオランダ人の旅行記に、「この国で最高」と書かれたほど評判が良く、欧州向けの輸出商品となりました。 1600年代の後半、ブルックリンで栽培されたトウモロコシの製粉所建設のため、川の上流はせき止められ、ゴワン川はその流れを失い、いわば「溝」となりました。 その後、穀物が地元消費を越える生産量へと増大したため、余剰穀物を他の地域で販売するための輸送の必要性から、この河口を船が通行できるように「溝」を拡大した「運河」が作られました。これが「ゴワナス運河 Gowanus Canal」の始まりです。深さ6フィート、幅12.5フィートで、岸に人力で船を引っ張るための歩道がついた運河が、黒人奴隷により作られました。 1776年ブルックリンは、独立戦争で英米軍の「ロングアイランドの戦い」(「ローワーマンハッタン」散歩の添書きご参照)の舞台でした。破れた米軍は撤退中に、このゴワナス運河を含む、ゴワン川にかかる橋を次々と破壊し、英軍の更なる前進を少しく食い止めたというわけです。 1800年代半ばからは、「ヘルズ・キッチン」散歩でご案内したように、ニューヨークの産業拡大期で、特にハドソン川とアメリカ中西部を結ぶ「エリー運河」が開通(1825年)し、ニューヨークは物流の中心となりました。それに呼応し1849年から60年代までゴワナス運河は幅、深さを拡大、そして現在のダグラス・ストリートまで延長されました。その両岸には隔壁つきの多くのドックが並び、「エリー運河」が運んできた、中西部の穀物の一大集積地となり、また石炭の集積地ともなります。その後、集積した物資の加工工場が続々と建設され、ゴワナス運河周辺は急速に産業化しました。 この当時、産業化したのは、「ヘルズ・キッチン」も同様でしたが、運河という引き込みはあり、ゴワナス湾という開けた場所もあるということで、「ヘルズ・キッチン」よりも数段上の産業化だったようです。 しかし栄えたのは良いのですが、産業廃棄物と生活下水で「公害」が発生、一マイル先でも臭う、ひどい異臭地帯となりました。 20世紀初頭には、アメリカで最も栄えた運河となり、運河両岸そしてゴワナス湾沿いには、屠殺場、鋳物、石工、セメント、製紙、製粉、製鉄、石鹸、接着剤、陶器等などの工場が立ち並び、産業廃棄物によりエリアの環境は更に悪化の一途をたどります。それに加えて周辺の住民の生活下水も運河に流れ込み、この運河は、汚染されつくした溝、となりました。 黒い泥の泡が浮かんでは破裂し、水が泡で渦巻いているようだったと、雑誌New Yorkerに描かれていたそうです。当時、ゴアナス運河に付けられたニックネーム、「ラベンダーの湖 Lavender Lake」は、染物工場からの廃水でその日ごとに川の色が変化するからだそうです。また、「Perfume Creek」とも呼ばれました。Perfumeとは「香水」のことで、その異臭に対する皮肉でしょうね。水質の有害さは凄まじく、それを利用して、木造船をこの運河に引き入れて、船底にへばりついたフジツボを殺して除去していたそうです(苦笑)。また水質調査によると、マラリア、腸チフスなどが検出されました。しかし、周辺の住民は貧困層でその危険もあまり流布しておらず、母親が喘息持ちの子供を運河に連れて行き、その水面からの蒸気を吸引させていたという話もあるそうです(泣)。 この状態の改善のため、1911年、運河に水流を流すシステムが備わりました。それは、上記お散歩地図での左側である西の方向の、イーストリバー河口の先である、ミルクバター海峡の海水を通す、直径12フィート、全長6280フィートのトンネルがこの運河先端のDouglas Streetまで掘削され、そのトンネル内に廃棄船から取り出した巨大スクリューで水流を起こすというものです。英語で「flush」と書かれていましたが、これはトイレの水をジャーっと流すことですから、このシステムは運河が汚れたと思ったら、まさにトイレの水を流すように稼動させて、運河の水を海へと流す、ということなんでしょうね。これにより異臭はそうとう抑えられ、環境は格段に改善したそうです。 さてこの運河ですが、1960年代から物流の中心は、比較的小規模な輸送は船から車・トラックとなり、大規模輸送は依然として船でしたが、コンテナ化とそれに伴う船の大型化に小さなゴワナス運河は対応できず、今では運河の運搬船通行は、非常に少なくなったそうで、それに従って工業地帯としては寂れ気味になってしまいました。 1961年にそのスクリューは、作業員が落としたマンホールのフタで破損しました。しかし、近所の下水処理システムが運河水質維持に十分と行政は判断し、修理をしませんでしたが、これが計算違い(苦笑)。運河の水質は悪化の一途、計算違いをした市当局はたまにドブさらいをしていく程度でした。 こうして運河も汚くなっていく一方、周辺エリアはさらに寂れ始め、1970年代にはエリアの50%は未使用地になってしまったそうです。その後、地域コミュニティーが水流システムの再稼動を含む、エリア再開発に努力を続けます。その結果、故障してから40年弱たった、1999年5月にこの水流システムが再稼働しましたが、最後は潜水ダイバーが川底の泥を手作業で掻き揚げるということになりました。あっと言う間に、運河にカニや魚が戻ってきたそうです。 ------ とまあ、きれいになった運河、と書いてみた次第ですが、実はfujiyanが実際にお散歩した2002年春、かすかですが異臭が漂っていました(苦笑)。 実は、ダグラス・ストリートの、運河終点=流水の出口近辺は、金網が張られていて、流水口そのものを見ることが、通常の場合出来ないはずなんです。しかし散歩の時に、 多分、近所から「異臭がする」とクレームがあったのでは、と推察しますが、行政関係の思しき人々が入り込んでいて運河を調べていたため金網の出入り口が開いていました。fujiyanは便乗して入り込んで、流水口を撮影した次第(笑)。 今回の散歩では、グラフィティ(壁画)が多かったです。マンハッタンでは少なくなったと言われている、ヒップ・ホップ文化の代表であるこのグラフィティですが、ここブルックリンの工業地帯では、たくさん残されているようですね。
|
| 「マンハッタンを歩く」 のメニューへ |
トップページへ |