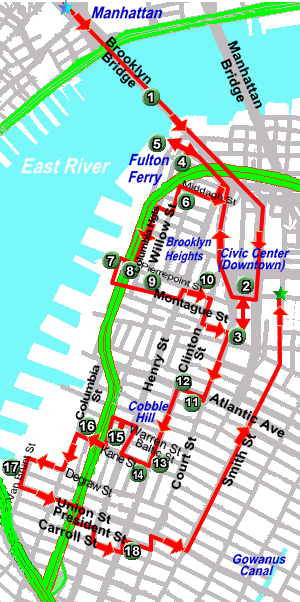| 地図中の数字付きボタンにて、JavaScriptを使用して写真をご案内しております。 全て新規画面設定ですので、まめに閉じてくださいネ。 |
||||
| このエリアが、NY近郊で、どのあたりかお知りになりたい方は、こちらをクリック! | ||||
今回は、マンハッタンを離れて、イースト・リバーを隔てたお隣、「ブルックリン」の中央部を歩きます。 ここは、1812年のフェリー開通からマンハッタンと結ばれ、特に1883年のブルックリン・ブリッジ開通により、栄えていきました。 青の星印である、マンハッタン側の地下鉄「シティー・ホール/ブルックリン・ブリッジ」駅からお散歩開始。
まずは(1)ブルックリン・ブリッジの歩道を渡り、イースト・リバーの上から様々な風景を楽しみます。ブルックリン側についたら、長ーくてチョット飽きてしまう(苦笑)アプローチを降りたら、(2)(3)ブルックリンの行政区域であるダウンタウンです。 まずはイースト・リバーに出るために坂を下っていきます。海運と物資集積が栄えていた時代の元(4)倉庫を経て、マンハッタンとブルックリンを繋いでいた(5)フェリーの元乗り場へ。 降りてきた坂を登って、今度は古い住宅街(6)ブルックリン・ハイツを歩きます。ブルックリン・ハイツは1814年のフェリー開通により人々が集まり始めましたが、1883年のブルックリン・ブリッジ開通前後に更に住居が増えた場所。 川沿いの高台からマンハッタンを望むことが出来る(7)プロムナードへと向かいます。川を離れて内側に戻ったら、(8)住居そして(9)スポーツ・クラブや(10)教会を拝見。 さらに南(地図では下)へと歩きます。(11)(12)アトランティック・アベニューを経て、(13)コッブル・ヒルへ。ここもブルックリン・ハイツと同様、ブルックリン・ブリッジ開通で住居が増えました。(14)教会、そして(17)全米初の低所得者層向け住居があります。 高速道路を越えて、川沿いへ。(16)グラフィティ(壁画)を超えると、(17)水運のための設備があります。内陸へと戻り、(18)教会を経由し、「スミス・ストリート」と呼ばれる、ブルックリンで注目されている通りを経て、ダウンタウンから地下鉄に乗って帰ります。 「ブルックリン」は、「マンハッタン」島を「イースト・リバー」で隔てた、東のお隣にある大きな島=「ロング・アイランド」の一部です。「ロング・アイランド」内で、マンハッタンに接した部分の、南側が「ブルックリン」、北側は「クィーンズ」ですね。 「ブルックリン」(Brooklyn)は、オランダ統治時代は「Breuckelen」と言う名で、英語では「Broken Land」、つまり壊れた土地というあまり印象のよくない名前でした。 (英国サッカーのスーパースター、ベッカム選手の長男の名前は「ブルックリン」君だそうですが、ベッカム選手は由来を知っているのかなぁ?チョット心配しているんですケド(苦笑)。) 独立戦争当初の1776年、ブルックリンで米英軍が戦った「ロング・アイランドの戦い」を経て、独立後、英軍が引き上げた1783年時、ブルックリンの人口は1500人をやや超えた程度だったそうです。 その後、1814年にマンハッタンとブルックリンを結ぶ定期フェリー蒸気船(1924年に廃止)が運行を開始し、ブルックリン側のフェリー乗り場に近く、高台であった「ブルックリン・ハイツ」に居住が進みます。現在のブルックリンにあたるエリアの人口は、1840年代に10万人を少し下回る数字まで拡大しました。 「現在のブルックリンにあたるエリア」と書きましたのは、「ブルックリン」はそもそも、今回のお散歩エリア周辺だけであり、「キングス郡(Kings County)」の一部で「Town of Brooklyn」=「ブルックリン町」でした。そこで、今回のお散歩のタイトルを「オールド・ブルックリン」とした次第です。 「ブルックリン町」は1834年に、わずか16,000人弱の人口で「ブルックリン市 City of Brooklyn」となりました。おそらく税と予算の関係、つまり「町」クラスに留まれば上部自治体のキングス郡からの補助金が期待できる等だと思いますが、この「市」への昇格は「無謀だ!」という声も多かったようです。1854年に北側の「ウィリアムズバーグ市」他と合併、「ブルックリン市」は拡大していき、「隣町」との合併を1896年まで続け、ほぼ現在の地域となりました。 ちなみに、各エリアが独自のデザインで道路整備を進めたあとに、ブルックリン市へと合併していきましたので、マンハッタンのようにきれいな「碁盤の目」が出来上がらず、縦横斜めに入り組んだ道路網になってしまったようです。 <ブルックリンは、1898年「拡大ニューヨーク市」へ> 元々の「ニューヨーク市」とは「マンハッタン島」だけ(とその飛び地)でした。1898年「ブルックリン」、「クィーンズ」、「ブロンクス」そして「スタテン島」が「ニューヨーク市」に加わり、「Greater New York」(「拡大ニューヨーク」という感じでしょうかね?)と呼ばれることになります。 時代はやや遡りますが、1867年にNYを訪れた英国作家チャールズ・ディケンズは、ブルックリンを「ニューヨークに対して、眠っている町」と評しました。この時は、「拡大ニューヨーク」合併前ですから、ディケンズの言う「ニューヨーク」とは「マンハッタン」のことです。マンハッタンの隆盛と比すると、あまり活発な町ではなかったようですね。 その後、ブルックリン内でイースト・リバーに近い場所は、マンハッタンの文化圏、経済圏拡大に取り込まれていったわけです。そして「ブルックリン・ブリッジ」が1883年開通したことがそれを決定付け、人々はここイースト・リバー沿いから東の内陸部へと広がり始めます。同年に、ブルックリン・ブリッジで横断する(おそらくケーブル式の)「鉄道」も開通しました。 その後、ブルックリンのみならずブロンクス、あるいはクィーンズ、スタテン島がマンハッタン文化・経済圏に取り込まれ、地下鉄などで繋ぎ合わせていく計画もあいまって、不動産ディベロッパーを中心に「拡大ニューヨーク」構想が盛り上がり、1894年住民投票が行われ、98年「拡大ニューヨーク」市が誕生した次第。 「拡大ニューヨーク」により、「ブルックリン」を含めた上記5つのエリアは「Boroughボロ−」という「(行政)区」となりました。ちなみに近隣エリアを吸収し続けた「ブルックリン市」はその頃、深刻な財政危機に落ちっており、この「拡大ニューヨーク」で救われたそうです。「ブルックリン市」は1900年において、人口が100万人を超えることになりました。 <「ブルックリン」は工業エリア> さて時代を振り返りますと、ブルックリンは、NYの工業地帯でした。 上記地図の右上「マンハッタン・ブリッジ」を、少し北東の辺りにアメリカ海軍の造船所が1801年作られ、「南北戦争」(1861-65)から、「第二次世界大戦」(1941-45)まで軍艦を建造、修理を続け、1966年まで存在しましたが、これが「工業」の第一号と言えそうです。 1825年にNY州中部で「エリー運河」が開通し、NYは五大湖と結ばれ物流の中心となりブルックリンの川沿いは港湾業、倉庫が栄えます。「南北戦争」からのアメリカ産業革命では「ゴワナス運河」などで工業化は進み、1880年には全米で4番目の工業生産量でした。労働者として1880年以降は、移民の第二次ピークが訪れ、南欧系(イタリア等)、東欧系(チェコ、ハンガリーなどの「ボヘミア」系、そしてロシア帝国迫害下にあったユダヤ系等)がブルックリンに職を求めてやってきました。 1898年「拡大ニューヨーク」発足後、1903年「ウィリアムズバーグ・ブリッジ」、1910年「マンハッタン・ブリッジ」という二つの橋もかかり、1908年ブルックリンに初めての地下鉄がマンハッタンから到達、ますますマンハッタンへの便が良くなっていきます。 ブルックリン内部では既に多くの高架式鉄道、路面電車が走っておりました。基本的に、マンハッタンへの入り口である、「ブルックリン・ブリッジ」、「ウィリアムズバーグ・ブリッジ」とその橋の足元にあるフェリー乗り場、などを基点としていました。それらの鉄道会社が「Brooklyn Rapid Transit」社(「BRT」)として1896年大同団結し、マンハッタンを中心とする「Interborough Rapid Transit」社(「IRT」)とともに、マンハッタンとブルックリン間の交通網を整備していきます。 いわゆる「地下鉄」網に関しては、別ページの添書きをご参照いただきたいと思いますが、こちらに、ブルックリンの1930年代で「トロリー」を主軸とした「バス路線図」があります。ホント縦横無尽に走っていますね。ちなみに1883年に創設され1957年にロスアンジェルスに本拠を移した、「ブルックリン・ドジャーズ」の球団名である「ドジャーズ=Dodgers」の由来ですが、「dodge」とは「避ける」ということで、ブルックリンの人達はトロリーなどの路面電車をヒョイと「避ける」のが非常に上手だったことに、発しているとか。 さらにちなみに「ブルックリン・ドジャーズ」は、黒人初の大リーガー「ジャッキー・ロビンソン」(1919-72)を産んだことでも有名です。ロビンソンは、黒人リーグでプレーしていましたが、1945年秋に「ブルックリン・ドジャーズ」とマイナー契約し、1947年大リーグに昇格、二塁手として活躍。現役10年間の通算成績では、打率.311、1518安打、そして6回ワールドシリーズに出場しました。 1929年からの大不況時代(-45?)は、ブルックリンにももちろん深刻な影響を与えますが、1941年からの第二次世界大戦(-45)は、海軍造船所を含み軍需景気をもたらします。しかし長続きはしませんでした。多くの企業は「大工場」に相応しい広い土地を求めて、ブルックリンから郊外へと転出、1966年には海軍造船所も閉鎖されました。1954年に23万5千人を数えた産業勤労者も、70年には20万人を切ります。 マンハッタンの「ベッドタウン」としては、自動車=「モータリゼーション」の波もあいまって、今回のお散歩コースを飛び越えて、ブルックリンのさらに奥へ「郊外」に人々は行ってしまいます。特に、今回のお散歩エリアである、ブルックリンの中心地は寂れていきました。 1970年からは地域復興の努力が始まり、マンハッタンに本社を持つIBM社がその組織の一部をブルックリンに移したり、1977年に商店街「フルトン・モール」が出来たりしましたが、1960年代には全米3位のビジネスエリアであった、ブルックリンのダウンタウンは6位まで下落し、1980年代には産業雇用者は10万人を下回りました。1990年代にアメリカの急激な景気回復に伴い、今回のお散歩エリアを含むブルックリンがマンハッタンのベッドタウンとして見直される一方、ハイテク業界のMetroTech社がブルックリン中心地に進出し、数千人の雇用者を導きいれるなど経済的な向上を見せましたが、昨今の全米を覆う不景気により、ブルックリンの経済的な地位の行方は不透明です。 ------ 今回の散歩のテーマは、まずはやっぱりイースト・リバー越しのマンハッタン島見物でした。 一方、噂には聞いていたんですが、行き交う人達がしゃべる言葉−「ブルックリン訛り」というものですが、これを堪能することができました。ホントに強烈で、ぜんぜん違う。特になぜかブルックリンでは、人々が「つるんで」歩いているという印象があります。グループで群れて、あの「ブルックリン訛り」でしゃべっているのと行き違うと、カルチャーショックであるとともに、けっこう怖く感じたというのが、本音ですね(苦笑)。 さらにご興味のある方は、以下をクリック!
|
| 「マンハッタンを歩く」 のメニューへ |
トップページへ |